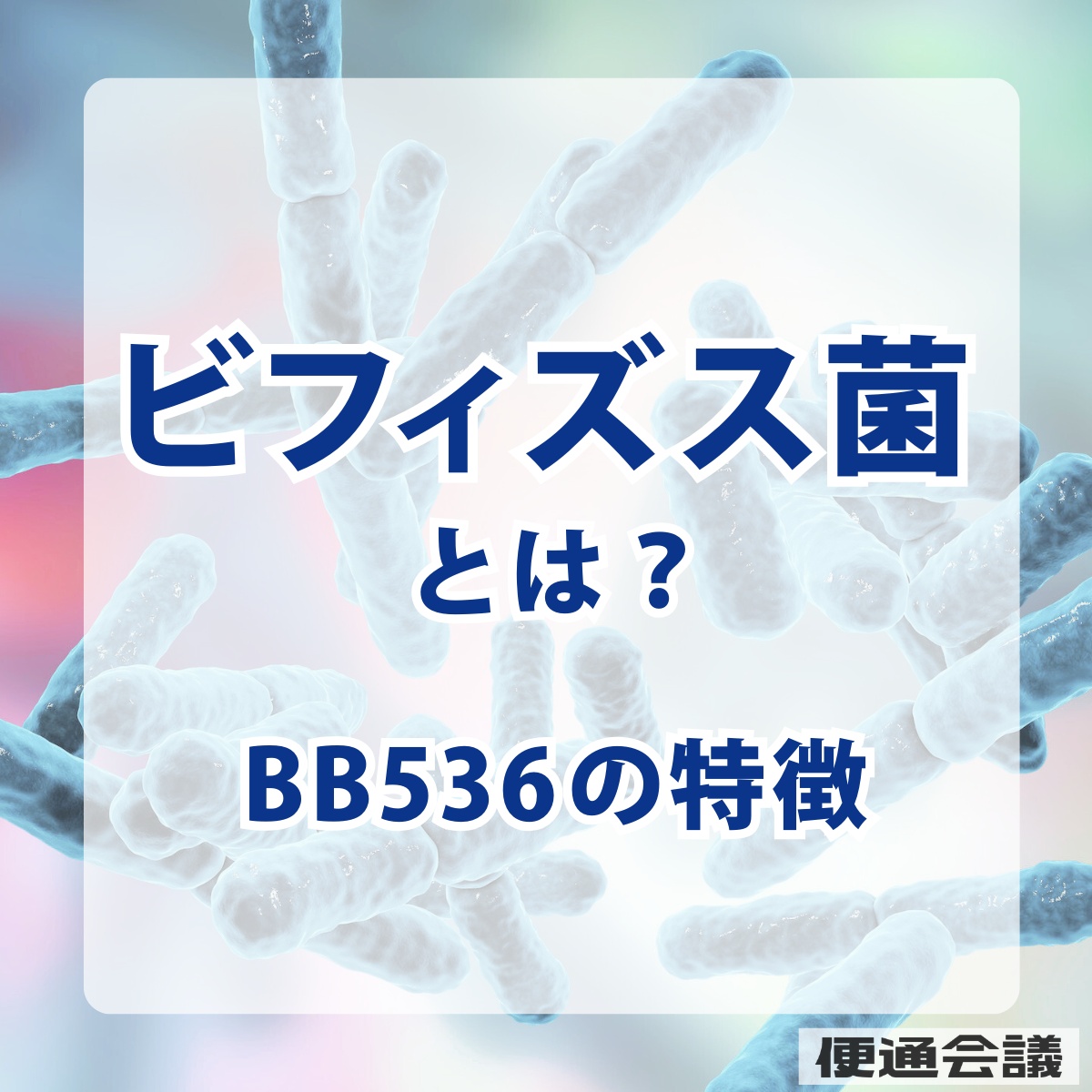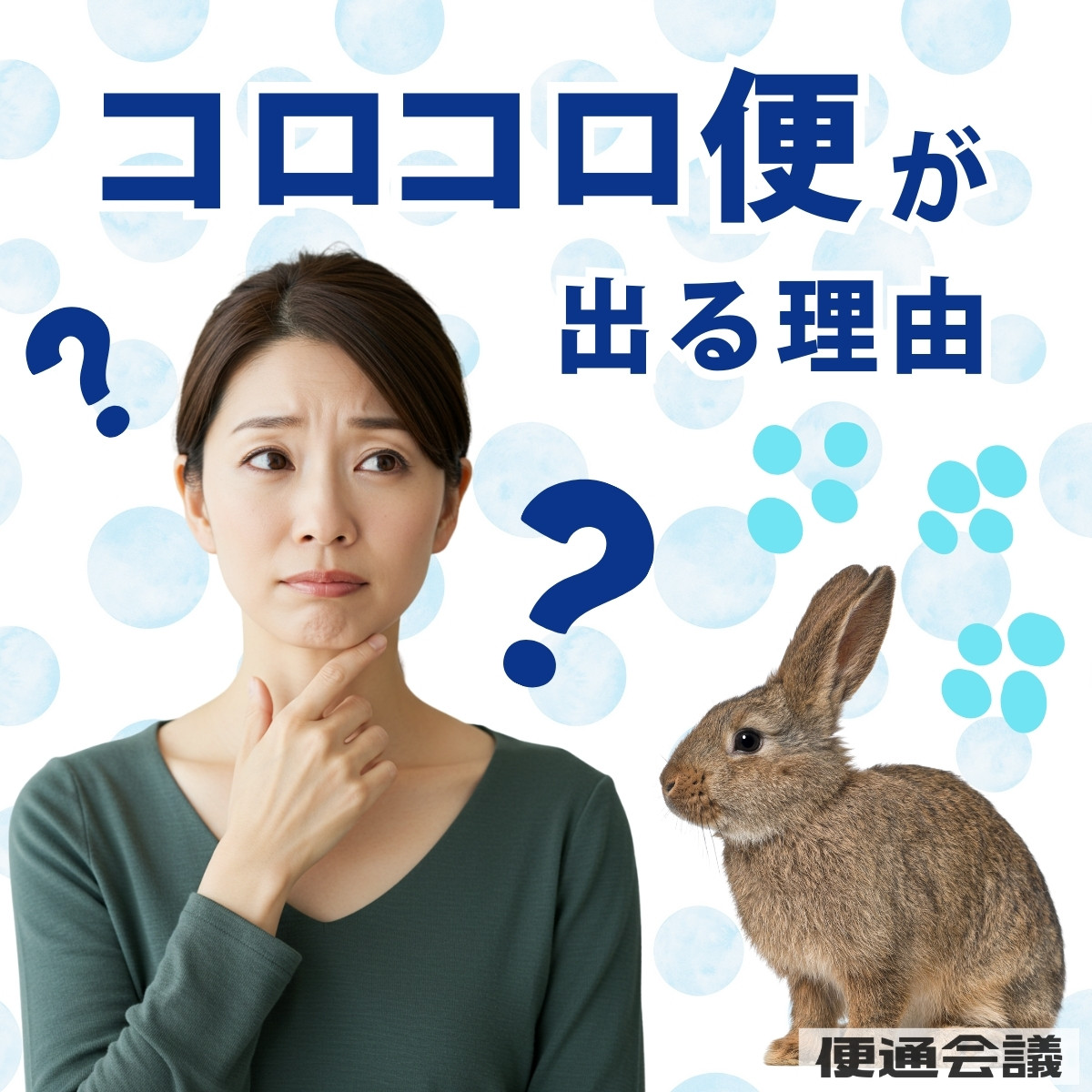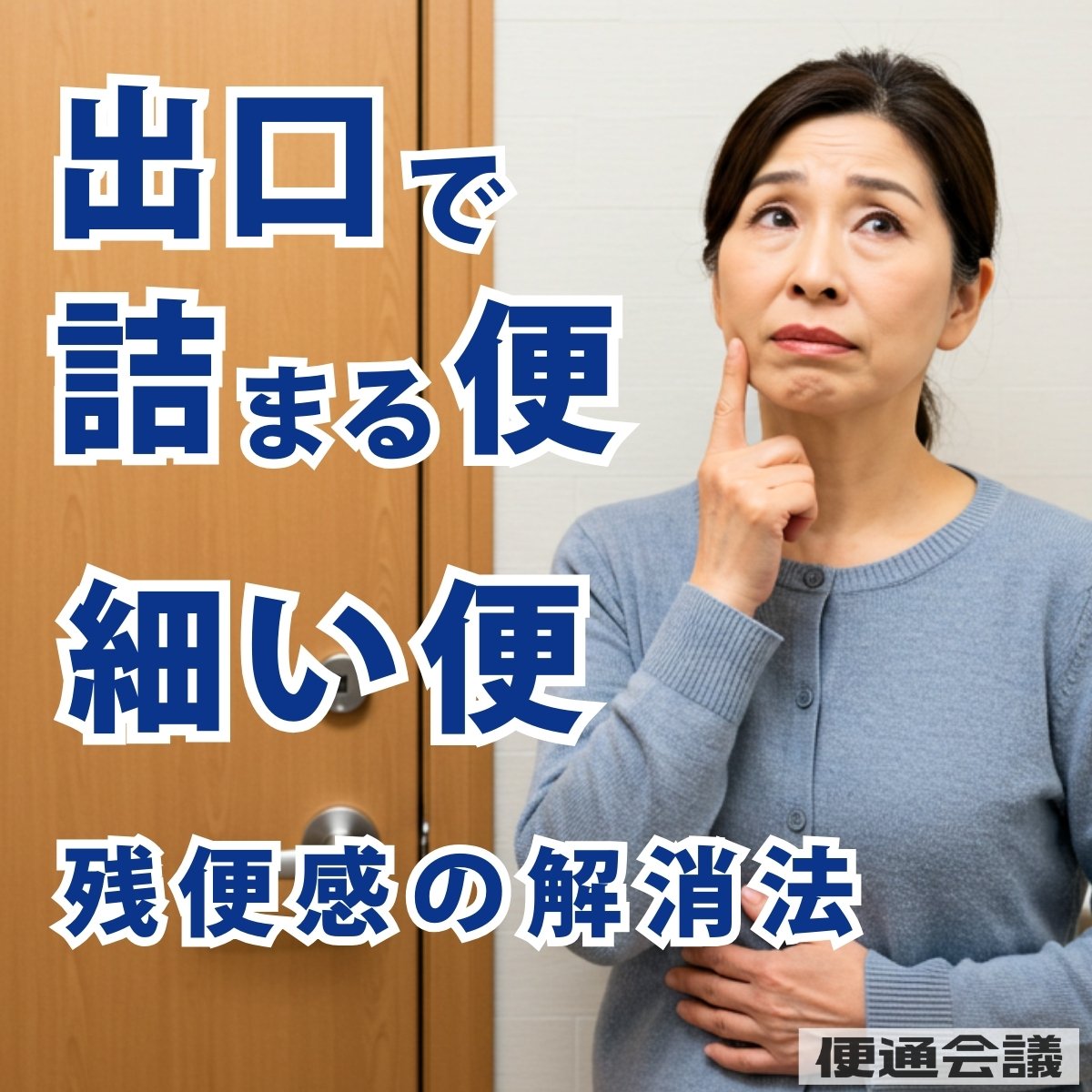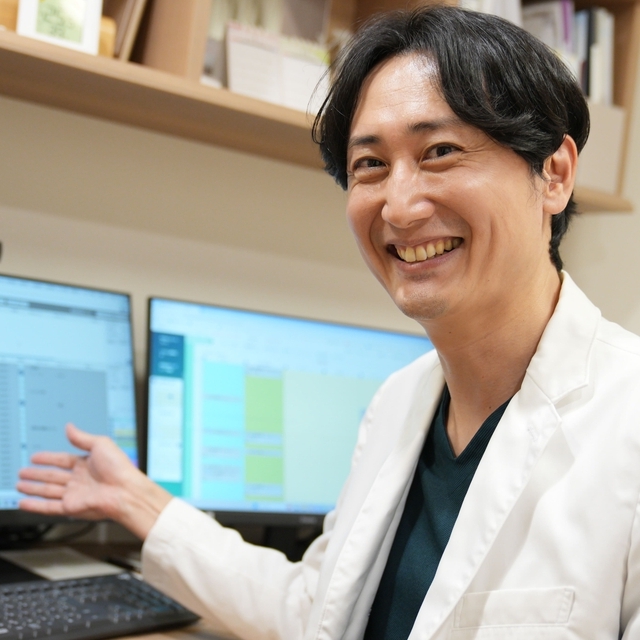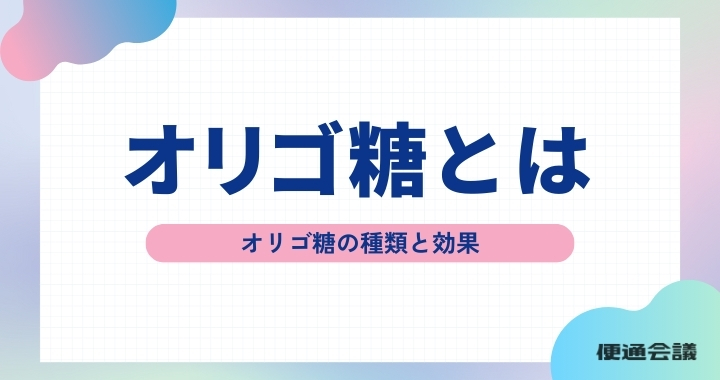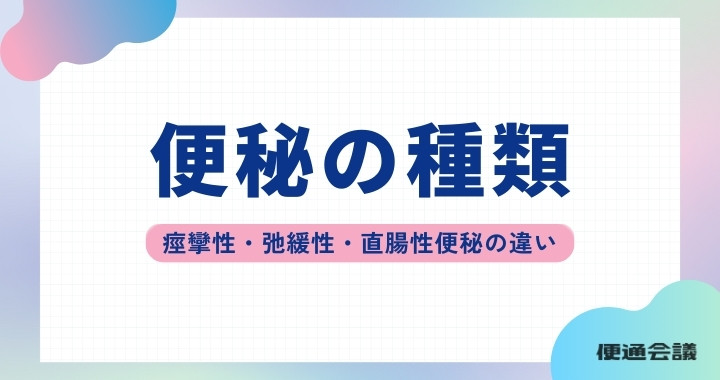最終更新日:2025.12.5
中学生の便秘の原因と解消法|家庭でできる腸活習慣と受診の目安

「中学生になってから便秘が増えた」「子どもが便秘を気にしているけど、どうすればいいの?」。
思春期の訪れとともに、便秘で悩むことが増えるお子さんは少なくありません。
中学生の便秘には、体の成長に伴うホルモンの変化や学校での排便我慢、生活習慣の乱れなど、思春期特有の原因が隠れています。
本記事では、中学生の便秘が起こる原因を詳しく解説し、家庭でできる具体的な解消法や腸活習慣を紹介します。
保護者の方に向けて、安心して中学生のお子さんを支えられる、すぐに役立つ実践的な情報をお届けします。
目次
中学生の便秘の原因|思春期特有の理由と生活習慣
中学生が便秘になりやすい理由は、一つではありません。
思春期は、体も心も大きく変化する時期であるため、複数の要因が重なっているケースが珍しくないのです。
まずは、中学生が便秘になる原因として多いものを挙げていきます。
1. 思春期特有のホルモンバランスの乱れ
中学生の体は急激に成長し、性ホルモンの分泌が活発になります。
このホルモン変化は、自律神経に影響を及ぼし、腸の蠕動運動を鈍らせてスムーズな便通を阻害する原因の一つです。
特に女子は初潮前後にホルモンの揺らぎが大きく、便秘や下腹部の不快感を訴えることが増えます。
2. 学校でトイレを我慢してしまう心理的要因
「排便時の音が気になる」「トイレ後の臭いが恥ずかしい」。
思春期の中学生にとって、学校のトイレは心理的に使いにくいものです。
そのため、便意を我慢する中学生も少なくありません。
日常的に便意を我慢すると、肛門付近に便が到達しても便意が起きにくい「直腸性便秘」になるリスクが高くなります。
直腸性便秘になると、気付かないうちに便が腸内に滞留。滞留した便は腸内で水分を吸収されて硬くなり、排便が難しくなるという悪循環に陥るのです。

3. 朝食抜き・不規則な生活リズム
中学生になると、部活動や塾で帰宅が遅くなる日が多くなることも。
夕食や就寝の時間が後ろにずれることで、起床時間がギリギリになり、朝食を食べないまま登校する子どもも少なくないでしょう。
中学生を対象にした自律神経と生活習慣との関連についての調査では、「朝食を食べない」と回答した子どもは約20%、「食事時間がやや不規則・不規則」と回答した子どもは50%以上にのぼりました(※)。

朝食は、腸を刺激して排便リズムを整える重要なスイッチです。そのため、朝食を食べないと便意が起こりにくくなり、便秘を招く原因になります。
不安定な中学生の排便習慣を整えて便通をサポート!「腸まで届くビフィズス菌」+「オリゴ糖」の便通特化サプリとは!?…>>詳しく見る
4. 座りっぱなしで運動不足
スマホやゲームで座りっぱなしの時間が多いと、腸の動きが鈍くなり、便秘がちになります。
また、排便に必要な筋力が低下し、ちゃんと便が出せなくなっている可能性も少なくありません。
5. 食物繊維が足りない食生活
ファストフードや炭酸飲料、スナック菓子を食べることが多い食生活では、水分や食物繊維が不足傾向に。
便が硬くなり、排便がスムーズにいかなくなります。

このように、中学生の便秘は「体の変化」「学校での我慢」「生活習慣の乱れ」が複合的に絡んで引き起こされているケースが珍しくありません。
だからこそ、家庭でのサポートが欠かせないのです。
中学生の便秘改善に役立つ腸活習慣|毎日の生活に自然に取り入れる
便秘薬を使えば一時的には解消できますが、思春期で体が不安定な中学生は、できる限り自然な形で便通を改善できるのが理想です。
そのカギとなるのが、生活習慣の積み重ね。中学生の生活リズムに合う腸活を続けることで、快適な便通が習慣化していきます。
それでは、今日からすぐにできる「中学生の腸活」を紹介します。
1. 食物繊維と発酵食品を取り入れた食事
食事は腸活の基本です。簡単なメニューでも良いので、朝食を必ずとる習慣をつけましょう。
朝食を食べることで体温が上昇し、活動の準備が整います。
また、食事から摂取したブドウ糖が脳のエネルギーとなり、集中力を高めて学習効率を良くします。
- 朝食例:ヨーグルト+バナナ+全粒パン(またはおにぎり)
- 昼食例(お弁当の工夫):卵焼きにほうれん草や小松菜を混ぜる、サラダに豆やコーンを追加
- 夕食例:野菜たっぷりの味噌汁+サバや鮭などの魚料理
- おやつ:ナッツ、干し芋、ドライフルーツ、無糖ヨーグルトにきな粉をかける
ポイントは「一品足すだけ」。例えば、味噌汁にきのこを足す、サラダに豆を入れるなど、ちょっとした工夫で食物繊維と発酵食品を同時に取り入れられます。

2. 朝の3分トイレ習慣を身につける
たとえ便意がなくても「朝食後に3分間トイレに座る」習慣を続けると、排便リズムが身につきます。
保護者が声掛けして、一緒に「朝の準備の一部」として定着させるのが効果的です。
3. 水分・油(オリーブオイルなど)で便を柔らかくする
スムーズな排便のために、便を柔らかくする工夫も大切です。
水分は1日1〜1.5リットルを目安として、こまめに補給しましょう。
また、オリーブオイルやごま油など良質な油を食事に取り入れるのもおすすめです。
適量の脂質を摂ることで、便が腸内をスムーズに移動できるようになり、便秘解消効果が期待できます。
4. 軽い運動やストレッチで腸を刺激する
激しい運動でなくても、朝のストレッチやラジオ体操、通学時のウォーキングで十分です。
特に「お腹をひねる動き」や「腹筋を使う運動」は、腸の蠕動運動を促します。
5. ストレスケアやリラックス法を取り入れる
ストレスは、便秘の大きな要因です。
中学生は高校受験の勉強や、人間関係の悩みなど、思春期特有のデリケートさでストレスをためがち。
ストレスをためて自律神経が乱れると、腸の動きも鈍くなります。
家庭では「お風呂でリラックス」「寝る前におしゃべり」「読書や音楽で落ち着く時間」などを設け、心のケアを意識してあげましょう。

6. 睡眠と生活リズムを整える
腸の働きは自律神経と深く関わっています。夜更かしや不規則な睡眠は便秘の原因に。
- 目標就寝時間:夜11時までにベッドへ
- スマホルール:寝る30分前に手放す → メラトニン分泌が促され、眠りが深くなる
- 朝のリズム:起きたらカーテンを開けて朝日を浴びると体内時計がリセットされ、腸の動きもスムーズに
睡眠の改善は腸だけでなく、集中力や肌トラブルの改善にもつながるため、中学生にとってメリットが実感しやすいでしょう。

7. 学校生活に合わせた工夫も忘れずに
腸活は「特別なこと」ではなく、学校生活の中で自然にできる工夫が大事です。
- 水分補給:部活バッグに水筒を必ず入れる(1日1.5Lを目安に)
- 休み時間:友達と階段を使って歩く → 軽い運動が腸の刺激に
- おやつ持参:個包装のドライフルーツや小袋ナッツをカバンに入れておく
8. 腸活サプリを活用する
食事や生活習慣を見直しても便秘が改善しない場合は、ビフィズス菌やオリゴ糖を配合した腸活サプリを活用するのも一つの手段です。
手軽に習慣化できるので、部活や高校受験で忙しい中学生でも続けやすく、親子で一緒に腸活を始めるきっかけになります。
例えば朝食やおやつのタイミングで摂取するだけでも、腸内環境にアプローチできます。
便秘改善には、便秘薬などの特別な薬や大掛かりな工夫よりも 、毎日の小さな積み重ねが効果的です。
中学生の生活に合った腸活習慣を取り入れて、便秘しにくい体づくりを進めましょう。

中学生の便通をサポート!毎日の腸活に取り入れたい腸まで届くビフィズス菌サプリとは!?…>>詳しく見る
中学生の便秘で医療機関を受診すべきサイン|保護者が知っておくポイント
生活習慣を見直しても改善しない場合や、以下のような異常がある場合は、医療機関への受診が必要です。
- 3日以上排便がない、腹痛が強い
- 便に血が混じる、嘔吐を伴うなど異常がある
- 食事や生活改善をしても良くならない
思春期の子どもは「恥ずかしい」「大げさだと思われたくない」という気持ちから受診を嫌がることがあります。
そんなときは、保護者が先に相談窓口に電話して状況を確認する、女性医師や小児科を選ぶなど安心感を与えることが大切です。
「薬をもらうと体が楽になるかも」と前向きに声をかけると、子どもも受診に前向きになりやすくなります。

中学生の便秘まとめ|家庭でできるサポートと予防のポイント
中学生の便秘は「ホルモンの変化」「学校での我慢」「生活習慣の乱れ」が重なって起こります。
解消には、朝食+トイレ習慣、運動や水分・食物繊維の工夫、規則正しい睡眠が欠かせません。
さらに、毎日の食事や生活改善だけでは便秘が改善しにくい場合は、ビフィズス菌やオリゴ糖を配合した腸活サプリの活用も有効です。
手軽に取り入れられ、忙しい中学生でも続けやすく、親子で一緒に腸活習慣を始めるきっかけになります。

部活や高校受験など忙しい毎日を送る中学生は、腸内環境が乱れがちです。
生活習慣の改善に加え、サプリを上手に活用することで、お子さんの健やかな成長と快適な毎日を支えることができます。
中学生の思春期特有の心理にも配慮しつつ、本人だけではなく保護者が一緒に対応するが肝心です。
まずは、今日からすぐにできることを親子で始めましょう。
中学生のお子さんの便秘が気になる保護者の方へ
生活習慣や食生活の見直しに、腸活サプリをプラス。
ビフィズス菌とオリゴ糖で内側からサポート。
習慣にしやすいシンプルな腸活、始めてみませんか?
【参考資料・出典】
※堀田法子, et al. "中学生・高校生の自律神経性愁訴と生活習慣との関連について." 学校保健研究 43.1 (2001): 73-82.

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。