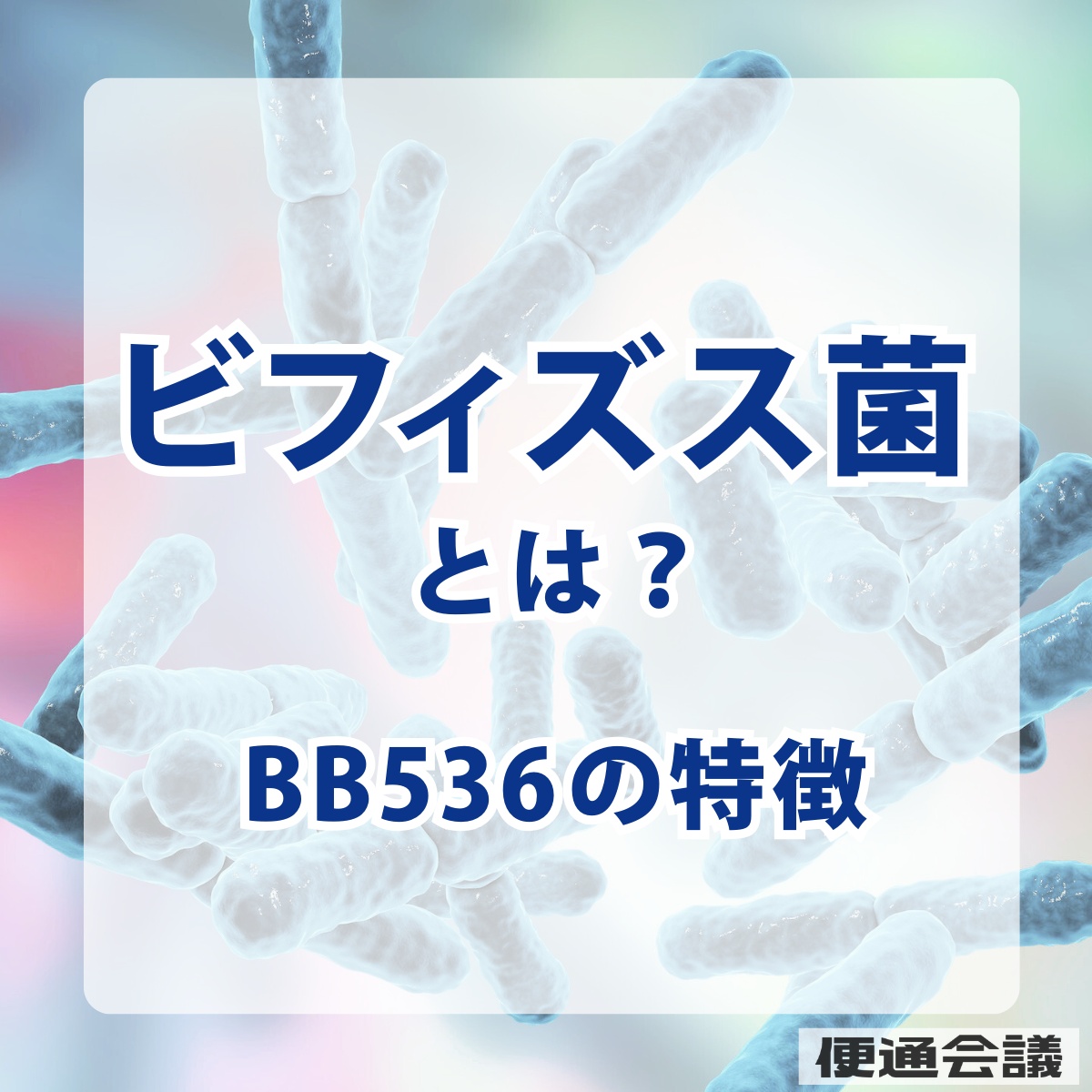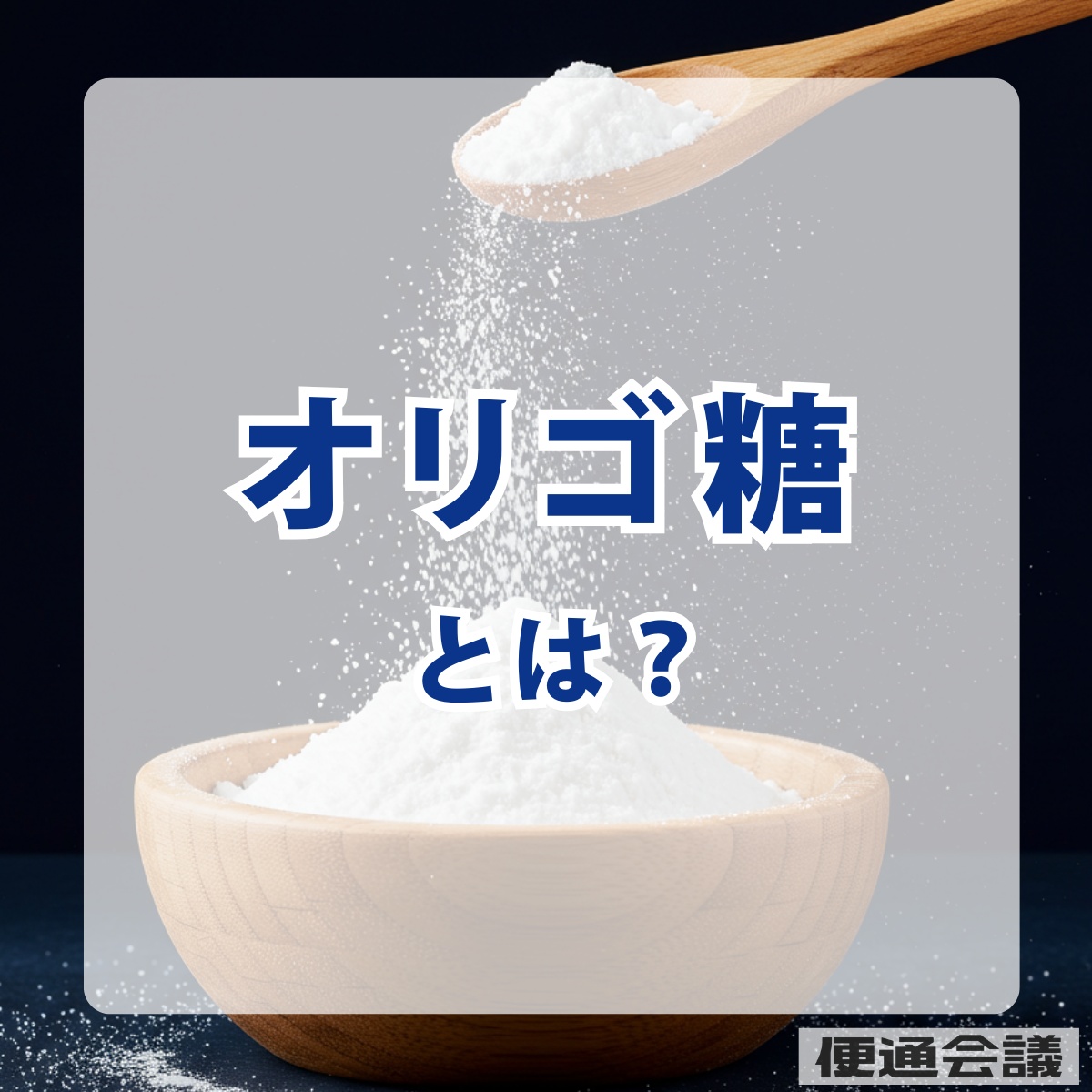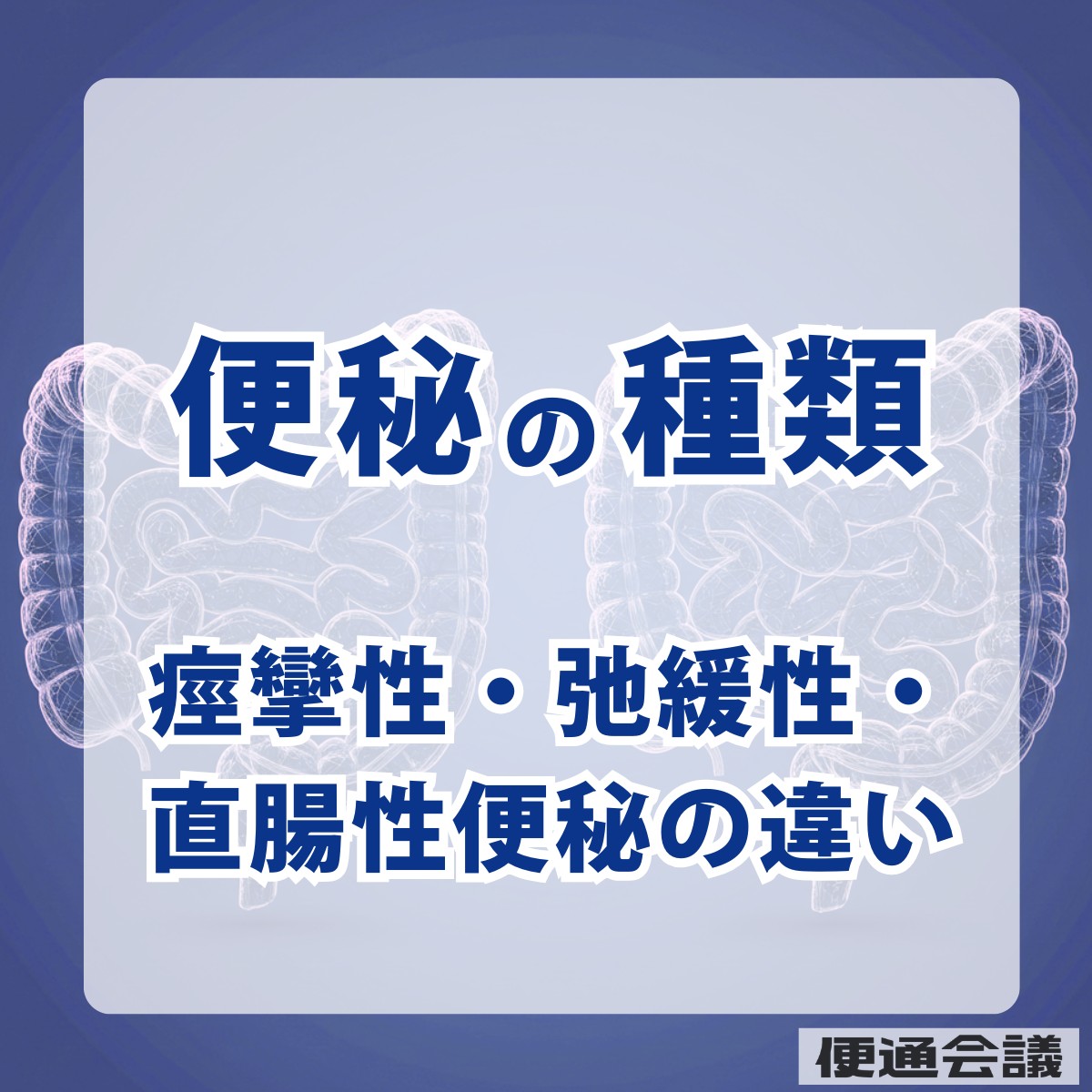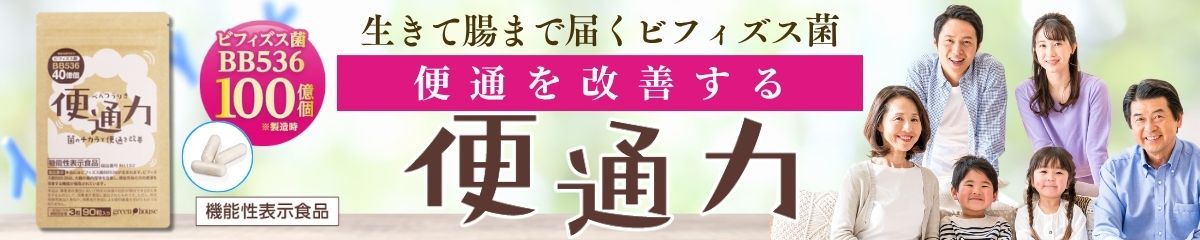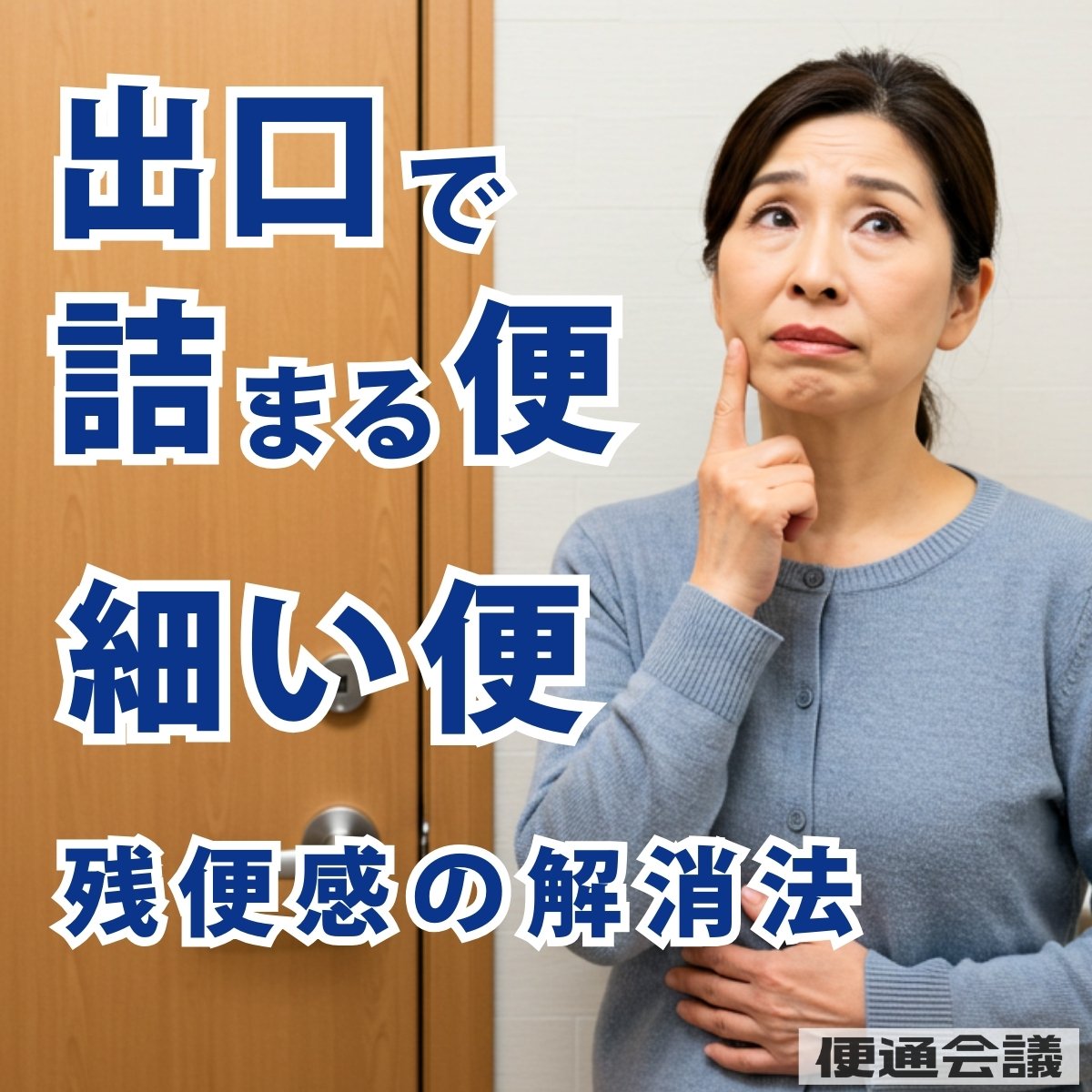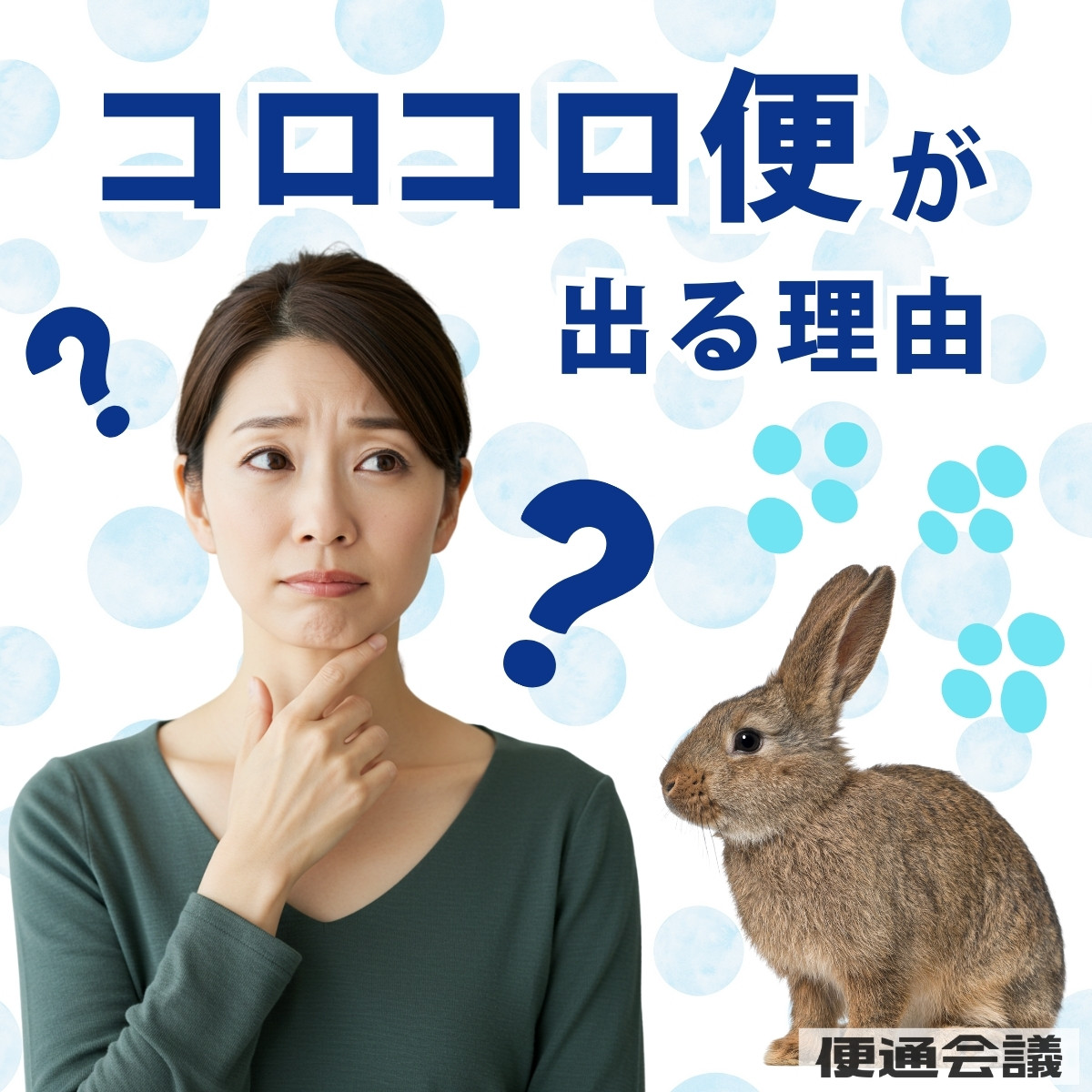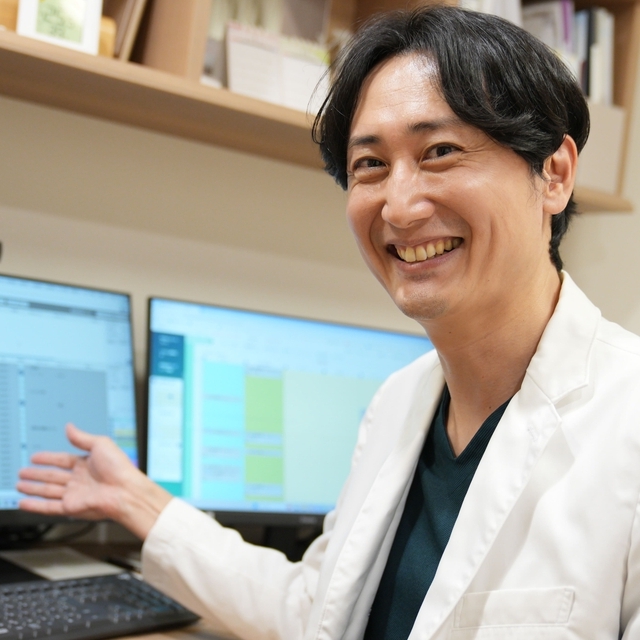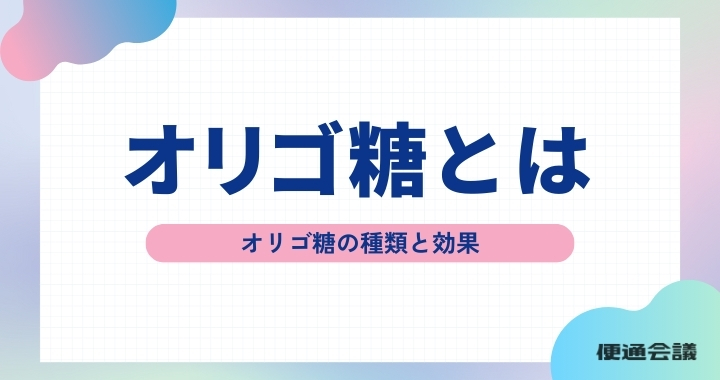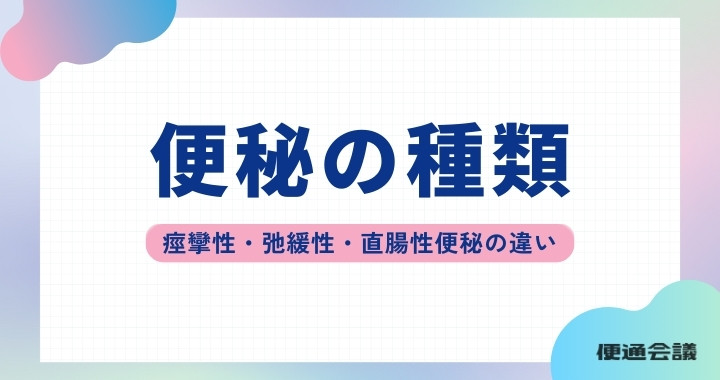最終更新日:2025.11.04
ビフィズス菌サプリでシミ・毛穴改善?最新試験の結果から見る皮膚への影響

「腸と肌はつながっている」――そんな話を聞いたことはありませんか?
近年、腸内環境を整える食品やサプリ(プロバイオティクス)を口から摂ることで、肌の健康にも良い影響があることが注目されています。
今回ご紹介するのは、順天堂大学の研究チームが行った最新の臨床試験。
ビフィズス菌の一種であるビフィドバクテリウム・ブレーベM-16V(ビフィズス菌M-16V)の摂取と女性の肌に起きた変化について、科学的に検証したものです。
「腸内環境と肌の関係」は本当?
私たちの腸内には、100兆個以上ともいわれる腸内細菌がすみついています。
腸内細菌には、大きく分けて「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の3種類があり、いわゆる「腸内環境が良い」状態は、善玉菌が多いことを指します。
しかし、善玉菌が減って悪玉菌が増加すると、腸内環境は悪化。便秘やお腹の張りだけでなく、肌の乾燥や炎症、くすみといった悪影響を全身に及ぼします。
このような腸と肌の相互関係は「腸皮膚相関(Gut-Skin Axis)」と呼ばれ、注目を集めている研究テーマです。

腸内環境の悪化が皮膚に悪影響を及ぼすメカニズム
腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れて悪玉菌が優勢になると、微生物代謝物が血中に放出されます。
その血液が皮膚に到達すると、表皮細胞に影響を及ぼし、皮膚の水分量やバリア機能の低下を引き起こすことがあります。
その結果、肌荒れや乾燥などのトラブルが起こりやすくなるのです。
これまでの研究では、アトピー性皮膚炎やニキビ、乾癬といった皮膚疾患のある人では、腸内細菌のバランスが崩れている傾向が報告されています。
一方で、プロバイオティクス(ビフィズス菌などの生きた善玉菌)を摂取することで、多くの皮膚トラブルに対して改善効果が期待できることも分かってきました。
研究の概要:ビフィズス菌で肌は変化する?
今回の研究は、日本の30〜79歳の健康な女性120名を対象に行われました。
参加者はランダムに2つのグループに分けられ、12週間にわたってサプリを摂取しました。
▶試験対象と摂取内容
- ビフィドバクテリウム群:59名(平均年齢46.6±12.3歳)
1袋に1×10¹⁰ CFU(=100億個相当)を含み、1日2袋、合計2×10¹⁰ CFU(=約200億個)/日を摂取 - プラセボ群:61名(平均年齢47.2±10.9歳)
乳酸菌を含まない、見た目・味が同じ食品を摂取
肌の状態は、専用の高精度カメラ「VISIA」で0週・4週・8週・12週のタイミングで撮影し、毛穴・シミ・しわ・全体の肌状態などをスコア化しました。
さらに便サンプルと皮膚の表面サンプルを採取して、腸内や皮膚の細菌バランスも解析しています。

結果:シミ・毛穴スコアが改善、肌の悪化を抑制
解析の結果、ビフィズス菌を摂取したグループでは次のような変化が見られました。
▶試験結果のまとめ
- 肌全体の状態:プラセボ群では8週目に悪化が見られましたが、ビフィズス菌群では悪化が抑えられました。
- 褐色斑(シミスコア):4週目・8週目で有意に改善しました。
- 毛穴スコア:4・8・12週目にかけて改善傾向が持続しました。
つまり、ビフィズス菌M-16Vの摂取は「肌の悪化を防ぎながら、毛穴やシミのスコアを改善する可能性」があると報告されました。
これは、腸内環境を整えることが肌のコンディション維持に役立つ可能性を裏付ける貴重な結果といえるでしょう。
腸内環境の変化:50歳以上の女性で善玉菌Blautiaが増加
ビフィズス菌の摂取は、腸内細菌叢の構成にも影響を与えることが分かりました。
参加者の便を解析した結果、ビフィズス菌群摂取群では腸内のBlautia(ブラウティア)属が増加。
特に50歳以上の参加者で有意な増加が確認されており、年齢による腸内環境の違いに応じた効果が示唆されます。
▶ブラウティア菌とは?
- 代表的な善玉菌で、短鎖脂肪酸の一種「酢酸」を作り出します。
- 酢酸には、腸内を弱酸性に保ち、炎症を抑える働きがあります。そのため、腸内の安定と肌の健やかさを保つためには欠かせません。
腸内細菌の多様性は加齢とともに低下しやすいため、50代以降の女性でこのような変化が見られたのは興味深いポイントです。

安全性:12週間の摂取でも問題なし
12週間の試験期間を通じて、ビフィズス菌群とプラセボ群の間で有害事象の発生率に差はありませんでした。
腹部の不快感や下痢なども大きな変化はなく、研究者は「本用量では安全に摂取できる」と報告しています。
ただし、今回の研究は中規模(120名)・短期間(12週間)であるため、より長期的な安全性や作用メカニズムの解明は今後の課題とされています。
腸からはじまる「美肌習慣」
今回の研究は、「腸と肌はつながっている」という考え方を裏付ける大きな一歩です。
特に、年齢とともに気になるシミ・毛穴・ハリの低下といった肌悩みが、「腸内環境を整えること」で改善する可能性があるという点は、これまでのスキンケア発想を変える内容でしょう。
もちろん、ビフィズス菌の摂取だけで劇的に肌が変わるわけではありません。
しかし、毎日の腸活習慣――食物繊維やオリゴ糖を摂り、発酵食品を取り入れるといった工夫に加えて、こうしたプロバイオティクスを上手に組み合わせることで、「内側から整える美容」を実践できる時代が来ています。

腸から始める美肌ケア | 研究が示す現実的な期待値
今回の順天堂大学の研究により、ビフィズス菌M-16Vの12週間摂取は、女性の肌において「褐色斑(シミ)や毛穴スコアの改善傾向」を示し、特に50歳以上では善玉菌Blautiaの増加も確認されました。
これは、腸内環境を整えることが肌の健康維持に役立つ可能性を示す新たなエビデンスといえるでしょう。
腸と肌をともに整える“内側からの美肌ケア”が、これからの美容習慣のキーワードになりそうです。
【出典・参考資料】
※服部和裕, et al. "アトピー性皮膚炎患児に対するビフィズス菌末の投与が児の腸内細菌叢とアレルギー症状に与える影響の検討." アレルギー 52.1 (2003): 20-30.
腸内環境を効率的に整えたいあなたへ
自然のチカラで体に優しい便通習慣
ビフィズス菌BB536とオリゴ糖で内側からサポート。
習慣にしやすいシンプルな腸活、始めてみませんか?

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。