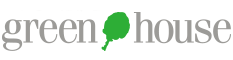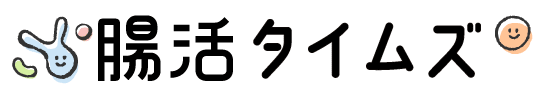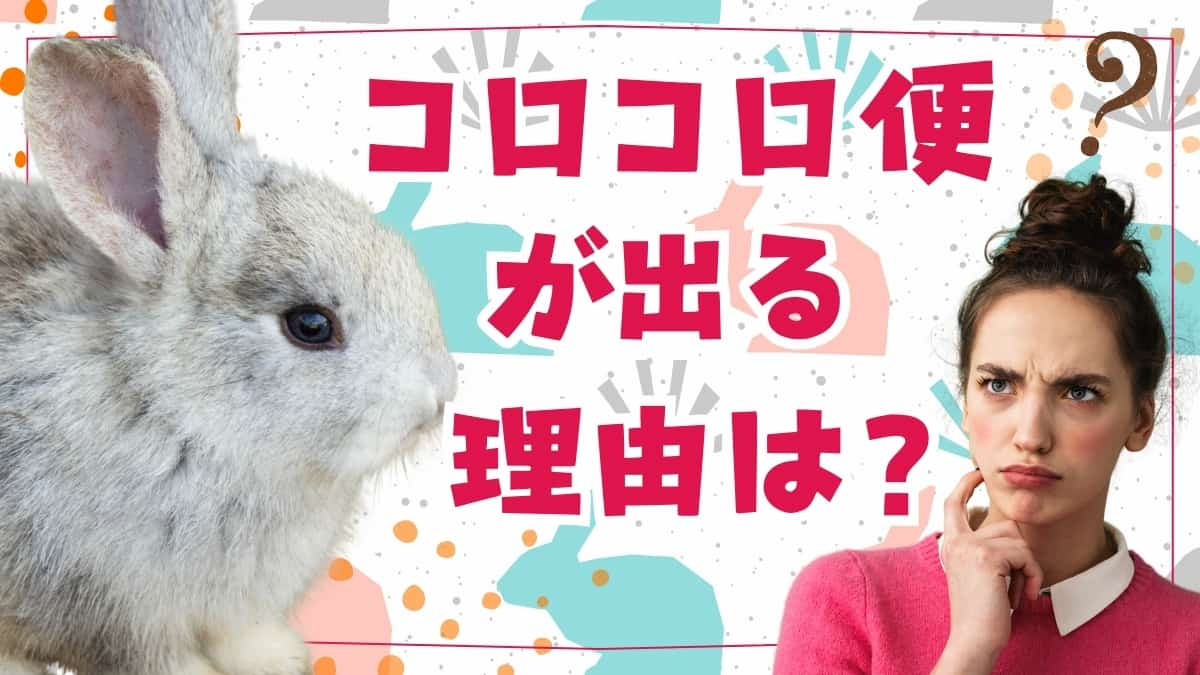便意がないのに便秘?|原因と便意を取り戻す方法を徹底解説
最終更新日:2025.07.07

便秘でつらいのに「便意が全くない…」と感じることはありませんか?
実は便意を感じない便秘は、放置すると便が腸にたまり腸内環境が悪化し、慢性化や深刻な体調不良につながるリスクがあります。
この記事では、便意がなくなる原因から、今すぐ実践できる生活習慣の改善やセルフケアまでをわかりやすく解説。
薬に頼らず自然に便意を呼び戻し、根本から便秘を改善したい方は必見です。
便意がない便秘の原因と対策を理解し、スッキリ快適な毎日を目指しましょう。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会
食品保健指導士
・管理栄養士
目次
そもそも便意とは?感じなくなるとどうなる?
便意は、直腸に便が届いたことを腸が感知し、脳が「出したい」と判断することで生まれます。
この“排便のサイン”は、腸と脳がしっかりと連携してこそ自然に働くものです。
しかし、生活習慣やストレスの影響で腸と脳の「会話」がうまくいかなくなると、そのサインは徐々に感じられなくなってしまいます。
その結果、
- ▶︎便が溜まり続け、腸内環境が悪化
- ▶︎ぽっこりお腹、肌荒れ、疲労感などの症状
- ▶︎食欲不振やメンタルの不調も
「たかが便秘」と軽視するには、あまりにも深刻な影響が潜んでいるのです。
便意を感じない便秘の主な原因|直腸性便秘とは?
「便意がない=便秘がない」わけではありません。
実際は直腸に便が滞留しているのに、その感覚を脳がキャッチできなくなっているのです。
では、なぜこの“便意センサー”が働かなくなってしまうのでしょうか?
以下に主な原因を詳しく紹介します。
①直腸性便秘|“出したい感覚”がマヒしている状態
もっとも多いのが「直腸性便秘」です。
これは、便が直腸に届いても、排便反射が起きにくくなるタイプの便秘。
以下のような生活習慣が原因となります。
-
▶︎ 排便を何度も我慢する習慣(忙しさ・外出先でのトイレ回避)
-
▶︎ 毎日の下剤・浣腸の使用で“出してもらう”癖がついてしまった
-
▶︎ 無理なダイエットによる食事制限で、腸に便が届きにくくなっている
長期間こうした生活が続くと、直腸に便があっても脳が「便意」を感じにくくなり、“出すタイミングを逃し続ける”悪循環に陥ります。

②自律神経の乱れ|腸と脳の信号がストップ
私たちの腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、自律神経と密接につながっています。
通常、リラックスしているとき(副交感神経が優位)に腸は活発に働きます。
しかし、
-
▶︎慢性的なストレス
-
▶︎緊張や不安の多い生活
-
▶︎夜型や不規則な生活習慣
これらが続くと交感神経が優位になり、腸の動きが鈍化。
腸から脳への「そろそろ出したいよ!」というサインが届かなくなります。
③内臓の冷え・血流不足|腸の温度が感覚を鈍らせる
「手足の冷え」は感じやすい一方で、「腸の冷え」は自覚しにくいのが特徴。
-
▶︎薄着や冷たい飲食物の摂りすぎ
-
▶︎筋力の低下による基礎代謝の低下
-
▶︎クーラー環境での長時間滞在
これらの要因が積み重なると腸の血流が滞り、神経の伝達やぜん動運動が鈍くなって便意そのものが生まれにくくなります。

④加齢による神経・筋力の衰え
年齢を重ねると、腸の働きそのものが衰えていきます。
特に、
-
▶︎神経の伝達速度の低下
-
▶︎腹筋や骨盤底筋群の筋力低下
-
▶︎水分摂取量の減少
などが重なることで、排便に必要な感覚や力が弱まり、便意を感じにくくなる傾向があります。
これは高齢者に多く見られる原因のひとつです。
⑤腸内環境の乱れ|悪玉菌の優位で腸が停滞
近年注目されているのが、「腸内フローラの乱れ」です。
-
▶︎食物繊維不足
-
▶︎発酵食品をあまり摂らない
-
▶︎抗生物質の服用歴がある
このような生活が続くと、善玉菌が減り、悪玉菌が優位な腸内環境になります。
すると腸のぜん動運動が弱まり、便意が起きにくくなるのです。
▼ 便意のサインが届かない方へ。“穏やかな実感”を大切にしたケア習慣>>詳しくはこちら
便意を目覚めさせる「五感刺激メソッド」
「食事や運動、生活習慣には気をつけているのに、なかなか便意が戻らない」 そんな方にぜひ試してほしいのが、“五感”に着目したアプローチです。
実は、便意は腸だけでなく脳の“思い込み”にも大きく左右されます。 そこで、眠っている便意センサーを呼び覚ますために、感覚を活用して“脳をだます”習慣を日常に取り入れてみましょう。
視覚:トイレの照明を変える
やわらかい電球色の光や自然光に近い照明は、副交感神経を優位にして腸をリラックスモードに導きます。
反対に、蛍光灯のような白く強い光は緊張を高めることもあります。
朝のトイレは自然光とやわらかい間接照明の組み合わせがベストです。

聴覚:「腸の音浴」習慣で副交感神経を優位に
腸の動きは自律神経によって支配されています。 そのため、リラックスを促す「音浴」も腸への間接的な刺激になります。
- 波の音や小川のせせらぎなどの自然音
- 腸内環境に良いとされる528Hzなどのヒーリング周波数
音楽療法と腸活を掛け合わせた新しいアプローチです。
嗅覚:リラックス系アロマを活用
腸はストレスにとても敏感です。 ラベンダー、スイートオレンジ、ベルガモットなどの香りは自律神経を整え、腸の緊張をほぐします。
朝のトイレにリラックスできる香りのスプレーをひと吹きして、香りで「出せる状態」にスイッチを入れましょう。
触覚:お腹を温めるだけでなく“なでる”
腸の働きにとって冷えは大敵です。 「おへその下(丹田)」を温めると腸の動きが促進されます。
湯たんぽやカイロでお腹を温めるのはもちろん、優しく手のひらで「の」の字マッサージをすることで、脳が「腸が動いている」と錯覚します。
味覚:食べる順番を「温→発酵→繊維」にする
メニューは同じでも、食べる順番で腸の負担は変わります。
この順番にするだけで腸がスムーズに動きやすくなり、便意を感じやすい状態が整います。

五感を通じて「出すリズム」を脳にインプット
この“五感刺激メソッド”のポイントは、脳に「便意の時間ですよ」と気付かせる演出を意識的に行うことです。
ご紹介した習慣は、どれも便意の感覚を呼び戻す刺激やサポートになります。 「ちょっと面白そう」「これなら続けられそう」と思ったものから始めてみてください。
便意がない便秘の改善には“腸内環境”がカギ
便意を感じない便秘は、単なる生活習慣の問題ではなく、腸と神経のつながりが乱れているサインでもあります。
今回ご紹介したような五感刺激や生活習慣の見直しは、腸の感覚を目覚めさせ、自律神経や腸内フローラのバランスを取り戻す第一歩です。
とはいえ、根本的な改善を目指すには、腸内環境そのものを整えることが欠かせません。
腸内ケアには“サプリメント”の力も有効
ビフィズス菌・オリゴ糖・乳酸菌などを効率よく摂れるサプリメントは、
食事だけでは届きにくい善玉菌をダイレクトに補給し、
鈍っていた腸の働きや便意の感覚をやさしくサポートしてくれます。
「出したいのに出せない」「トイレに行っても何も感じない」――そんなつらさを繰り返す前に、
今日から五感を使った習慣+腸内ケアを意識してみませんか?
▼ つらい“出ない感覚”に悩んだら。穏やかに便意をサポート>>詳しくはこちら
よくある質問【Q&A】
便通を自然にサポートする「便通力」の詳細はこちら
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。