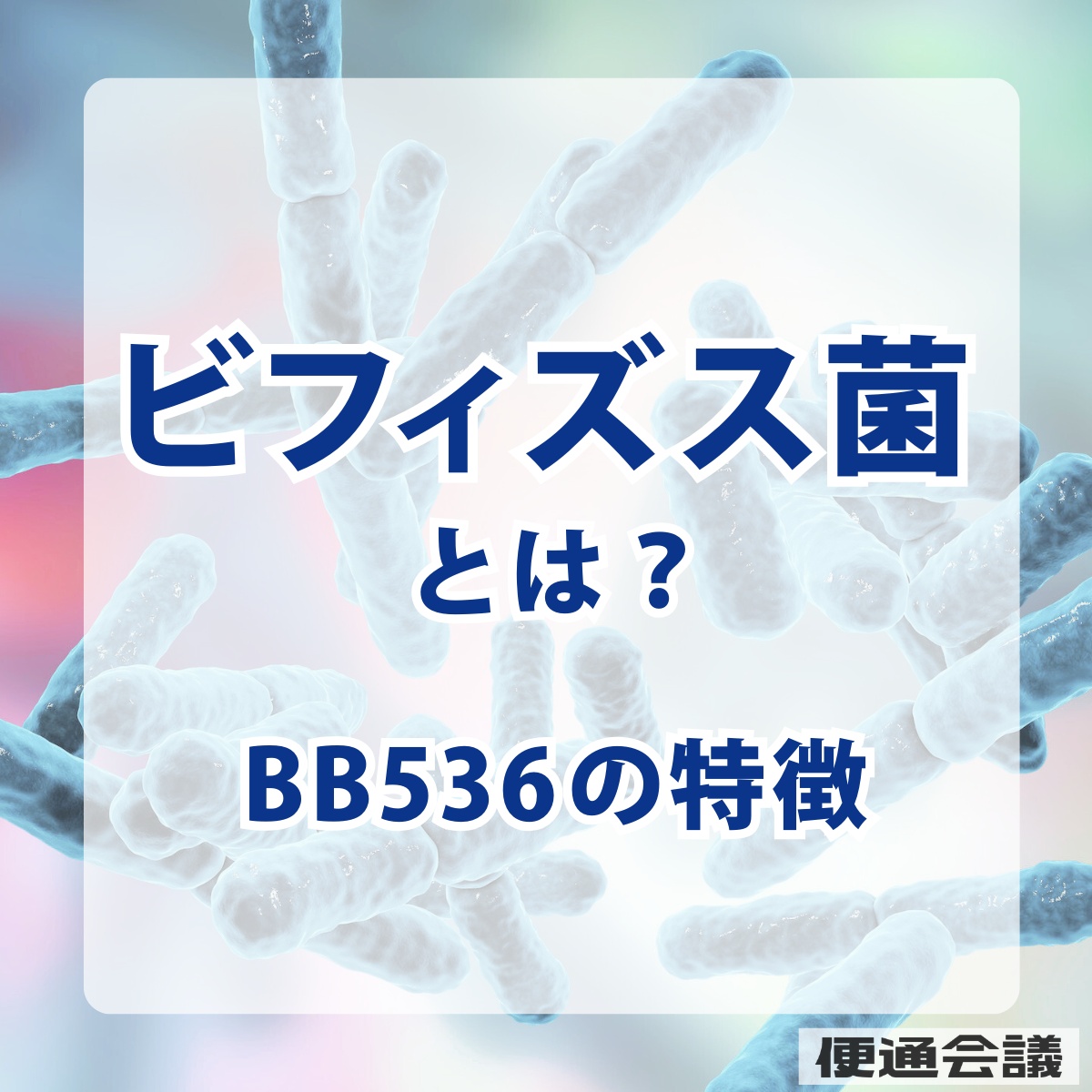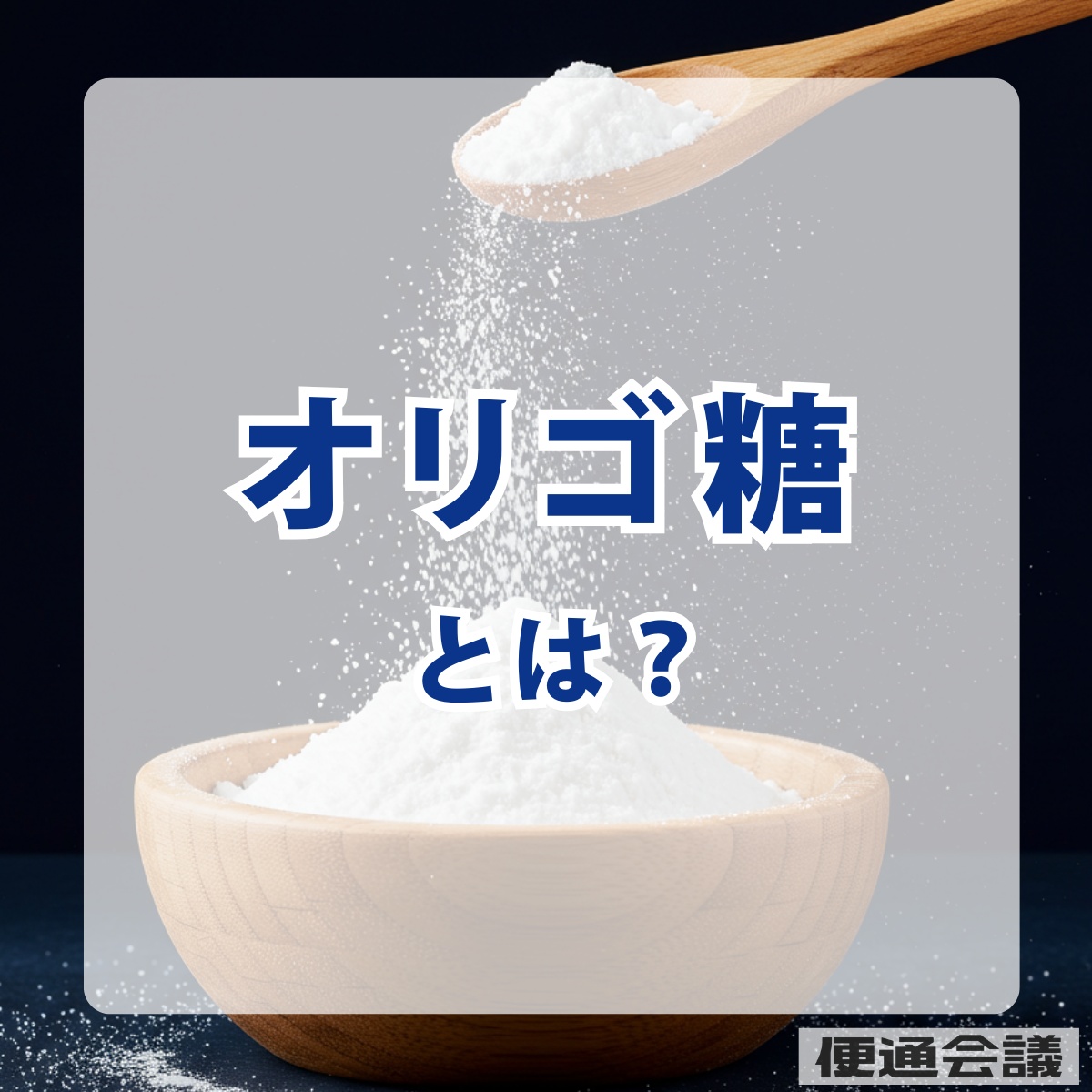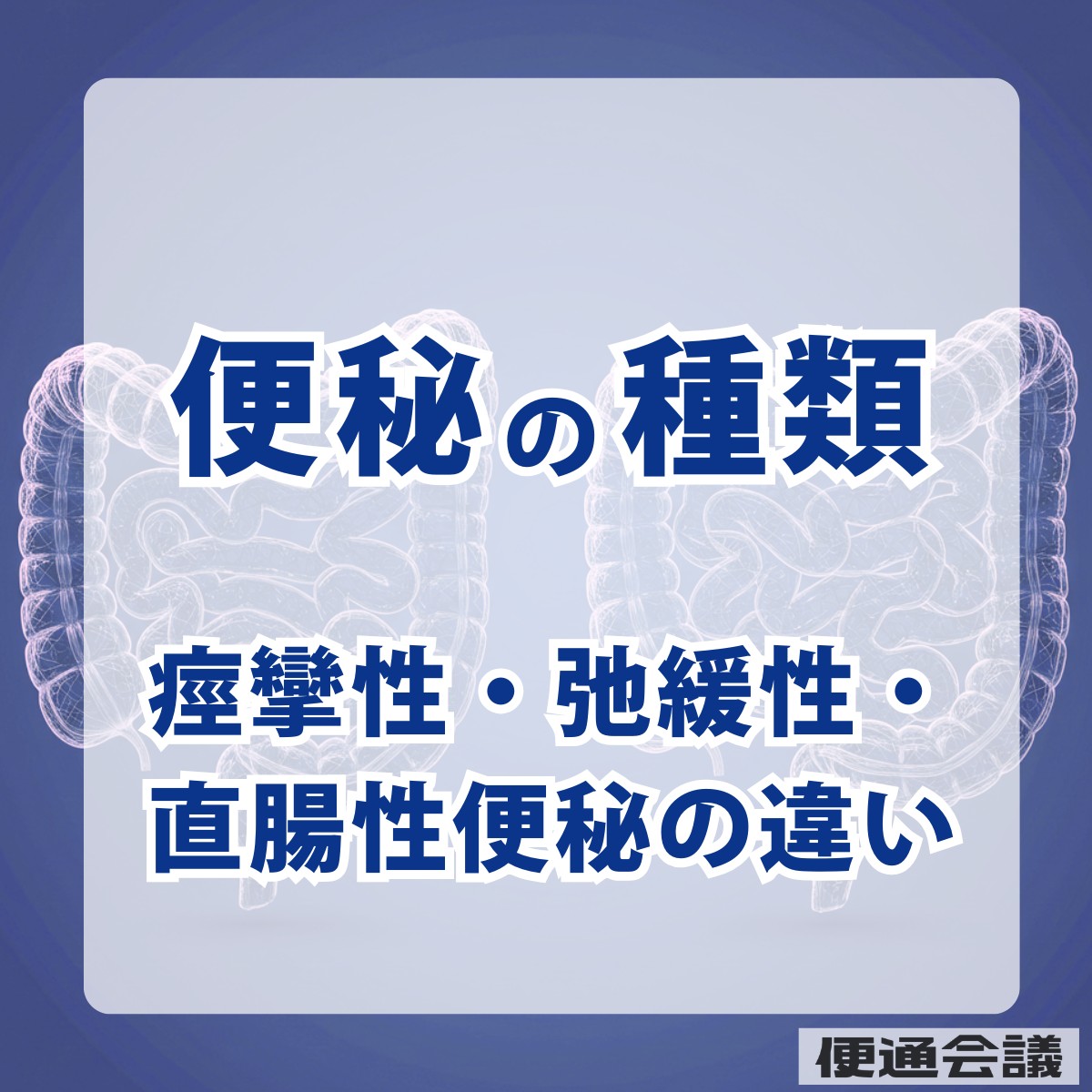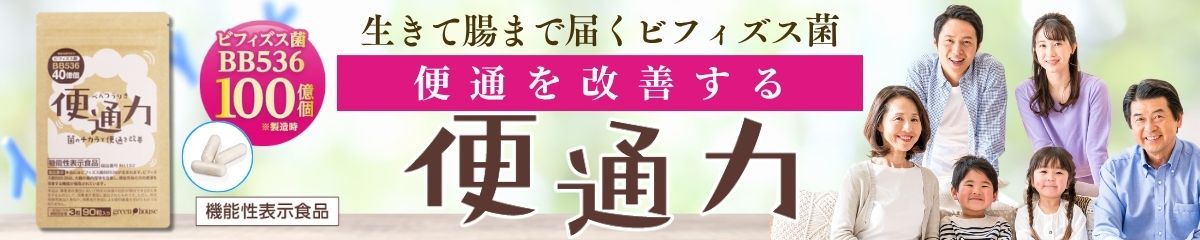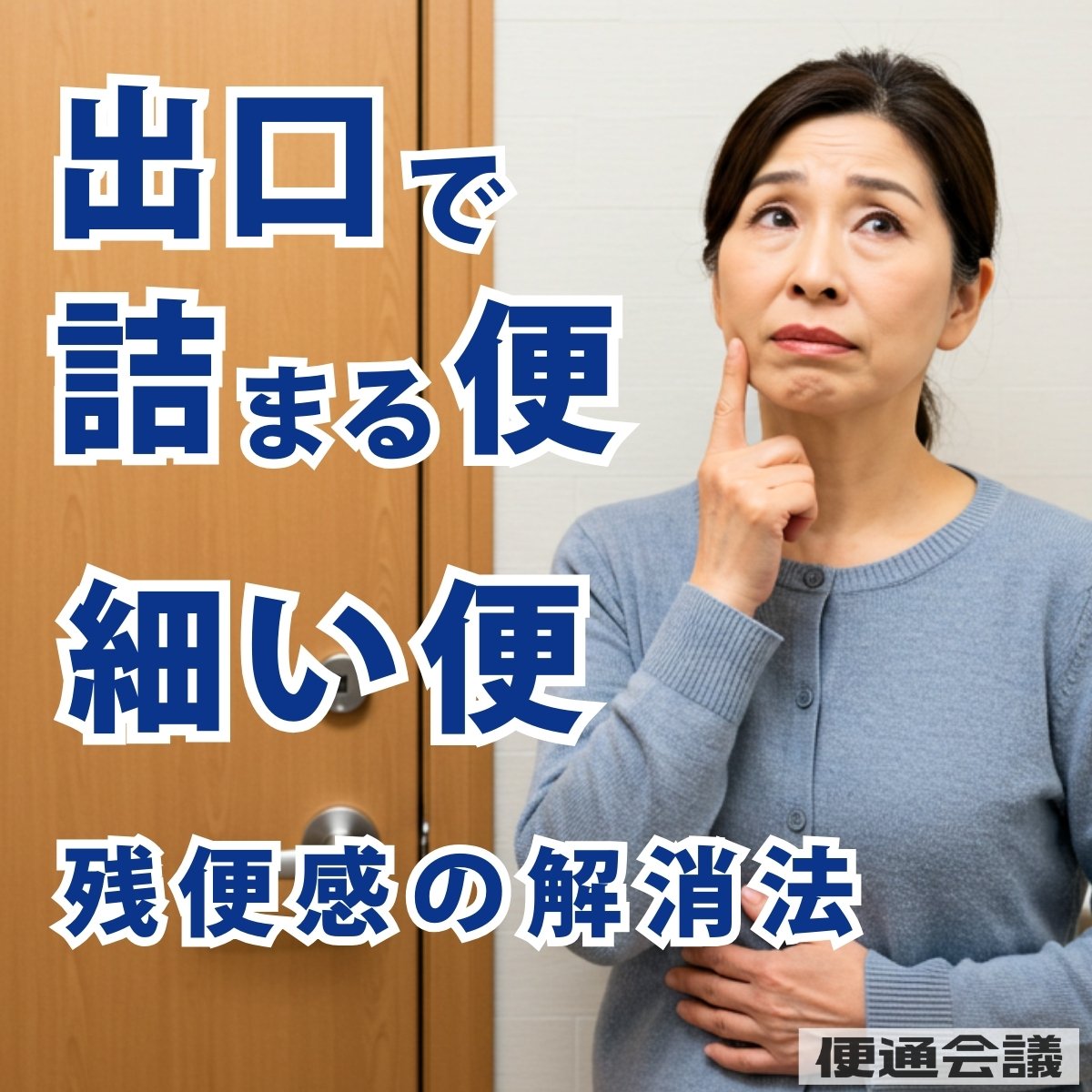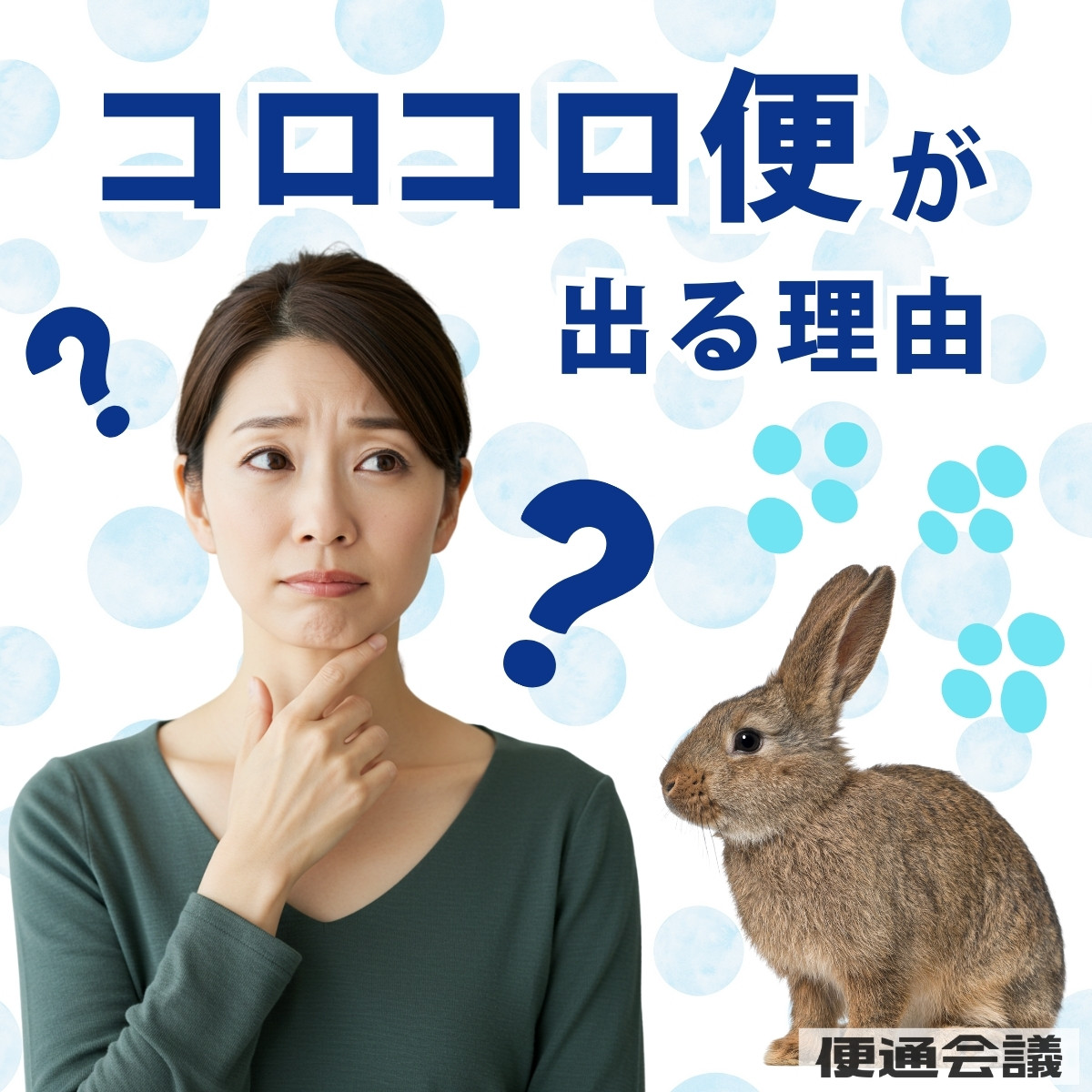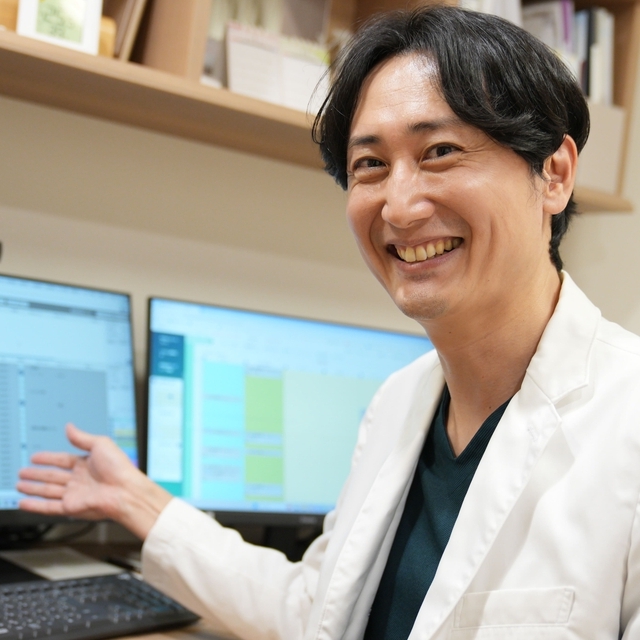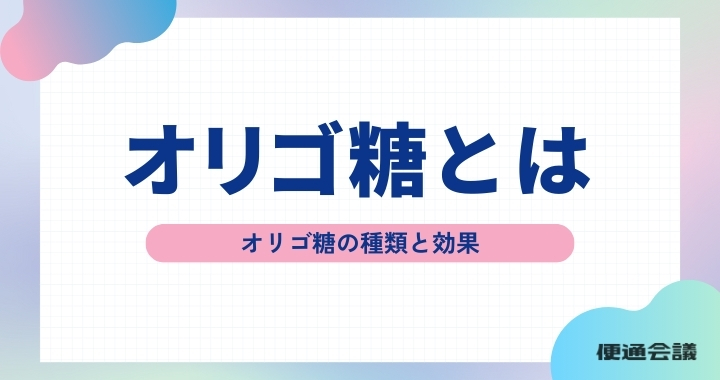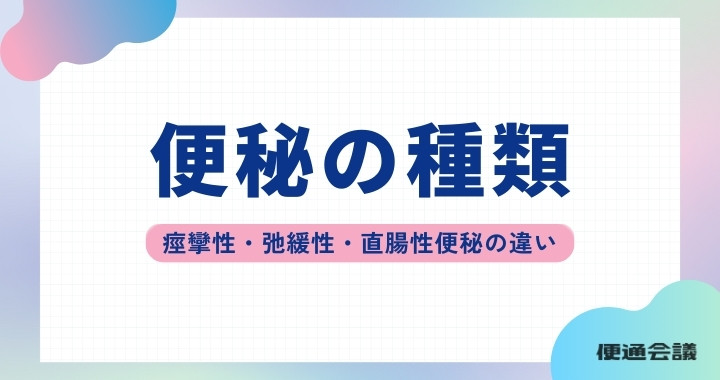最終更新日:2025.9.5
歯磨きの回数が少ないと子どもは便秘になりやすい? | 最新調査が示す意外な関連性

小さな子どもの便秘は、保護者にとってよくある悩みの一つです。「毎日きちんと歯を磨かせているのに、うちの子は便秘がち…」と感じる家庭も少なくないでしょう。
しかし、最新の全国規模の調査では、歯磨き習慣と子どもの便秘リスクには驚くべき関連性があることが明らかになりました。
口の中の清潔さと腸の健康、一見まったく関係がなさそうに思える二つの習慣の間に、どのようなつながりがあるのでしょうか。
本記事では、子どもの歯磨き回数と便秘の関係性について、最新のデータを基に考察していきます。
子どもの腸内環境を良くするために、保護者として知っておきたい情報です。
えっ、本当に?歯磨きで子どもの便秘リスクが変わるの?
便秘は、子どもの生活の質に直結する健康課題です。長期化すると腹痛や食欲不振だけでなく、日常の活動や精神的な発達にも影響を与えることがあります。
これまで便秘のリスク因子として知られてきたのは、食生活の偏りや運動不足、ストレスなどです。
しかし、口腔衛生の習慣が腸の健康にどの程度関与するかについては、これまで明確なデータはほとんどありませんでした。
そこで東北大学の研究チームは、全国規模で母子の健康データを追跡する「エコチル調査」を用いて、歯磨き習慣と小児の機能性便秘の関連性を検証しました。
研究の目的は、単に「歯磨きをしないと便秘になる」という単純な因果を示すことではなく、生活習慣の一つとしての歯磨きが、腸の健康にどのように影響する可能性があるのかを明らかにすることにありました。
子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)とは…
環境省が2011年から開始した、国内最大規模の出生コホート調査です。全国約10万組の親子を対象に、胎児期から少なくとも13歳まで(将来的には18歳まで)の健康や生活環境を追跡調査しています。日本では前例のない大規模かつ長期的な研究です。
1日の歯磨き回数が少ない子どもほど便秘傾向に!
調査結果は、驚くほど明確なものとなりました。
▶年齢別の便秘人数・割合
- 3歳時点の便秘:10,123名(全体の12.1%)
- 4歳時点の便秘:8,820名(全体の10.5%)
- 3歳と4歳両方で便秘(慢性便秘):3,659名(全体の4.4%)

▶1日2回(適切な歯磨き回数)の歯磨きを報告した人数
- 2歳:40,108人(47.9%
- 4歳:63,418人(75.8%

▶歯磨き回数と慢性的な機能性便秘リスクの関係
- 2歳時の歯磨き1日1回 → 1.22倍
- 2歳時の歯磨き1日1回未満 → 1.62倍
- 4歳時の歯磨き1日1回 → 1.22倍
- 4歳時の歯磨き1日1回未満 → 1.60倍

つまり、歯磨きの回数が少ないほど、便秘になりやすく、しかもその傾向は長期的にも持続する可能性があることが分かります。
「歯磨きは口の健康だけでなく、腸の健康にもつながるかもしれない」という新たな視点が示されたのです。
歯磨きの回数が少ない幼児が便秘になる理由とは?
なぜ口腔衛生と腸の健康が結びつくのか、明確な因果はまだ解明されていません。しかし、いくつかの仮説があります。
口腔内の細菌バランスが腸内環境に影響する可能性
歯磨きを怠ると、口腔内の菌バランスが乱れ、虫歯や歯周病の原因となるだけでなく、腸内細菌にも影響を及ぼすことが考えられます。
近年の研究では、口腔内の細菌が飲食物とともに腸に到達し、腸内細菌叢(腸内フローラ)の構成を変化させる可能性が示されています(※1)。
腸内フローラは便通に直接関わるため、口腔内の菌バランスの乱れが便秘のリスクに影響することは十分に考えられます。
さらに、口腔内の悪玉菌の増加は炎症性物質の放出を促すことが知られており、腸の蠕動運動や消化機能にも微妙に影響する可能性があります。
つまり、歯磨き不足による口腔内環境の変化は、腸の健康に波及する「間接的なルート」として機能する可能性があるのです。

生活リズムの一部としての歯磨き習慣
毎日決まった時間に歯を磨くことは、単に口腔ケアの習慣だけでなく、生活リズムの安定化にもつながります。
幼児期は生活リズムの乱れが便秘につながることが知られており、規則正しい睡眠・食事・排便のリズムを持つ子どもは腸の蠕動運動が安定しやすいとされています。
また、子どもを保育所に通わせている母親の生活リズムなどと腸内細菌叢との関連について検討した研究では、規則正しい生活リズムを持つ人ほど、腸内に存在するビフィズス菌属の占有率が高いことが明らかになりました(※2)。
歯磨きは、その生活リズムを支える「日常の目印」として機能するとも考えられるでしょう。

その他の関連要素
口腔からの栄養摂取との関係
歯磨き習慣が整っている子どもは、咀嚼や食習慣も規則正しく、食物繊維や水分の摂取が安定している傾向があります。これも便通改善に寄与する可能性があります。
保護者の健康意識の影響
歯磨きをきちんと行わせる家庭では、生活習慣や食事管理に意識が高いことが多く、間接的に便秘リスクを下げる要因となる場合があります。
つまり、歯磨きは単に口の健康を守るだけでなく、生活全体のリズムを整える「小さな習慣」として腸の健康にも関与している可能性があるのです。
1日2回以上の歯磨き習慣で幼児の便秘を予防!
今回の研究から分かるのは、幼児期の毎日の歯磨き習慣が、便秘予防にもつながる可能性があるという点です。
1日2回以上の歯磨きを習慣化することが、口腔衛生だけでなく便秘予防にもつながるかもしれません。
また、歯磨きだけでなく、食物繊維や水分の摂取、適度な運動といった他の生活習慣も整えることで、さらに便秘リスクを減らせる可能性があります。
小さな日常の習慣の積み重ねが、子どもの健康全体に大きな影響を与えることを意識してみましょう。
今日からできる「小さな工夫」を積み重ねることで、子どもの便秘予防に大きな差が生まれるかもしれません。
【参考資料・出典】
※1:山崎和久. "歯周病と全身疾患の関連 口腔細菌による腸内細菌叢への影響." 化学と生物 54.9 (2016): 633-639.
※2:宮原葉子, et al. "保育所幼児保護者の栄養摂取状況, 生活習慣等が健康に関わる腸内細菌叢に及ぼす影響." 日本食生活学会誌 32.2 (2021): 77-86.
腸内環境を効率的に整えたいあなたへ
自然のチカラで体に優しい便通習慣
ビフィズス菌BB536とオリゴ糖で内側からサポート。
習慣にしやすいシンプルな腸活、始めてみませんか?

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。