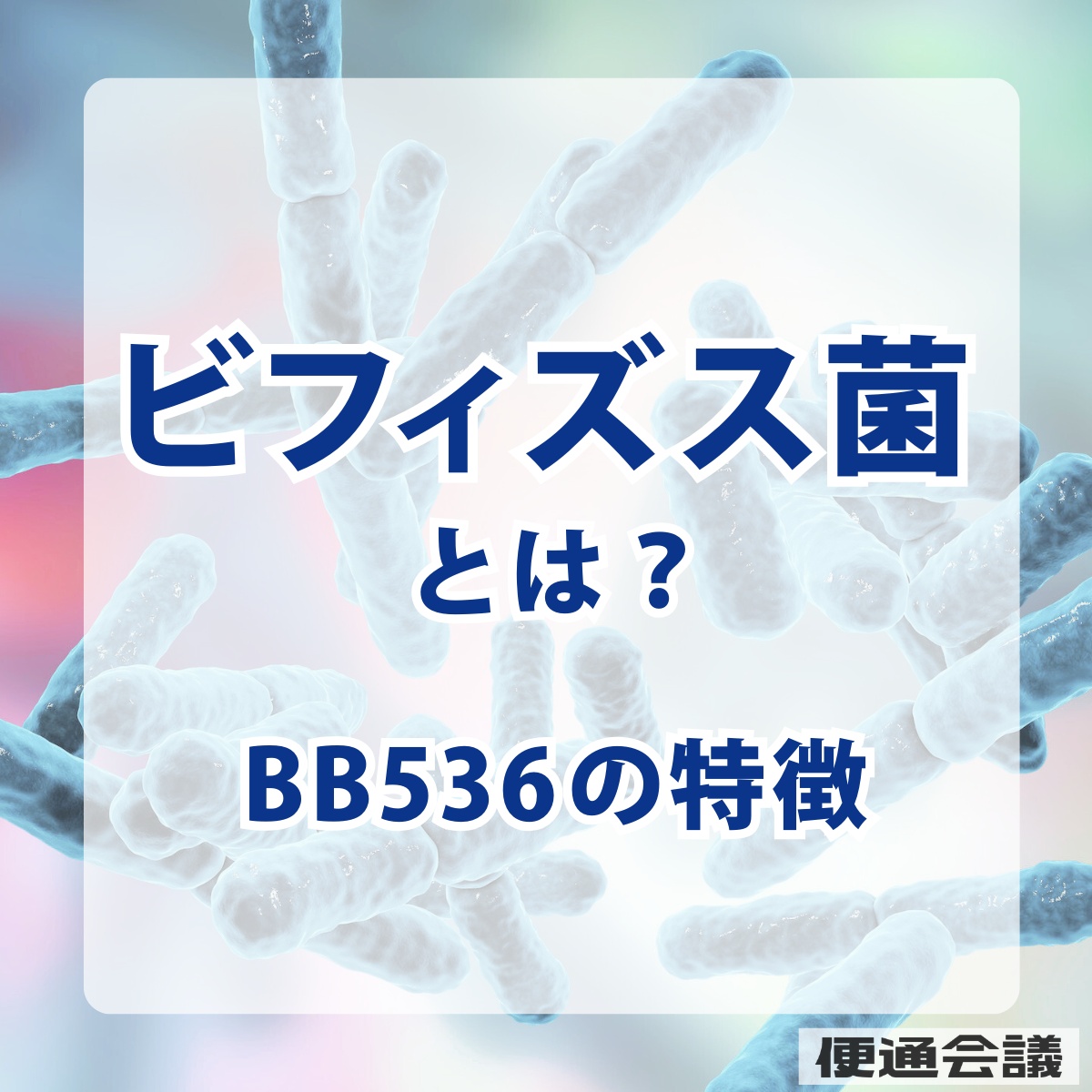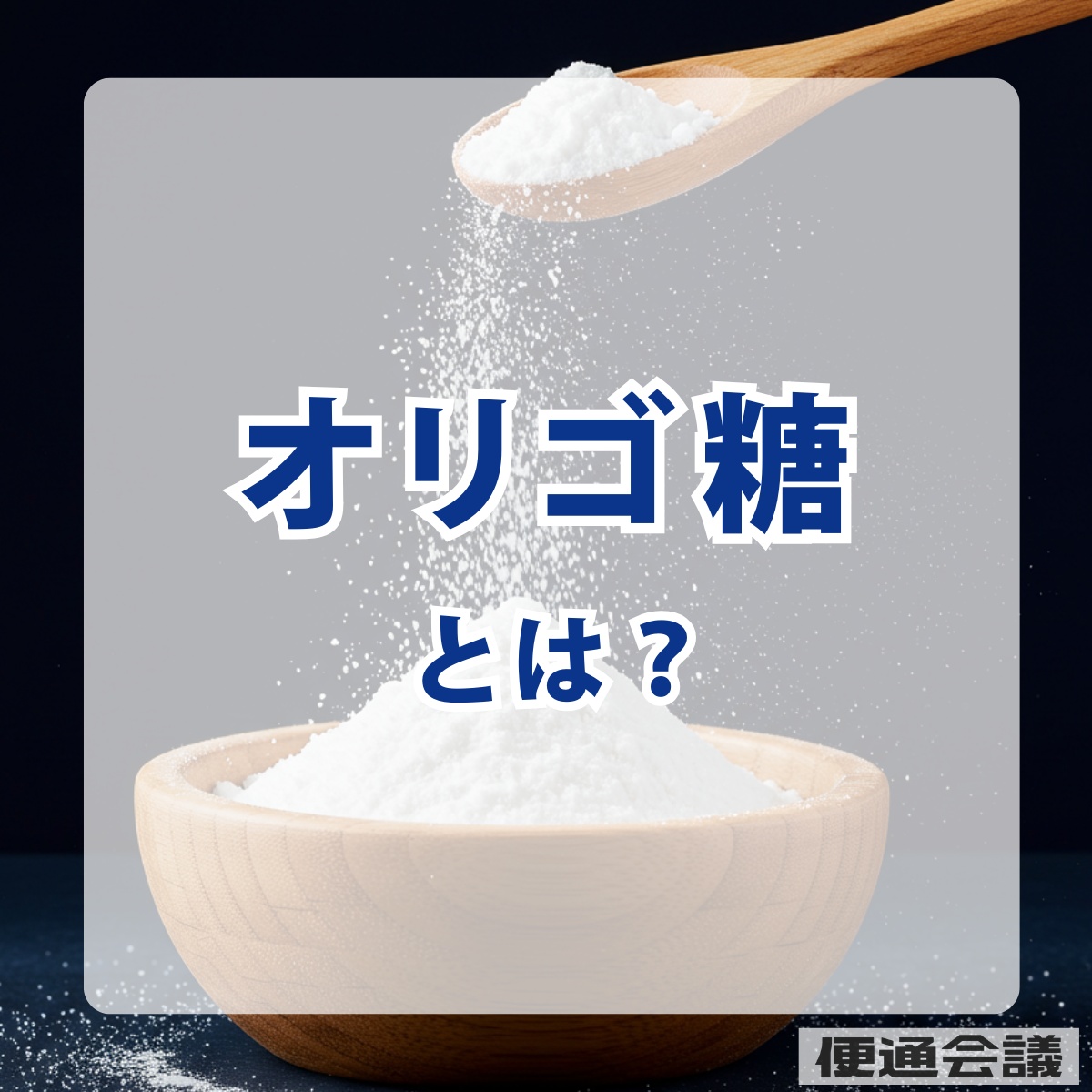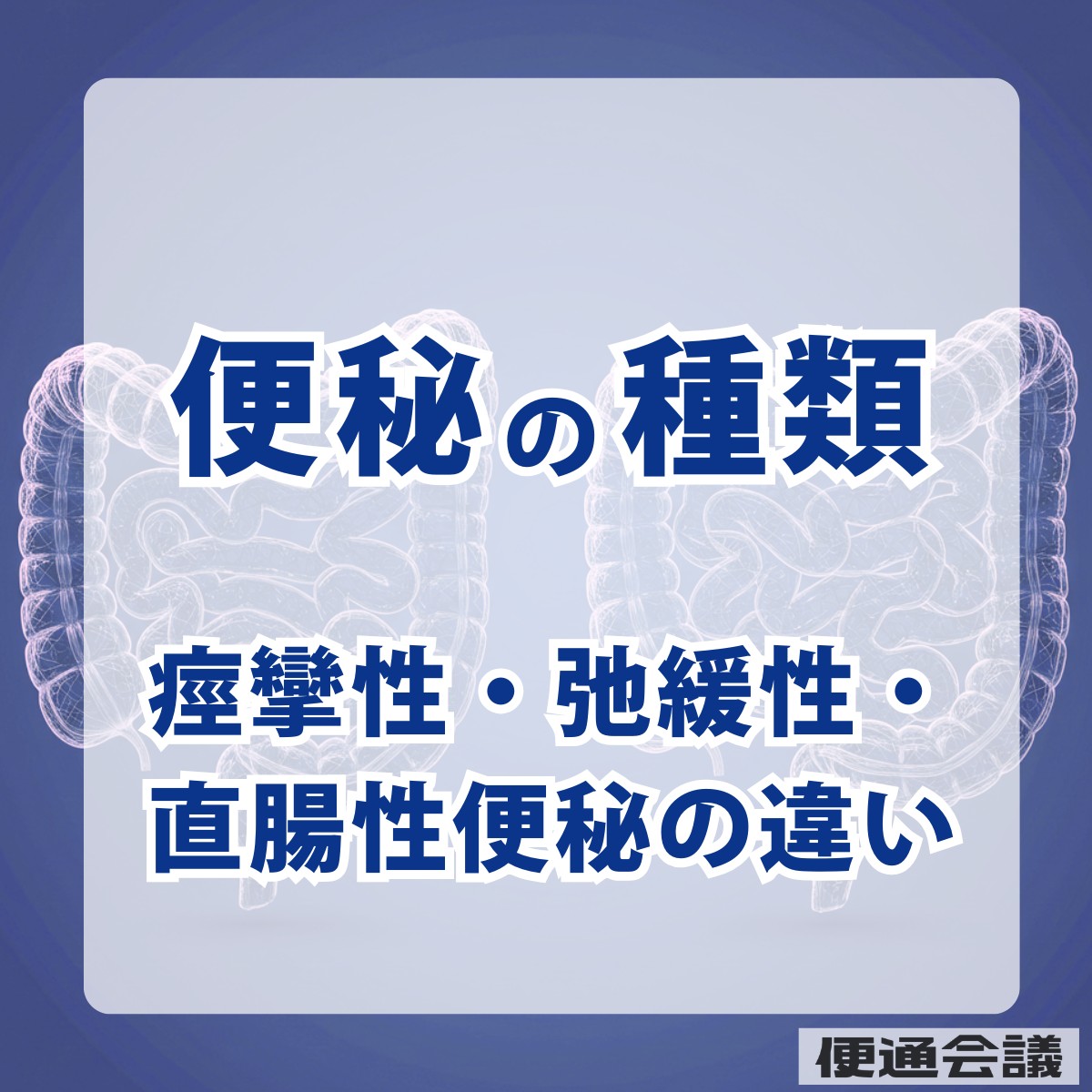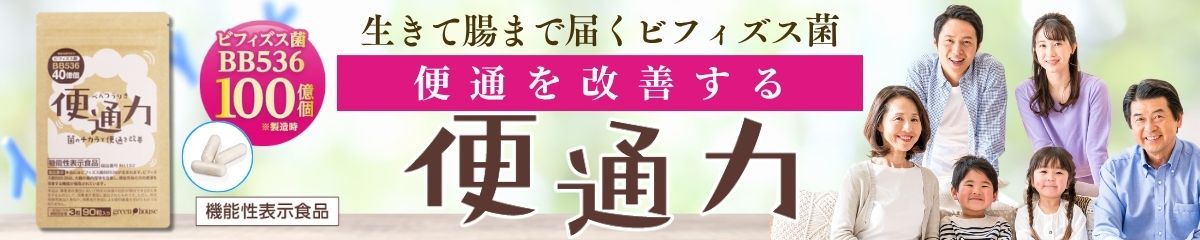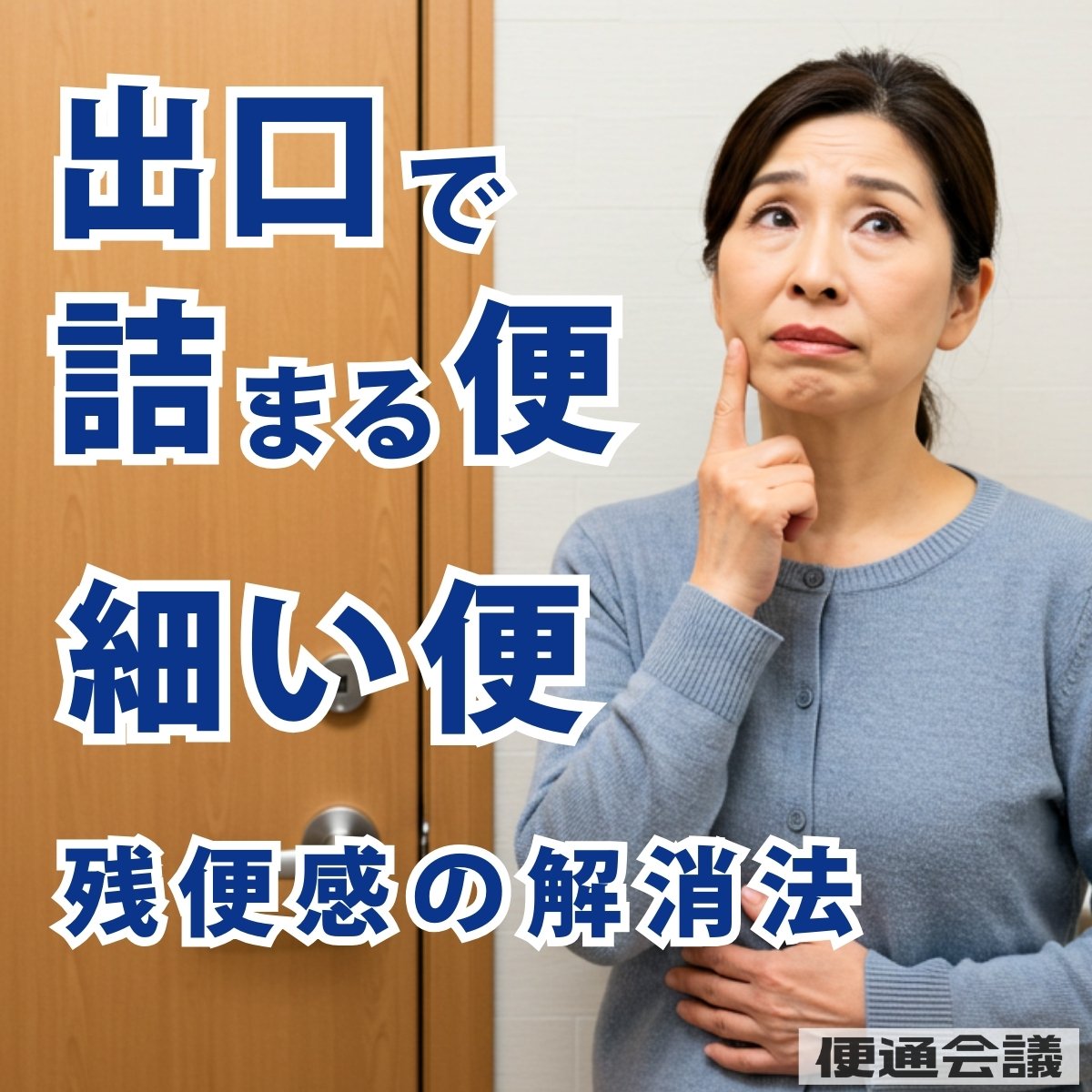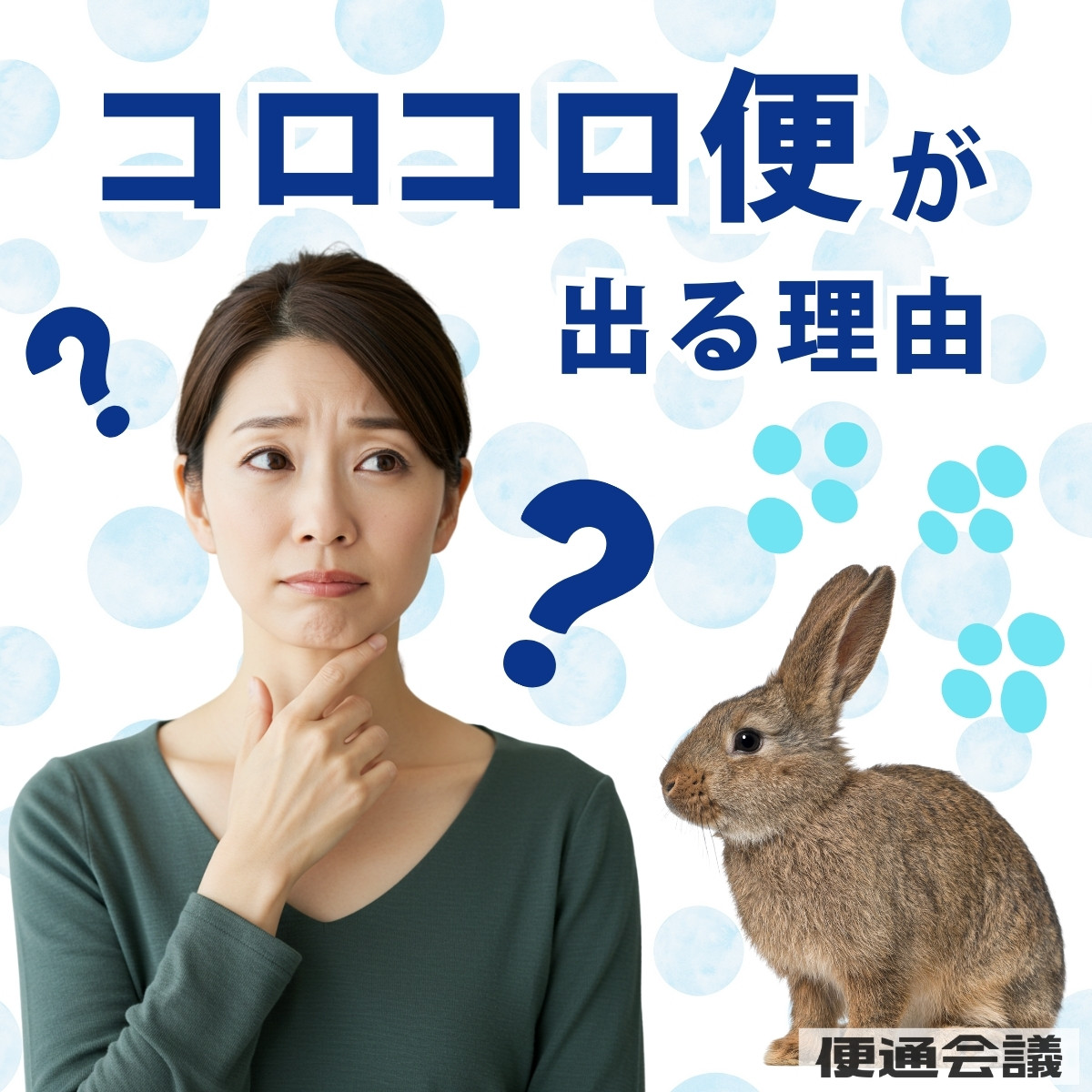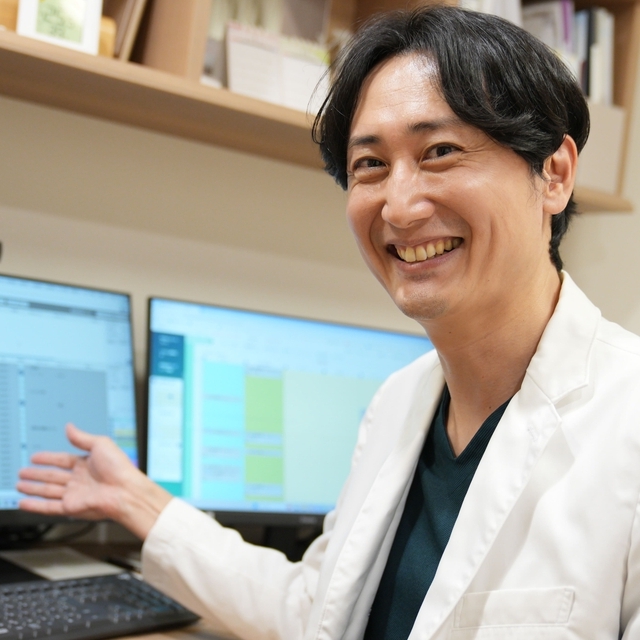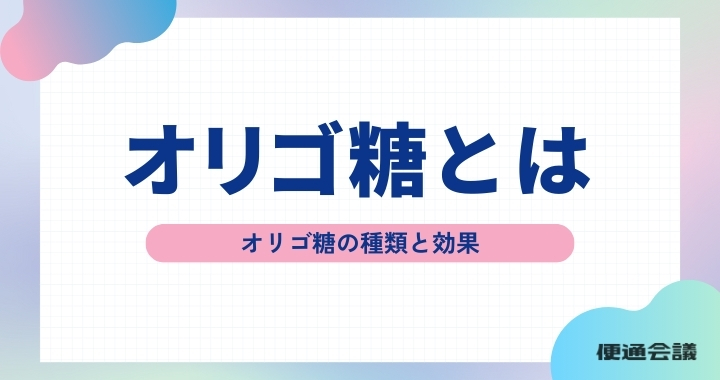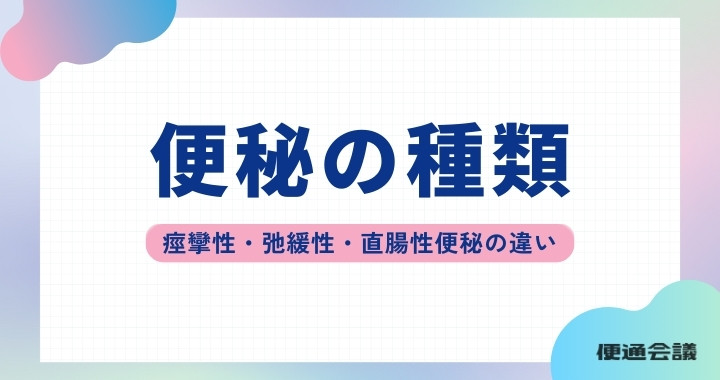最終更新日:2025.11.04
幼児の気質は腸内細菌叢と関係している?最新研究が示す「腸と心のつながり」

幼児期のちょっとした気分の揺れや行動の特徴が、腸内の微生物と関係している可能性が最新の研究によって明らかになってきました。
研究では、3~4歳の子どもたちの腸内細菌の構成や多様性が、その子の気質やストレス反応と関連していることが示されています。
幼児期の腸内細菌叢(腸内フローラ)が気質に及ぼす影響について、研究で示された結果について、詳しく見ていきましょう。
幼児期の“気質”とは?将来に影響はある?
そもそも、“気質”とは何でしょうか?
気質とは、心理学の分野で「人が生まれつきもっている情動反応や行動傾向」を指し、性格の土台となる要素です。
一方で性格は、こうした気質に環境や経験が加わって形成されていくものと考えられています。
幼児期の気質を測定する代表的な質問票「児童行動質問票(Children’s Behavior Questionnaire/CBQ)」では、気質を次の3つの側面に分類しています。
▶幼児の気質の3分類(CBQより)
- 否定的情動性
恐れや悲しみ、怒りなどの不快情動の表出や、脅威刺激に対する特性 - 外交性/高潮性
笑顔など快情動の表出や、新奇な環境へ積極的に探索・接近する特性 - エフォートフル・コントロール
①②の行動を自ら制御する特性(注意や抑制の調整など)
幼児期のネガティブな感情の高さや努力による制御の低さは、将来の不安やうつ症状のリスクと関連することが知られています。
つまり、この時期の気質の評価は、将来の精神的健康を予測する重要な手がかりとなるのです。

幼児期における腸内細菌叢と脳の発達の関係
腸内細菌は、神経伝達物質や免疫系、ホルモンを通じて脳に情報を伝える重要な役割をもっており、これを「腸内細菌叢-腸-脳相関(腸内細菌-脳-腸軸、腸内細菌-脳腸相関)」と呼びます。
つまり、腸内細菌は単なる消化の助けに留まらず、脳にも影響を与えることが、数多くの研究によって示されているのです。
乳児期~幼児期にかけて腸内細菌叢は大きく変化する
人間の腸内細菌叢は生後1年の間に大きな変化を遂げ、乳児期から生後3~5年で成人に近い構成へ近付きます。
この時期は、感情やストレスの調整に関わる前頭前皮質が発達する時期でもあります。
つまり、幼児期の腸内環境は、脳の発達と密接にリンクしている可能性があるのです。

幼児を対象に気質と腸内細菌の関係を調査
今回の研究では、日本国内の複数地域にある保育園に通う3~4歳の幼児284名(男児172名、女児112名)を対象に、気質と腸内細菌の関係を調べました。
▶気質評価:母親による「児童行動質問票(CBQ-SF)」で評価
▶腸内細菌叢評価:便検体から16S rRNAシークエンシングにより多様性や個人間の差、特定の細菌の豊富さを測定
母親の観察をもとにした評価と、科学的に解析された腸内細菌データを組み合わせることで、気質と腸内環境の関係性を多角的に検討しました。
▶「児童行動質問票(CBQ-SF)」とは
- 子どもの気質を評価するために用いられる尺度で、92項目から構成されています。
- 保護者が、過去2週間に観察された日常的な状況における子どもの行動を、7段階で評価します。
▶「16S rRNAシークエンシング」とは
- 微生物の集団(微生物叢、マイクロバイオーム)の構成を調べるための分子生物学的な手法です。
- 特に、培養が難しい、あるいは未だ知られていない細菌を特定し、その相対的な存在量を解析する際によく用いられます。
ネガティブ傾向が強い幼児に多い腸内細菌叢の特徴
解析の結果、否定的情動性(ネガティブ感情)が高い幼児では、酪酸の産生や抗炎症に関わる腸内細菌(Faecalibacterium属の細菌)が少なく、炎症の誘発に関わる腸内細菌(Eggerthellaや Flavonifractor)が多い傾向が見られました。
▶抗炎症的な菌が少ない → ストレス反応が高い
▶ネガティブな感情が強く現れる子どもほど、腸内環境に偏りがある
このように、炎症関連細菌のバランスが気質の差と関連する可能性が示されたのです。
ポジティブ傾向で外向性が高い幼児の腸内細菌叢は?
一方で、腸内に Faecalibacterium など抗炎症的性質を持つ細菌が多く存在する子どもは、ポジティブな感情を表し、他の人と積極的に交流したり、新しい刺激に興味を示したりする傾向がありました。
さらに、腸内細菌の多様性が高い幼児ほど、新しいことへの挑戦や、動機に基づいて行動しやすいといった外向的特性がみられました。
▶抗炎症的な菌が多い → ポジティブな感情を示し、他人との交流や新たな刺激に積極的
▶腸内細菌の多様性が高い → 新たなことへのチャレンジなど外向的特性が高い
統計的には「傾向レベル」ではありますが、腸内細菌の豊富さや多様性が性格形成や感情表現に影響を与える可能性があることを示しています。

幼児期に腸内細菌叢を整える重要性
腸内細菌は、生後3~5年で成人に近い構成に安定します。
この時期は、感情や注意の制御に関わる前頭前皮質の発達が著しい時期でもあります。
つまり、幼児期は腸内細菌の基盤が形成されると同時に、精神機能の発達にも大きく影響する重要な時期です。
今回の研究では、幼児期における腸内細菌と気質の関係が明らかになりました。
抗炎症細菌の量や腸内細菌の多様性は、ストレス反応や外向性など将来の精神的健康に関わる指標として、今後、さらなる注目を集めるでしょう。

まとめ | 幼児期の気質は腸内細菌の構成が左右する可能性
今回の研究は、幼児期の気質について理解するうえで、重要なヒントをもたらしました。
腸内細菌は、ただ消化を手助けするだけでなく、子どもの心の成長にも影響を与える存在であることが、研究を通して示唆されています。
▶研究からわかった主なポイント
- 幼児期の気質:腸内細菌の構成や多様性と関連している
- 否定的情動性が高い子ども:抗炎症に関わる細菌が少なく、炎症を誘発する細菌が多い傾向がある
- 外向性/高潮性:腸内細菌の多様性や抗炎症細菌の豊富さと関連している
- 幼児期:腸内細菌の基盤形成と前頭前皮質の発達が重なる重要な時期である
- 腸内細菌と気質の関係:将来の精神的健康リスクを早期に評価する手がかりとなる可能性がある
否定的な感情は、うつ病などメンタル疾患のリスクを高める要因であり、抗炎症細菌の減少も発症に関係しています。
幼児期のうちから、プロバイオティクスの補給などで腸内細菌叢のバランスを整えることで、将来的なメンタルヘルス問題を予防・改善できる可能性があります。
腸内環境と心理的健康の関係を理解することが、幼児期の発達を支える新たな視点につながるでしょう。
【参考資料・出典】
腸内環境を効率的に整えたいあなたへ
自然のチカラで体に優しい便通習慣
ビフィズス菌BB536とオリゴ糖で内側からサポート。
習慣にしやすいシンプルな腸活、始めてみませんか?

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。