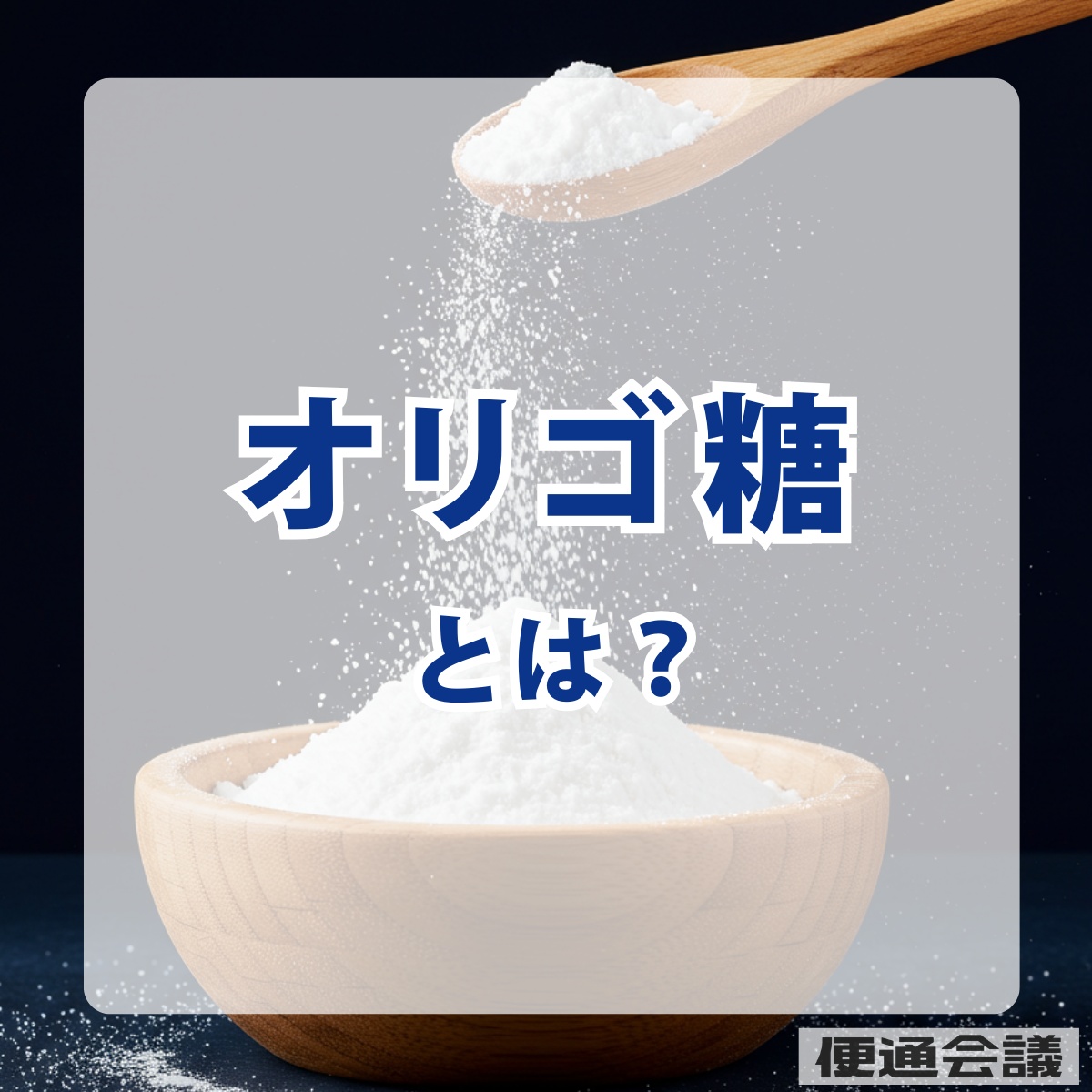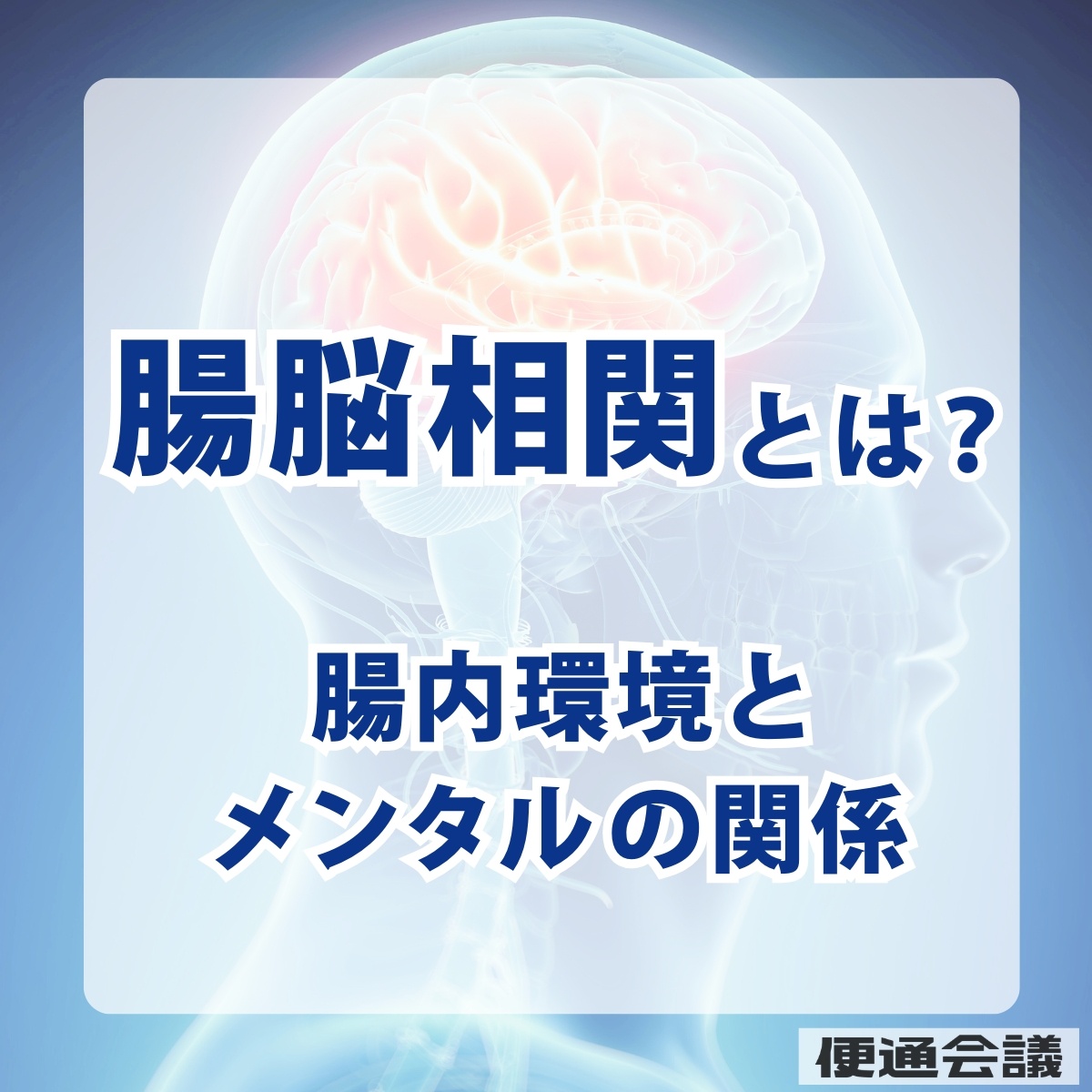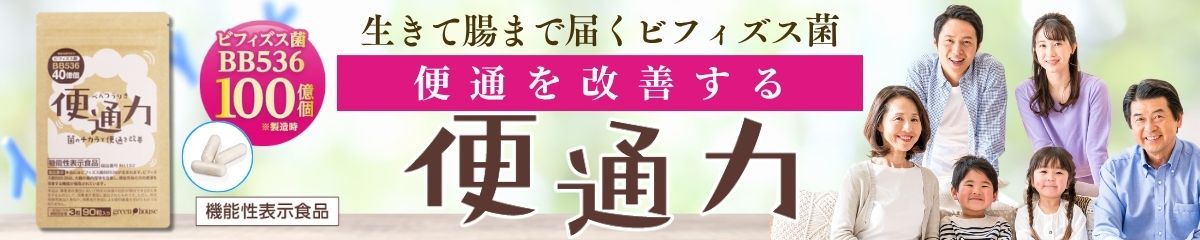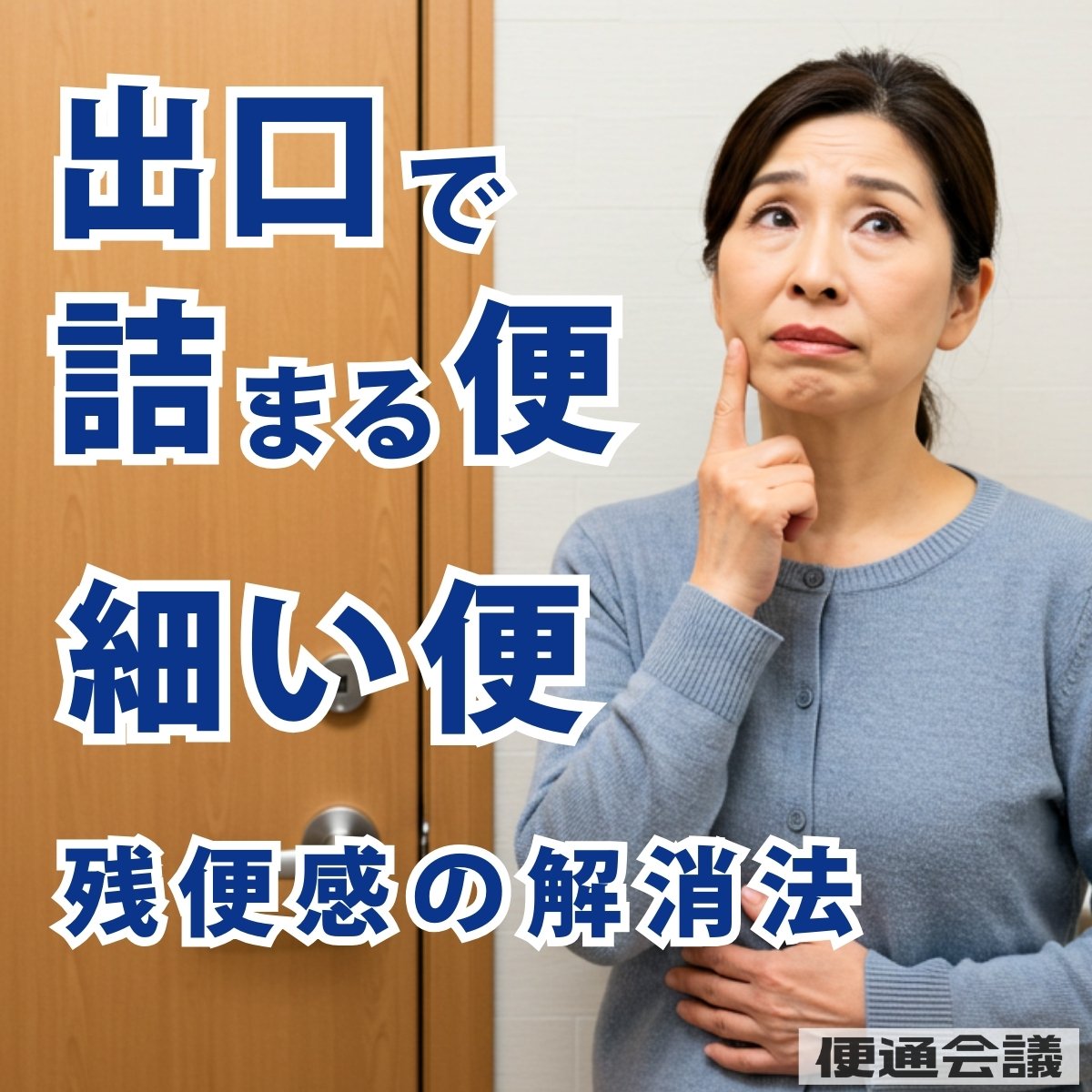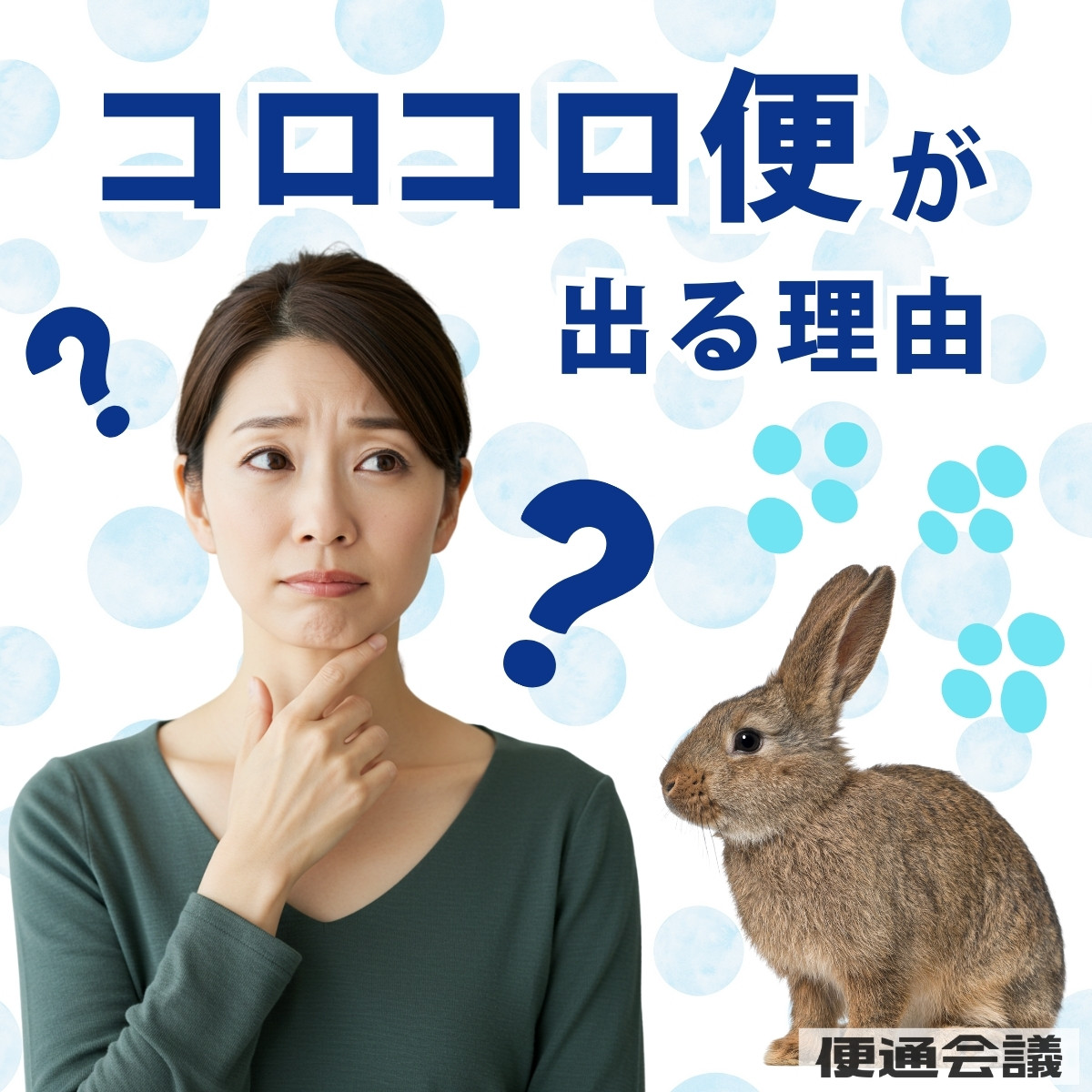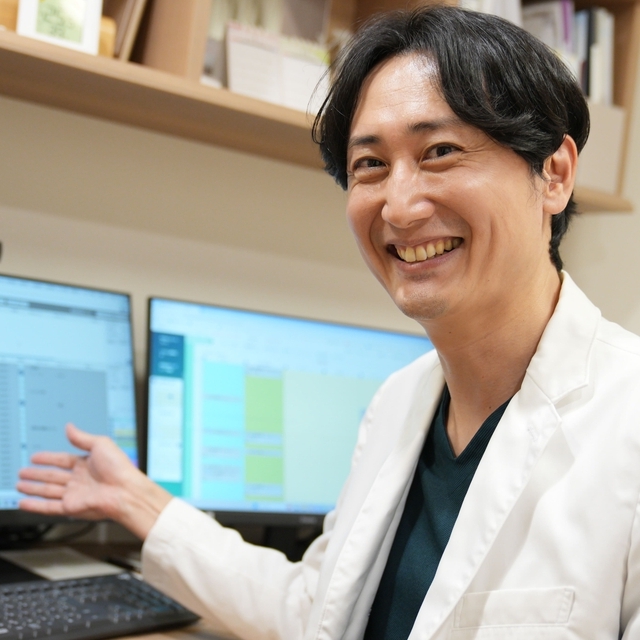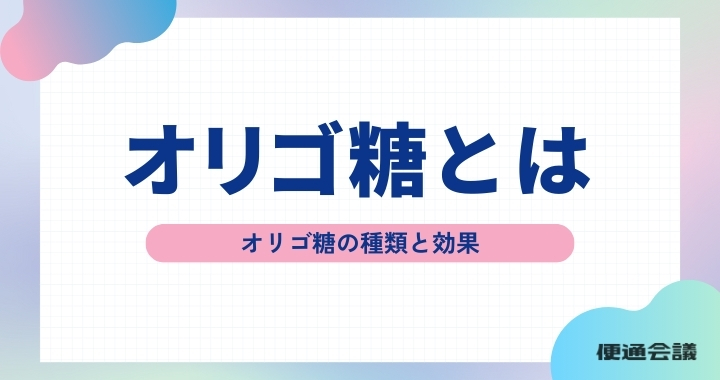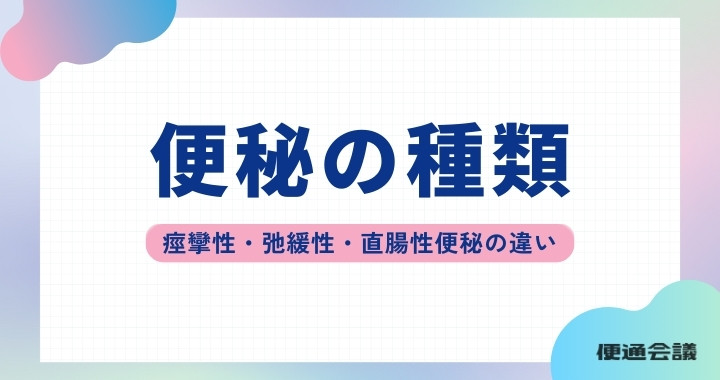最終更新日:2025.9.25
便秘の種類について|自分に合った腸活で快適な毎日を

便秘は、単に「便が出ない状態」ではありません。原因や症状によって様々なタイプに分類され、対策法も異なります。
そのため、便秘の種類を理解することが、自分にとって有効な便秘対策法を知るための近道なのです。
本記事では、それぞれの便秘の特徴や原因について、詳しく解説します。
自分の便秘タイプを知って、本当に効果がある腸活法を実践しましょう。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
目次
- b. 後天性の器質性便秘
- 機能性便秘とは?生活習慣やストレスが影響
- a. 一過性単純性便秘
- b. 薬物性便秘
- c. 症候性便秘
- d. 習慣性便秘
- まとめ|自分の便秘タイプに合う腸活で便秘を改善!
器質性便秘とは?腸の構造や機能に問題があるタイプ
便秘は大きく「器質性便秘」と「機能性便秘」の2種類に大別されます。それぞれの特徴について、まずは「器質性便秘」からご紹介します。
器質性便秘は、腸そのものの構造や器質に異常があるために起こる便秘です。生活習慣の改善だけでは解消しにくく、医療的な対応が必要な場合があります。

a. 先天性の器質性便秘
生まれつき腸や肛門の形状に異常がある場合、便の通過が阻害され、便秘を引き起こします。
代表的な疾患
- ヒルシュスプルング病
- 肛門閉鎖症
ヒルシュスプルング病は、消化管の蠕動運動に必要な神経細胞が欠如しているため、腸が動かず便が腸内に滞留して腸閉塞を引き起こす疾患です。
症状は新生児期から現れることが多く、早期の診断と手術が必要となります。
肛門閉鎖症は、生まれつき肛門が完全に開いていなかったり、位置が異常であったりする先天性の消化管異常です。
このため、便が排出されず腸内に滞留し、重度の便秘や腸閉塞を引き起こすことがあります。早期の診断と外科的治療が必要な疾患です。
b. 後天性の器質性便秘
成長や加齢、病気、手術後の影響で腸の構造や機能が変化して起こります。
代表的な原因
- 腫瘍による便通障害
- 炎症や手術後の癒着
腸内の腫瘍が便の通過を妨げ、慢性的な便秘や血便の原因になることがあります。
腸の癒着が蠕動運動を妨げ、便がスムーズに排出されにくくなります。
長引く便秘に血便、体重減少、腹痛、発熱を伴う場合は器質性便秘の可能性があります。早めの医療機関受診が必要です。
機能性便秘とは?生活習慣やストレスが影響
機能性便秘は、腸の構造に問題はないものの、腸の働きや排便習慣の乱れによって起こる便秘です。生活習慣やストレス、薬の影響が大きく関わり発生している便秘のことを指します。
では、機能性便秘の分類を確認してみましょう。

a. 一過性単純性便秘
旅行や引っ越し、生活リズムの変化で一時的に起こる便秘です。
一過性単純性便秘
- 特徴:数日で自然に解消されることが多い
- 対策:水分補給と食物繊維の摂取、排便習慣を意識するだけでも改善可能です。
b. 薬物性便秘
服用中の薬が原因で便秘になることがあります。
薬物性便秘
- 代表的な薬:鎮痛薬(オピオイド系)、抗うつ薬、鉄剤、カルシウム剤など
- 対策:薬の種類や摂取のタイミングを医師と相談することが重要です。
c. 症候性便秘
糖尿病や甲状腺疾患などの病気の症状として現れる便秘です。
甲状腺機能低下症では腸の蠕動が低下し、慢性的な便秘が起こります。また、糖尿病では自律神経障害が腸の動きを鈍くする場合も。
原疾患の治療が不可欠で、便秘対策だけでは改善しません。
d. 習慣性便秘
習慣性便秘は、排便習慣や腸の働きの偏りによって慢性的に便秘が続くタイプです。
習慣性便秘の中でも、特徴や原因によって大きく3種類に分類されます。

便秘を習慣化しない!腸まで届くビフィズス菌で自然なお通じを手に入れるには…>>詳しく解説
d-1. 痙攣性便秘(過敏性腸症候群型便秘)
痙攣性便秘は、腸の蠕動運動が過剰に活発になり、便がスムーズに移動せずにコロコロと硬くなる便秘です。
20~40代の女性に多く、日本人に多い過敏性腸症候群(IBS-C)の症状として現れることがあります。
症状の特徴
- 硬くコロコロした便
- 便意はあるのに排便できない
- 便秘と下痢の繰り返し
- 腹痛・お腹の張り
- ストレスで悪化(腸脳相関)
腸が過剰に収縮することで便が細かく分断され、まるでウサギの糞のようになります。
腸の痙攣により便の通過が妨げられ、「便意を感じるのに出ない」「残便感がある」といった不快感が続きます。
過敏な腸は便をため込んだ後、急に排出することがあり、便秘と下痢を繰り返す場合があります。
食後や緊張時に腹痛が起こりやすく、排便で軽減するのが特徴です。
腸と脳(精神)の状態には深い関連性があると考えられ、「腸脳相関(脳腸相関)」と呼ばれています。
強い精神的プレッシャーやストレスがかかると便秘症状が悪化しやすくなるのは、このためです。
主な原因
- 過敏性腸症候群(IBS-C)による腸の痙攣
- 便秘型(IBS-C)
- 下痢型(IBS-D)
- 混合型(IBS-M)
- 分類不能型(IBS-U)
- 食物繊維の摂り方の偏り
- カフェイン・コーヒーの刺激
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome: IBS)は、腸に炎症や器質的異常がないにもかかわらず、腸の運動異常や知覚過敏が生じる機能性疾患です。
日本人の約10~20%が罹患していると推測され、男性よりも女性患者の方が若干多いことが分かっています。
過敏性腸症候群は、症状によって4つのタイプに分類されています。
痙攣性便秘は、便秘型過敏性腸症候群(IBS-C)の一種として考えられています。
過敏性腸症候群の主な原因が、ストレスなどの精神的要因です。
ストレスの蓄積で自律神経がバランスを崩すと、腸のリズムを調整する役割を担う副交感神経の働きが乱れ、腸の過剰な収縮を引き起こします。
その結果、便が分断されたり、スムーズな移動が妨げられたりして、便秘や腹痛を繰り返すのです。
過敏性腸症候群が原因の場合は、便秘薬(下剤)を使うと腸の痙攣が悪化して逆効果になるケースがあります。
水溶性食物繊維(海藻・オートミールなど)は腸を優しく整える一方、不溶性食物繊維(穀物・野菜)は刺激が強く便秘を悪化させる可能性があります。
コーヒーは腸を刺激し、排便を促して便秘を治す効果があるとされています。
しかし、痙攣性便秘の人にとっては刺激が強すぎる場合も。特に空腹時は腹痛の原因になるため、控えた方が良いでしょう。
過敏性腸症候群の人は、カフェインが腸を過剰に動かして症状を悪化させるケースがあるため、摂取量に注意が必要です。
腸活のポイント
- 腸を温める
- 少量を回数に分けて食べる
- 呼吸法やマインドフルネス
- 発酵食品の積極的摂取
温かい飲み物や腹部を温めることで腸の緊張が和らぎ、過剰な蠕動を抑制します。
一度に多く食べると腸に負担がかかり痙攣を誘発します。1日4〜5回に分ける食事で腸の刺激を穏やかに。
腹式呼吸や簡単な瞑想で自律神経を整え、腸の痙攣を抑えます。
ヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品で腸内フローラを安定させ、便通リズムを整えます。
痙攣性便秘は「腸のストレス症状」とも言えます。ポイントは「腸への刺激を穏やかにすること」と「自律神経を整えること」です。
痙攣性便秘は無理な便秘薬使用で悪化することがあるため、自然に腸を落ち着かせる方法が最適です。

d-2. 弛緩性便秘
弛緩性便秘は、腸の蠕動運動が弱まり、腸内に便が滞留する便秘です。特に高齢者や運動不足の人に多く見られます。
症状の特徴
- 便が硬く排出が困難
- お腹の張りや残便感
- 排便間隔が長くなる
腸の動きが鈍いため、便が腸内に長時間滞留します。その間に便内の水分が腸管で吸収され、硬化。いきんでも排出困難な便になります。
便が長く腸内に滞留すると、膨満感や不快感が続きます。
数日排便がない、または少量ずつしか排出されません。
主な原因
- 運動不足・筋力低下
- 水分・食事量の不足
- 腸内細菌バランスの乱れ
腸の蠕動運動を助ける腹筋や骨盤底筋の衰えが便の停滞を招きます。
高齢者は喉の渇きを感じにくく、便が硬化しやすくなります。
善玉菌の減少や悪玉菌の増加が蠕動運動を弱めます。
腸活のポイント
- 腸マッサージで蠕動を促す
- 軽い有酸素運動
- 朝食に発酵性食物繊維を摂る
- 規則正しい生活リズムを確立する
お腹を時計回りに軽くマッサージすることで蠕動運動を促し、便の移動を助けます。
ウォーキング、ジョギング、スイミングなどで腸の動きを活性化。
バナナ、オートミール、海藻などで腸内環境を整え、便を柔らかくします。
就寝・起床時間を一定にすることで、自律神経を整え腸の働きを安定させます。
弛緩性便秘は「腸の活動を物理的に刺激して活性化すること」が鍵です。運動や腸マッサージ、生活リズムの見直しが大きな効果を生みます。

内側から改善するなら、腸まで届くビフィズス菌とオリゴ糖がオススメ!…>>詳しく解説
d-3. 直腸性便秘
直腸性便秘は、便が直腸まで到達しているのに排便の習慣や反射が鈍くなることで起こる便秘です。子どもや便意を我慢する習慣のある人に多く見られます。
症状の特徴
- 便は溜まっているのに便意が起きない
- 便が硬くなり排出困難
- 慢性的な残便感
長時間我慢すると、直腸の神経が鈍化して便意が起こりにくくなります。
直腸に便が滞留することで水分が吸収され、硬くなります。
便が直腸に留まることで、排便後もすっきり感が得られません。
主な原因
- 排便習慣の乱れ
- 加齢や筋力低下
「便意を我慢する」習慣が続くと、直腸反射が鈍くなります。
高齢者は腹筋や直腸筋の働きが弱まり、排便がスムーズに行えなくなります。
腸活のポイント
- トイレでの正しい排便姿勢
- 便意がなくてもトイレ習慣を作る
- 柔らかい便を作る食事
- 姿勢改善と腹筋トレーニング
足元に踏み台を置いて膝の位置を高くし、上半身を前傾させることで、直腸と肛門の角度が排便に適した角度に整い、便が出やすくなります。
朝食後や就寝前など、決まった時間に座る習慣をつけることで直腸反射を活性化。
水溶性食物繊維や良質なオイル(オリーブオイルなど)を適量摂取すると、腸管内を便がスムーズに移動して排出しやすくなります。
腹筋や骨盤底筋を軽く鍛えることで直腸の排便反射がサポートされ、過度ないきみを必要とせず便が出せるようになります。
直腸性便秘は「便意のタイミングを逃さず、排便を習慣化すること」が最重要です。食事・姿勢・筋力の3方向からアプローチすることで自然な便通が期待できます。

まとめ | 自分の便秘タイプに合う腸活で便秘を改善!
便秘はタイプによって原因や改善方法が異なります。
しかし、共通して言えるのは、腸内環境を整えることがすべての便秘改善に効果的という点です。
腸活のポイント
- 腸内フローラを整える腸活サプリを活用する
- 水溶性食物繊維を中心とした食事で便を柔らかくする
- 適度な運動で腸の蠕動をサポートする
- ストレスケアで自律神経を整える
- 水分補給と排便習慣を見直す
痙攣性便秘・弛緩性便秘・直腸性便秘それぞれに合った腸活を行うことで、便秘の悪循環から抜け出し、毎日スッキリ快適な排便リズムを取り戻せます。
腸活を習慣化することは、単なる便秘改善だけにとどまりません。
体調や肌の調子、集中力や気分の安定にもつながります。
今日から自分に合った腸活を始めて、快適な毎日を手に入れましょう。
腸活をもっと効率的に続けたいあなたへ
根本からのスッキリ!をサポートする
ビフィズス菌BB536を効率良く摂取できる腸活で、無理なく自然なお通じを目指しませんか?
【参考資料・出典】
※細田誠弥. "生活習慣と排便異常." 順天堂医学 50.4 (2004): 330-337.
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。