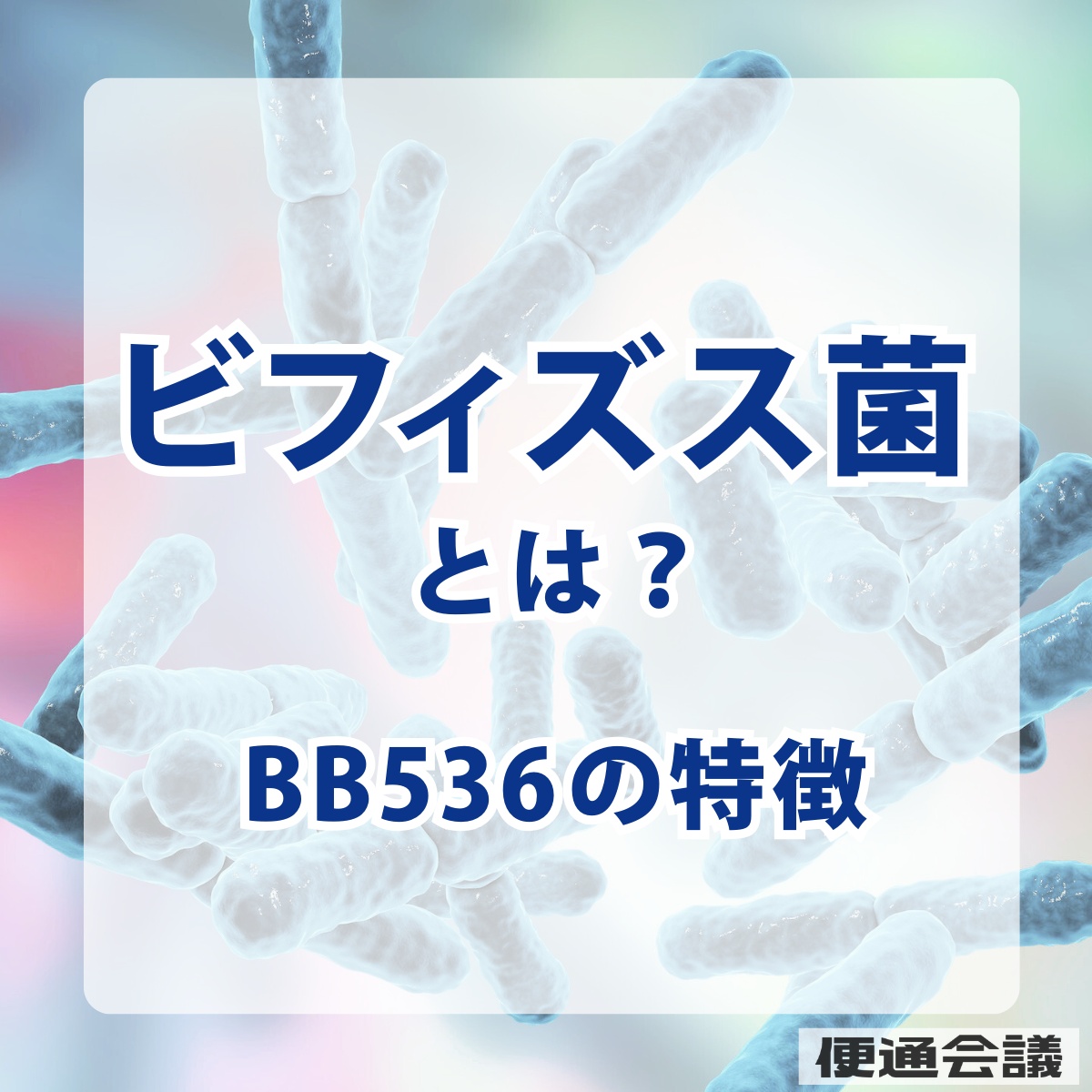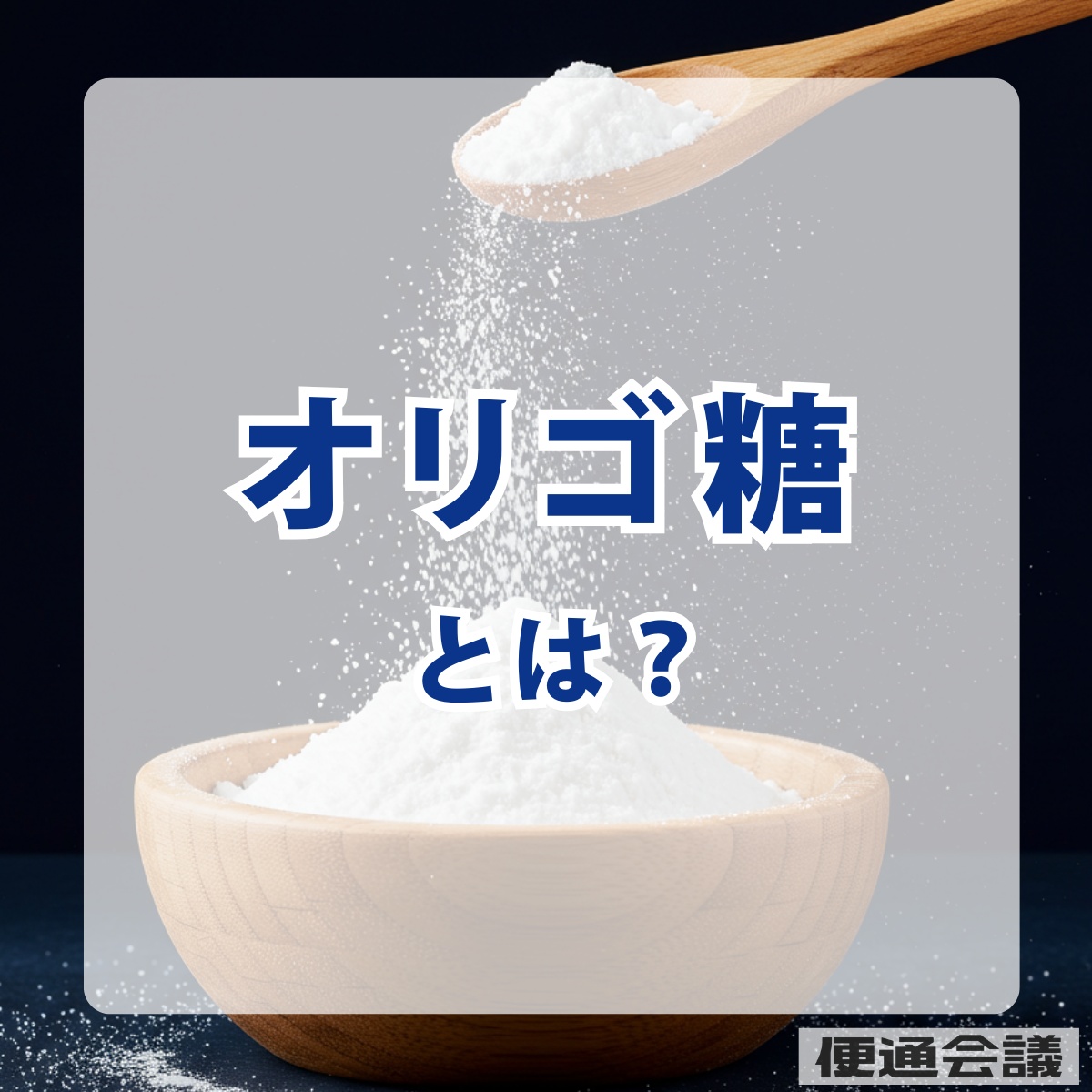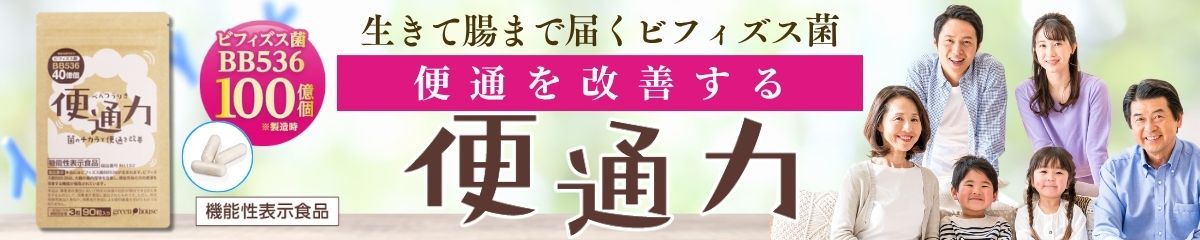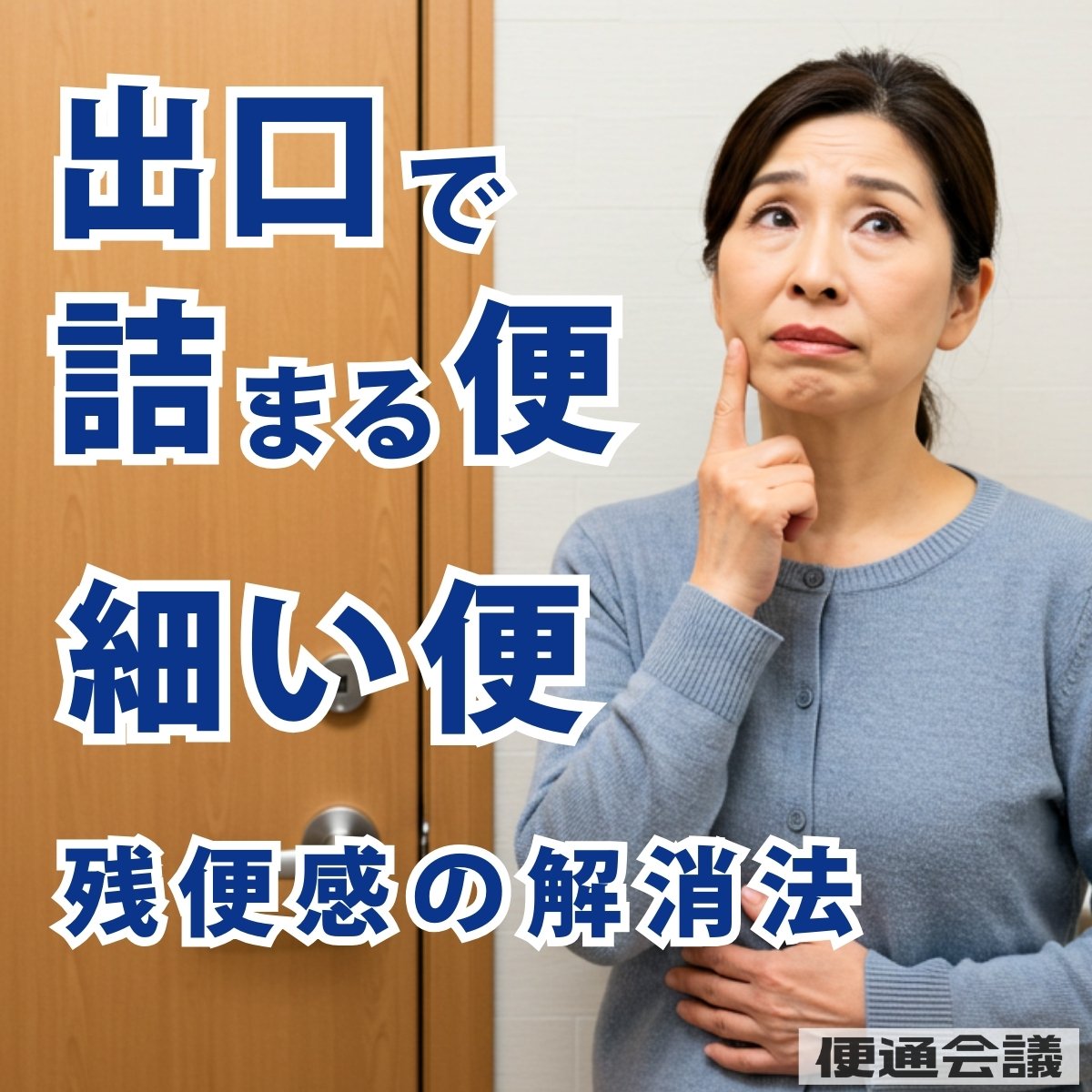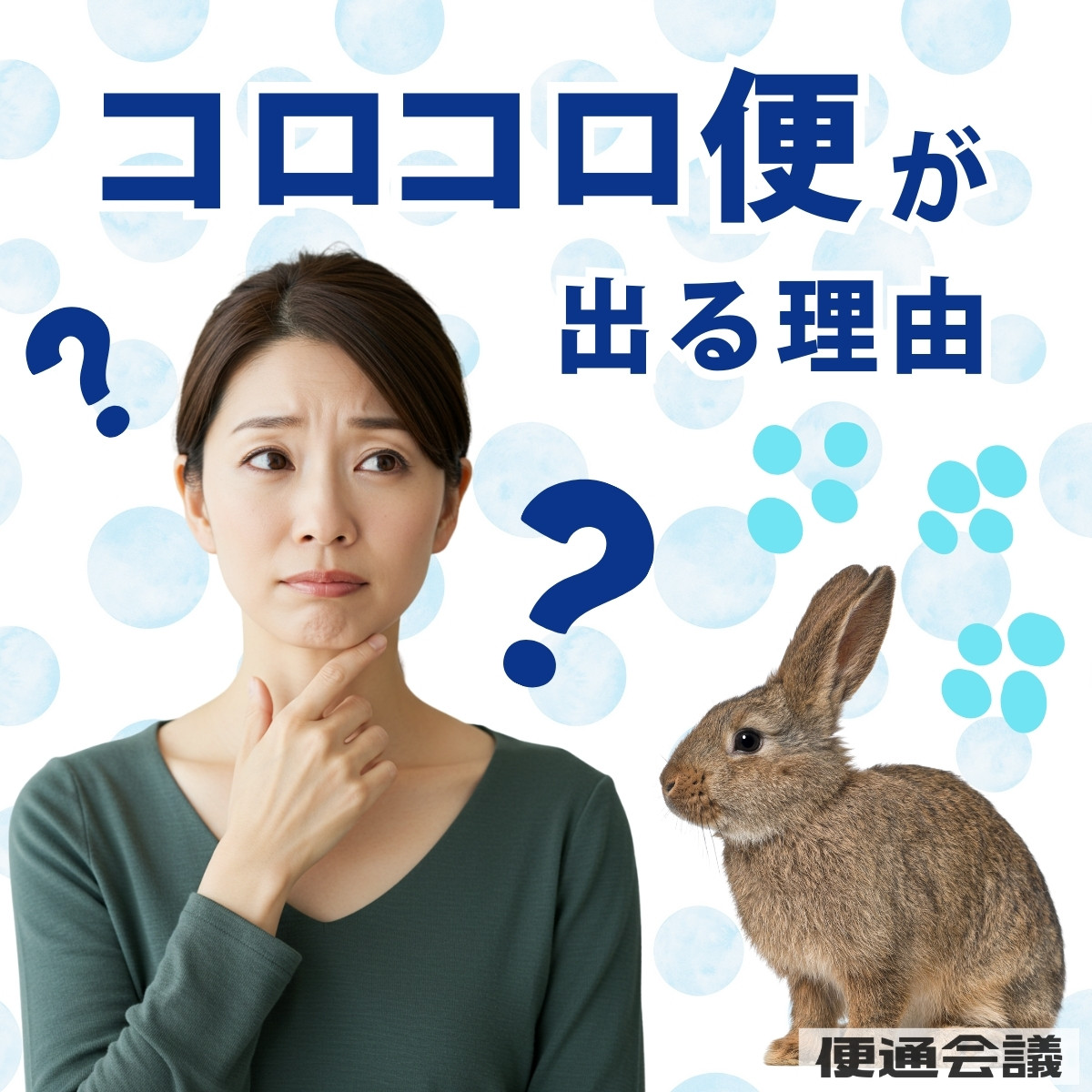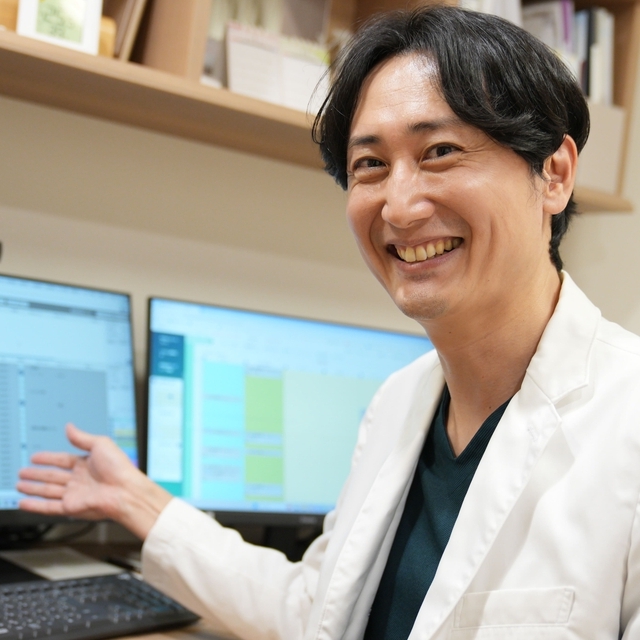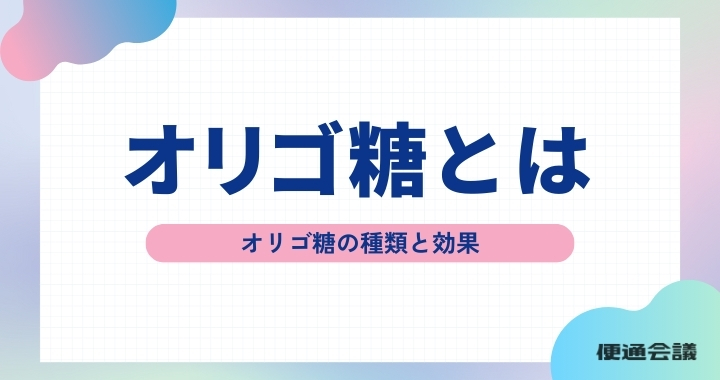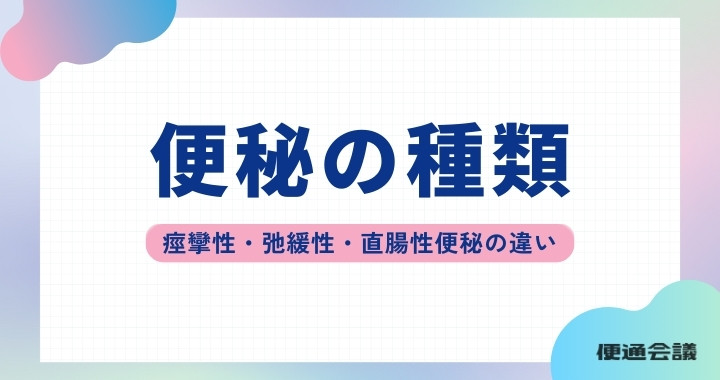最終更新日:2025.12.05
コーヒーと便秘の関係|出る人・詰まる人の違いとマンノオリゴ糖の可能性

目覚めの一杯にはじまり、食後や気分転換、眠気覚まし、リラックスタイム…。1日に何杯もコーヒーを飲む人も多いのではないでしょうか?
コーヒーを頻繁に飲む人の中には、「コーヒーを飲むとお通じが来る」と感じている人がいるかもしれません。しかし一方で、「コーヒーを飲むと便秘が悪化する」と感じる人もいます。
同じコーヒーなのに、なぜこんな違いが出るのでしょうか。
その秘密は、コーヒーに含まれるカフェインや他の成分が腸へもたらす作用と、個人の腸の敏感さや生活習慣にあります。
本記事では、コーヒーが便通を促すメカニズム、逆に便秘を悪化させる要因、そしてコーヒーに含まれる今話題の腸活成分「マンノオリゴ糖(MOS)」について詳しく知っていきましょう。
目次
コーヒーが便通を促すメカニズム | カフェインの作用とは?
コーヒーを飲むと便通が良くなる理由として挙げられるのが、カフェインをはじめとしたコーヒーに含まれる成分による、腸への作用です。
ここでは、コーヒーによる神経への刺激作用や消化液の分泌促進、さらにはデカフェコーヒーでも起こる腸刺激のメカニズムを詳しく解説します。
1. カフェインの神経刺激作用
コーヒーに含まれる目覚まし成分として知られる、カフェイン。しかし、その作用は眠気覚ましだけではありません。
カフェインには、中枢神経を刺激して交感神経と副交感神経のバランスに影響を与え、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発化させる働きがあります。
- 交感神経:覚醒や集中力を高め、心拍数や血圧の上昇をサポート
- 副交感神経:消化器官の動きを促し、腸の蠕動運動を刺激

具体的には、コーヒーを食後に摂取すると、大腸の収縮運動が活発化し、便が直腸へと押し出されやすくなることが、米国の研究で確認されています。
さらに個人差はありますが、カフェインに敏感な人ほど、飲んだ直後に便意を感じやすい傾向があります。
これは、交感神経刺激と副交感神経の反応が連動するためと考えられています。
2. 胃酸・胆汁分泌による消化促進
コーヒーには胃酸や胆汁の分泌を促進する作用もあります。
胃酸が十分に分泌されると、食べ物の消化がスムーズに進み、腸に運ばれる内容物が適度な水分を保持した便になりやすくなります。
- 胃酸の増加:タンパク質の分解が促進され、腸に送られる栄養物が効率的に消化される
- 胆汁の分泌促進:脂肪の消化がスムーズになり、便の通過がスムーズになる
この結果、便が腸内で滞留する時間が短くなり、便秘予防に効果を発揮します。
特に、朝食後にコーヒーを飲むと、腸が朝の活動モードに切り替わるタイミングと重なるため、自然な排便リズムを作ることができます。
さらに、コーヒーには消化酵素の分泌を刺激する作用もあるため、食後の胃腸の働きを総合的にサポートします。

3. デカフェでも起こる腸刺激
興味深いことに、カフェインを含まないデカフェコーヒーでも、腸の蠕動を促す作用が確認されています。
つまり、便通促進はカフェインだけの作用ではないのです。
- ポリフェノールやクロロゲン酸などの非カフェイン成分:腸内環境を整える作用や腸蠕動を刺激する可能性がある
- 温熱効果:温かい飲み物として腸壁を刺激することも排便を促す要素
このため、夜やカフェイン摂取を控えたい場合でも、デカフェコーヒーを適量飲むことで、便通のサポートが可能です。
また、デカフェコーヒーには腸内の善玉菌を増やす働きも期待され、長期的には腸内フローラの改善にもつながるとされています。
ヒト由来ビフィズス菌BB536とオリゴ糖で腸に優しい腸活をはじめませんか?>>詳しく解説
コーヒーで便秘が悪化する場合があるのはなぜ?
「コーヒーを飲むと、逆に便秘が悪化することがある…」。そんな経験をした人もいるでしょう。
その原因として、カフェインの利尿作用や体質、飲むタイミングなど、いくつかの要因が絡み合っていることが挙げられます。
次は、コーヒーの摂取と便秘悪化のメカニズムを分かりやすく解説します。
1. 利尿作用による水分不足
カフェインは利尿作用を持つため、何杯もコーヒーを飲むと、体内の水分が過剰に排出されることがあります。
- 水分不足の影響:腸内で便が乾燥し、硬くなる
- 硬い便のリスク:腸内に滞留しやすく、排便時に肛門を傷つけ、切れ痔や痛みの原因になる
特に、朝の空腹時にコーヒーを大量に飲む習慣がある人や、運動不足の人、さらに水分補給が少ない人は要注意です。
水分不足は、便秘だけでなく全身の血流や代謝にも影響を及ぼします。
排出しやすい便の柔らかさを保つためにも、1日を通してしっかりと水分補給することが大切です。

2. 過敏性腸症候群(IBS)の人の注意点
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome:IBS)は、大腸に器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や便秘・下痢などの症状が慢性的に起こる疾患です。
ある研究では、過敏性腸症候群患者がカフェインを多く摂取するほど症状が悪化することが、示されました。
また、過敏性腸症候群は精神的ストレスや生活リズムの乱れでも悪化するため、コーヒーの刺激が腸に負担をかけやすくなります。
そのため、過敏性腸症候群の人はカフェイン入りコーヒーを控える、またはデカフェや少量にとどめるなど、自分の症状に合わせた工夫が必要です。

3. 飲むタイミングの影響
コーヒーを飲むタイミングも、便通に大きく影響します。
- 空腹時に飲む場合
空腹で胃腸に食べ物がない状態でカフェインを摂取すると、胃酸が過剰に分泌され、胃腸に負担をかけることがあります。
実は、胃酸過多も腹痛や便秘悪化を引き起こす原因の一つです。 - 夕方以降に飲む場合
カフェインは覚醒作用があるため、夕方以降に摂取すると寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
満足に眠れない日々が続くと自律神経が乱れ、腸内環境が悪化。便秘の原因となります。

このように「量」「体質」「飲むタイミング」によって、コーヒーで便秘が改善するか、悪化するかが変わるのです。
コーヒーに含まれるマンノオリゴ糖(MOS)の役割
さらに、腸活ブームの昨今、コーヒーに含まれる「マンノオリゴ糖(MOS)」が注目されています。
マンノオリゴ糖は単なる便通サポート成分ではなく、腸内フローラを整え、腸の働きを総合的にサポートする役割を持っています。
ここでは、マンノオリゴ糖とは何か、腸内でどのように働くのか、そして研究成果や実践上の注意点まで詳しく解説します。
1. マンノオリゴ糖(MOS)とは?
マンノオリゴ糖(MOS)は、コーヒー豆の細胞壁や微量の天然成分に含まれる難消化性オリゴ糖です。
マンノオリゴ糖(MOS)の特徴
腸の動きをコントロールしている自律神経を整えることで、便秘の根本改善が期待できます。
- 小腸では分解されない → 消化酵素で分解されず、大腸まで到達
- 善玉菌のエサになる → 腸内でビフィズス菌などの栄養源として利用される
MOSは、単なる食物繊維とは異なり、腸内の善玉菌に特化した「選択的プレバイオティクス」として作用する点がポイントです。
コーヒーを飲むことで、日常の食事だけでは得にくい善玉菌サポートを得られる可能性があります。

2. マンノオリゴ糖の腸内での働き
マンノオリゴ糖(MOS)が腸内に届くと、さまざまな作用を通じて便通改善や腸内環境のサポートにつながります。
マンノオリゴ糖の摂取量と排便日数・排便回数の関連を調べた臨床試験では、1日に3.0g摂取した場合、1.0gの時に比べて、排便日数・排便回数が約3倍上昇したことが報告されています。
こういった研究の結果から、マンノオリゴ糖の作用として
- ビフィズス菌増加:善玉菌が増えることで腸内フローラが改善され、腸内環境が安定
- 短鎖脂肪酸生成:酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸が増え、腸蠕動(ぜんどう)運動が活発化し、便通がスムーズに
といった、腸全体の機能をサポートする効果が示唆されています。
コーヒーで刺激を与えて便秘改善する前に…便通を改善するビフィズス菌サプリ「便通力」で体に優しい腸活をはじめよう!>>詳しく解説
便通改善につながるコーヒー習慣
ここでは、腸にやさしく、さらに便通効果を高めるためのコーヒー習慣を具体的に紹介します。
1. 適量の目安
コーヒーには便通を促す効果がありますが、飲みすぎは逆効果になることもあります。
- 目安:1日2〜5杯程度
- 多すぎる場合のリスク
カフェインによる交感神経過剰刺激で腸が緊張
利尿作用が強まり、体内の水分不足で便が硬化
適量を守ることで、便通改善の効果を保ちながら、カフェインの副作用を抑えることができます。

2. 飲むタイミング
コーヒーの便通効果は、飲む時間帯によって変わります。
- 朝食後(9〜10時)
起床直後の腸はまだ活動が不十分ですが、朝食を摂った後のタイミングでコーヒーを飲むと、腸蠕動(ぜんどう)運動が起きやすく、スムーズな排便につながります。 - 昼食後(13〜14時)
食べ物の消化が始まったタイミングでコーヒーを飲むと、胃酸や胆汁分泌を促進し、便の移動を助けます。 - 夕方以降は避ける
夕方以降にカフェインを摂取すると、睡眠の質が低下し、腸内環境にも悪影響が及ぶ可能性があります。夜はデカフェに切り替えると安心です。

3. 水分補給
コーヒーには利尿作用があるため、飲むだけでは水分が不足する場合があります。腸内の水分量が不足すると便は硬くなり、便秘悪化の原因に。
- おすすめの水分補給
コーヒー1杯につき、コップ1杯の水を追加で摂る
日中に少しずつ水分を補給する習慣をつける
水分補給を意識するだけで、便が柔らかくなり、排便がスムーズになります。
4. デカフェ活用
午後や夜にコーヒーを楽しみたい場合、デカフェコーヒーを活用するのも効果的です。
- メリット
カフェインを控えながら便通改善効果を維持
睡眠の質を損なわず、夜間の腸活をサポート
デカフェは通常のコーヒーに比べてカフェイン量がほぼゼロのため、就寝前のリラックスタイムや、カフェイン過敏の人でも安心して取り入れられます。
腸活効果を高めるコーヒーにプラスαのアレンジ
毎日のコーヒーに少し手を加えるだけで、便通改善や腸内環境のサポート効果をさらに高められます。味わいも豊かになり、毎日のコーヒー時間がさらに満足度の高いひと時に。
手軽に取り入れられる、コーヒーの「腸活アレンジ」を紹介します。
1. 牛乳を加える
牛乳をコーヒーにプラスするだけで、腸への働きかけが変わります。
- 乳糖が善玉菌のエサに
腸内の乳酸菌やビフィズス菌は乳糖を分解して乳酸や酢酸を生成します。これが蠕動運動を刺激し、便通改善につながります。 - カルシウムやタンパク質も補給
牛乳を加えることで、栄養面でも腸内環境にプラスの影響があります。特に、カルシウムは腸の健康維持にも役立つとされています。 - 注意点
乳糖不耐症の方は、ラクトースフリー牛乳や植物性ミルクを活用すると安心です。

2. ハチミツを混ぜる
自然の甘みとしてハチミツを加えるだけで、腸活効果がさらにアップします。
- オリゴ糖が善玉菌のエサに
ハチミツに含まれるオリゴ糖には、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を増やす効果があり、腸内フローラの改善に寄与します。 - ビタミン・ミネラル・有機酸も補給
腸だけでなく、疲労回復や栄養補給にも役立つため、朝のコーヒーに加えるのがおすすめです。 - 注意点
ハチミツは、1歳未満の乳児には与えないようにしましょう。

3. スパイスやポリフェノール追加
さらに、腸の働きを助けるスパイスやポリフェノールを取り入れると、コーヒーの効果を多角的にサポートできます。
- シナモン
血行を促進し体温を上げることで腸の活動を活発化
冷え性の人にもおすすめ
過剰摂取に注意し、クマリン含有量の少ない「セイロンシナモン」を選ぶ - ココア
ポリフェノールが腸内善玉菌の増加をサポート
抗酸化作用で健康維持にも寄与
このように、少しのアレンジでコーヒーの味わいも変わり、腸活の効果もより高まります。毎日のコーヒー時間を「腸にやさしい時間」として楽しみながら、便通改善を習慣化できます。
まとめ | 毎日のコーヒー習慣で便通を整えよう
今回は、コーヒーの便秘改善作用について解説しました。
コーヒーは便通を促す効果が期待できる一方、体質や飲み方次第では便秘を悪化させることもあります。
腸が刺激に反応する人は自然に排便が促されますが、敏感な腸や水分不足のある人は硬い便や便秘の原因になることもあるため注意が必要です。
コーヒーに含まれるマンノオリゴ糖(MOS)や、牛乳・ハチミツ・スパイスなどの腸活アレンジは便通改善をサポートする補助的な役割を果たします。
さらに、日々の食生活やコーヒー習慣だけでは補いきれない部分には、腸活サプリを取り入れるのもおすすめです。

自分に合った量とタイミングでコーヒーを楽しみつつ、サプリを組み合わせることで、毎日の便通をより安定させ、腸内環境を整えることができます。
便通改善をしっかりサポートしたい方は、まずは自分の体質に合った腸活サプリを試してみましょう。
腸活をもっと効率的に続けたいあなたへ
コーヒー習慣にプラスして腸活!
ビフィズス菌とオリゴ糖で腸を内側からサポート。
習慣にしやすいシンプルな腸活、始めてみませんか?
【参考資料・出典】
※種村一識, et al. "コーヒー摂取が胃運動および自律神経活動に与える効果の検討." 日本栄養・食糧学会誌 65.3 (2012): 113-121.
※Brown SR, Cann PA, Read NW. Effect of coffee on distal colon function. Gut. 1990 Apr;31(4):450-3.
※藤井繁佳, et al. "コーヒー豆由来のマンノオリゴ糖の食品への高度応用." 日本食品工学会誌 8.4 (2007): 231-238.
※浅野一朗, et al. "コーヒーマンナン由来マンノオリゴ糖の腸内細菌資化性." 日本農芸化学会誌 75.10 (2001): 1077-1083.

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。