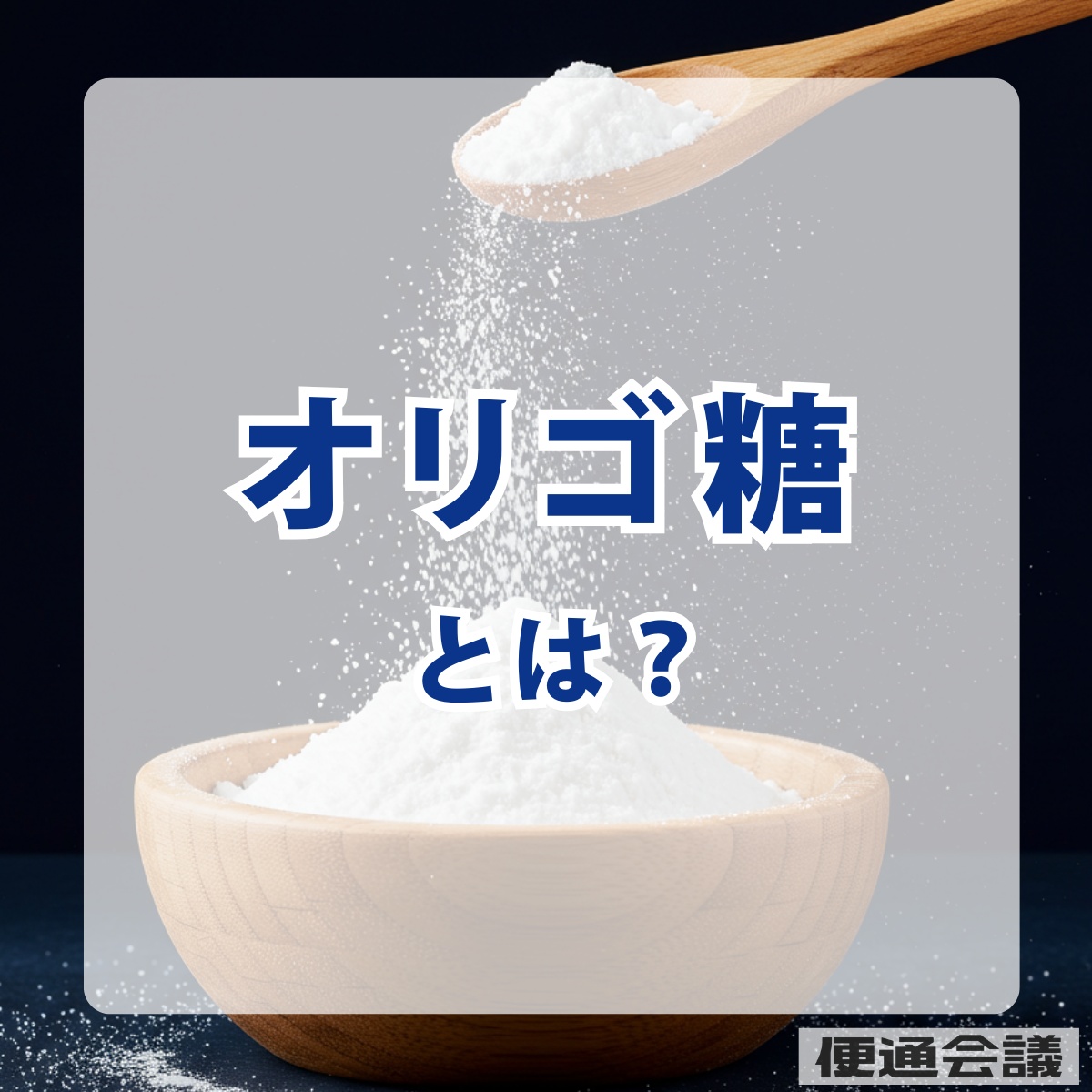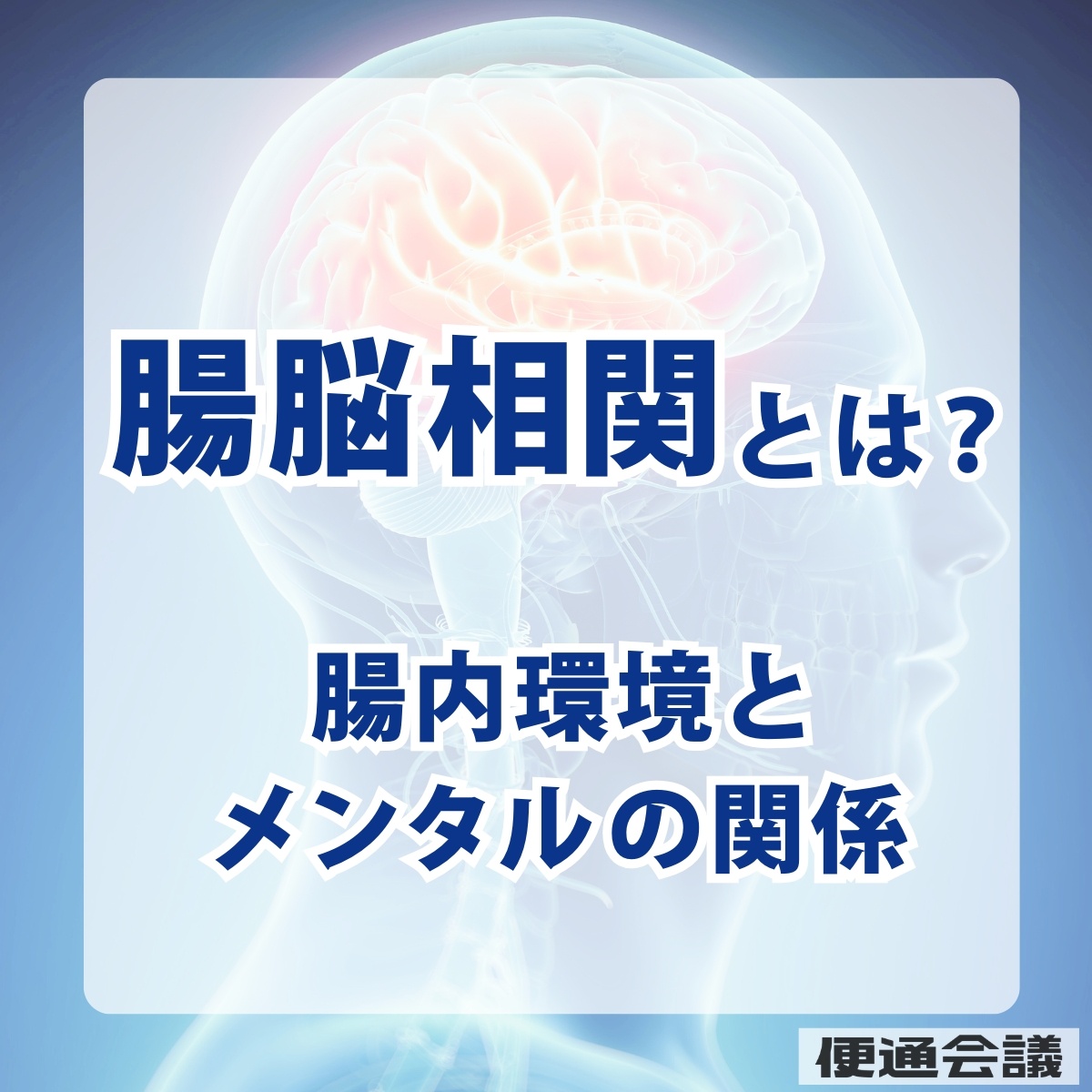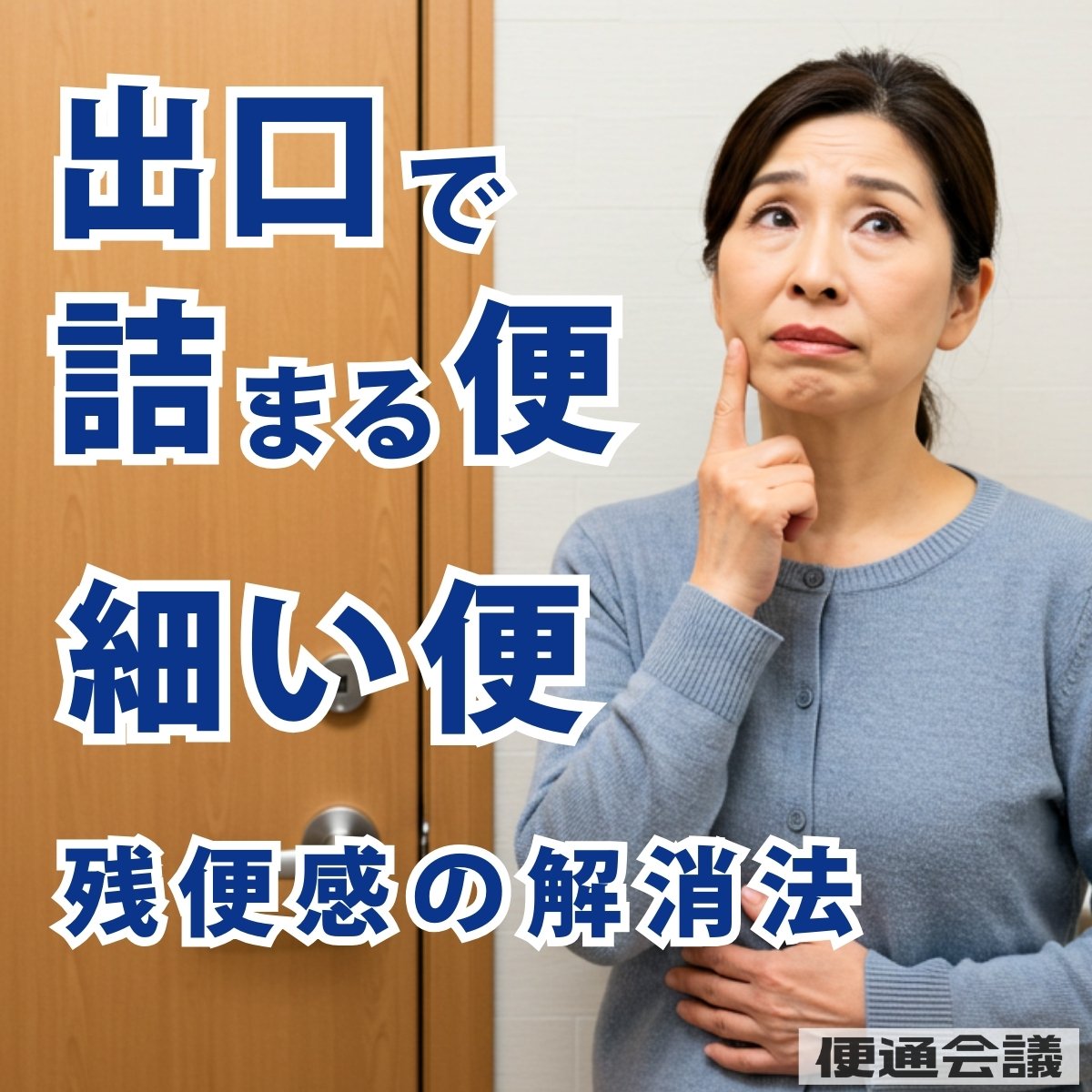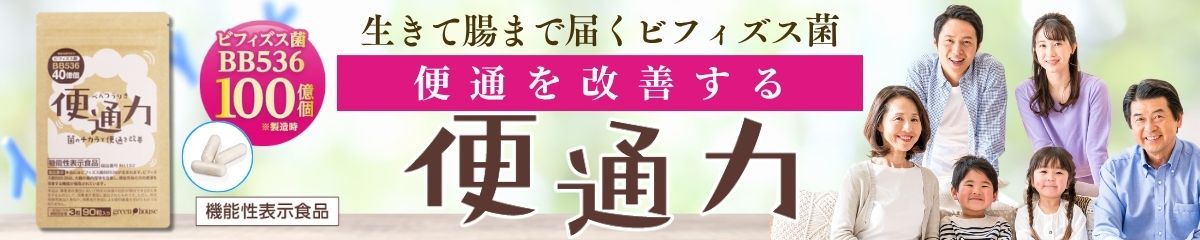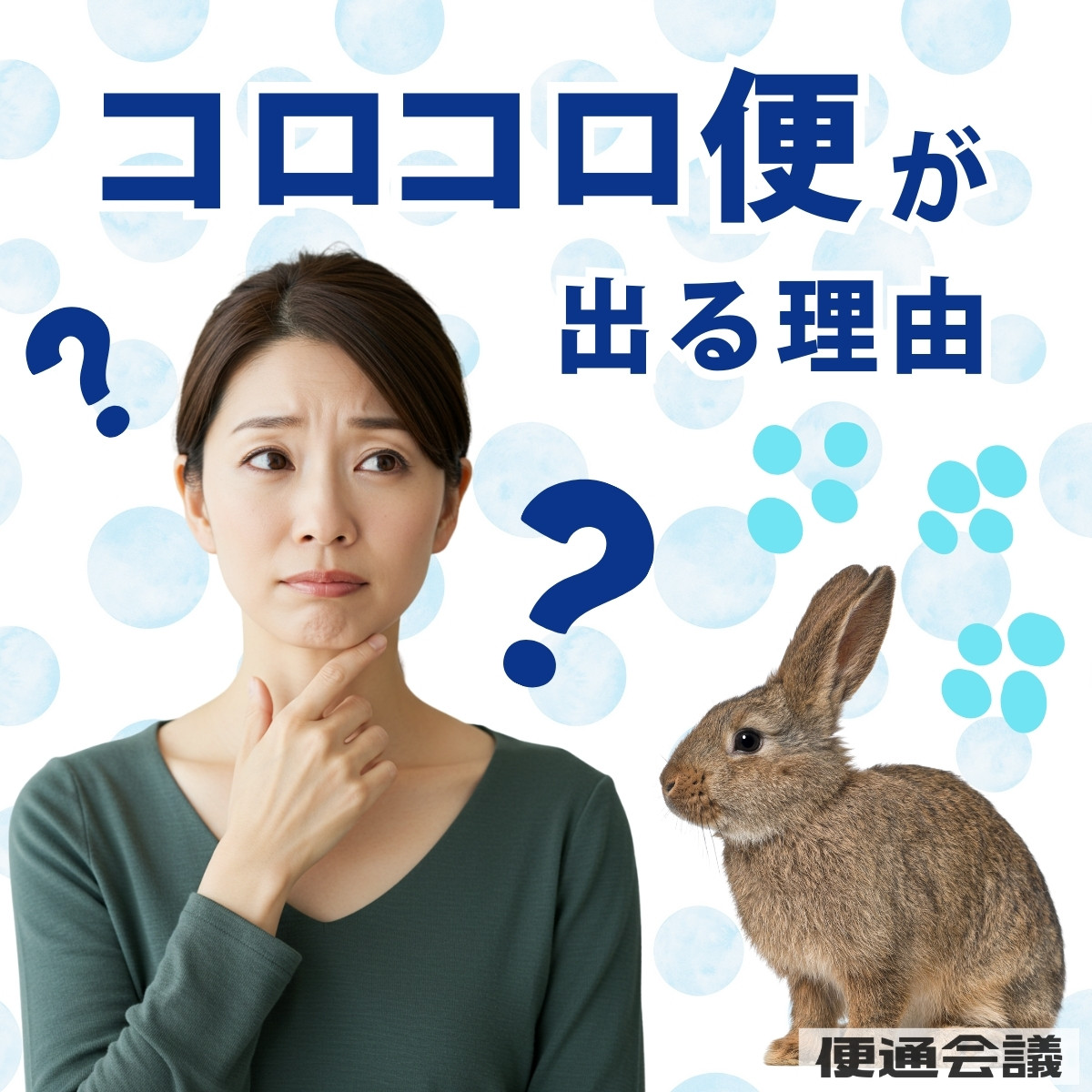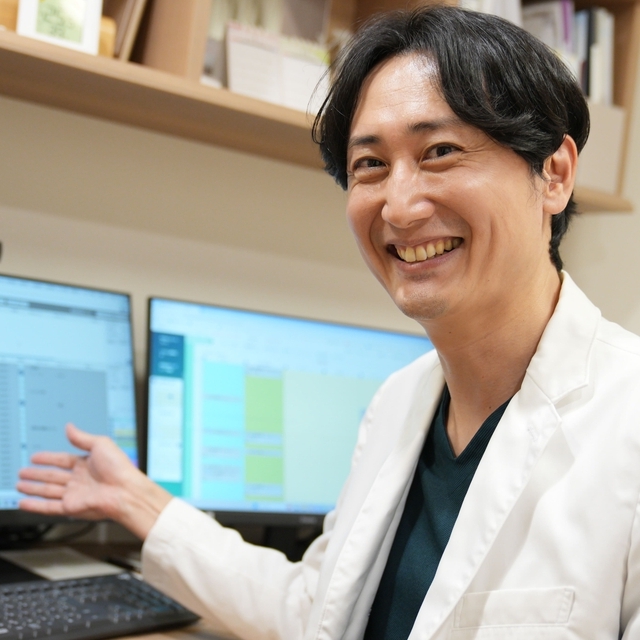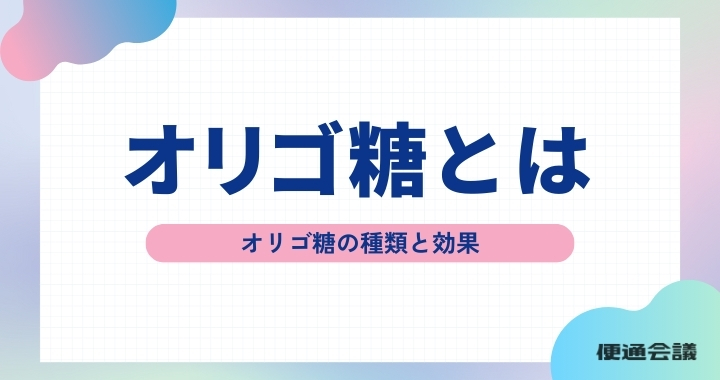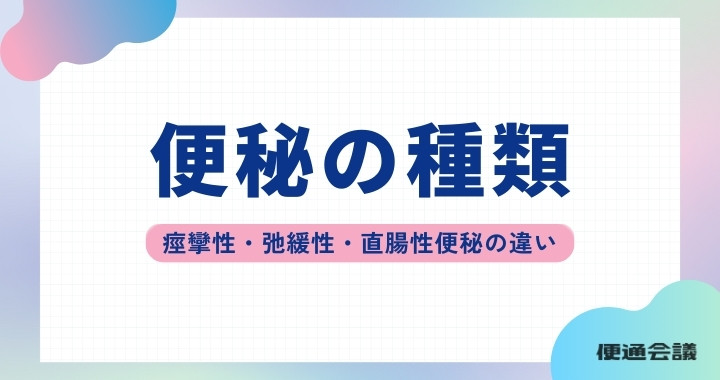最終更新日:2025.12.5
食物繊維とは?腸内環境を整えて便秘改善に役立つ“第六の栄養素”

便秘改善や腸内環境を良くするために欠かせないのが、食物繊維です。
近年の研究では、食物繊維は腸内環境の改善だけでなく、美肌や睡眠の質、体重管理、メンタルの安定など、全身の健康にも幅広く関与することが明らかにされています。
2025年版「日本人の食事摂取基準」では、健康維持や便秘予防の観点から、一日に必要な食物繊維の摂取量が引き上げられました。
本記事では、食物繊維の基本情報から腸活への効果、推奨摂取量などについて、分かりやすく解説します。
食物繊維について深く知り、効率良く腸活を実践しましょう。
目次
- 便通改善につながる食物繊維の効率的な摂取方法は?
- 短鎖脂肪酸(SCFA)とは?腸内発酵で生まれる健康成分の秘密
- 2025年版食物繊維摂取基準の見直しと1日目安量の最新情報
- 食物繊維が体重管理・肥満予防に役立つメカニズム
- まとめ | 食物繊維で腸内環境を整え健康・美容をサポート
食物繊維の基本 | 腸だけでなく全身の健康をサポートする働き
食物繊維は、人の消化酵素では分解されずに大腸まで届く炭水化物の一種です。
糖質と同じ「炭水化物」に分類されますが、糖質のようにエネルギー源にはなりません。
ただし、大腸で腸内細菌により発酵されて短鎖脂肪酸(SCFA)が生成され、これが間接的にエネルギーや代謝に寄与します。
そして、食物繊維のもっとも大きな役割が「腸内環境を整える」ことなのです。
“栄養にならない不要物”から“第六の栄養素”へ
食物繊維は、1970年代までは「栄養にならない不要物」と考えられていました。
ところが、その後の研究で食物繊維には以下のような働きがあることが明らかになったのです。
食物繊維の主な働き
- 腸の動きを活発にする
- 血糖値やコレステロール値の上昇を抑制して、生活習慣病の予防に寄与する
こうした経緯から、食物繊維はたんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルに続く「第六の栄養素」として位置づけられています。

腸内細菌の増加をサポートする食物繊維
腸内には百種類以上の腸内細菌が生息し、それぞれの菌種が集団を形成しています。
これが、いわゆる「腸内フローラ(腸内細菌叢)」です。
腸内フローラのバランスが整うと腸内環境が良好になり、免疫機能や代謝機能、さらにはメンタルの安定にもつながることが、さまざまな研究によって報告されています。
発酵性が高い食物繊維は腸内細菌の“えさ”となり、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を増やすことで、腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスを整える重要な役割を担っているのです。
水溶性・不溶性食物繊維の違いと便秘改善への効果
食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類に分けられ、それぞれ異なる働きを持っています。
どちらも健康維持に欠かせない成分であり、偏りなく摂取することが腸内環境を整えるための重要なポイントです。
水溶性食物繊維 | 腸内細菌を育て、血糖や脂質の吸収を調整する
水溶性食物繊維は水に溶け、腸内でゲル状になる性質があります。
このゲルが腸の中をゆっくり移動することで、糖や脂質が穏やかに吸収され、食後の血糖値が急上昇するのを抑制します。
また、コレステロールを体外へ排出する手助けをするため、動脈硬化や高脂血症の予防にも有効性が期待できます。
▶水溶性食物繊維が多い代表的な食品
- ごぼう(ゆで)
- アボカド(生)
- なめこ(ゆで)
- にんじん(ゆで)
- モロヘイヤ(生)
- 大豆(ゆで)
- りんご(皮つき)
- ケール(生)
不溶性食物繊維 | 腸を刺激して排便を促す“腸の掃除役”
不溶性食物繊維は水に溶けにくく、大腸まで届いた後に水分を吸収して膨張。膨らんだ内容物が腸壁を刺激し、蠕動運動を活発にして排便を促進します。
また、腸内に残った有害物質や発がん性物質を吸着して体外へ排出するため、腸内を清潔に保つ働きも期待されている“腸の掃除役”です。
噛みごたえのある食材に多く含まれており、食感の楽しさと満腹感の持続にも寄与すると考えられています。
▶不溶性食物繊維が多い代表的な食品
- きくらげ(乾)
- おから(乾)
- 干しひじき(乾)
- 干ししいたけ(乾)
- 小麦ふすま(ブラン)
- きなこ(黄大豆)
- 納豆(1パック換算)
- さつまいも(焼き)

水溶性と不溶性の理想的な摂取バランスは、1:2とされています。
野菜・果物・豆類・穀物を組み合わせることで、腸内細菌叢の健全化や便通リズムの安定がより効果的に促されるでしょう。
便通改善につながる食物繊維の効率的な摂取方法は?
食物繊維を摂取するコツは、1日の食事に野菜・果物・豆類・穀物を組み合わせて取り入れることです。
例えば、以下のようなメニュー例で食物繊維の摂取量を自然に増やせます。
▶食物繊維を摂取する1日のメニュー例
- 朝食:オートミールとフルーツ
- 昼食:野菜たっぷりの玄米弁当
- 夕食:主菜にきのこや海藻を添える

重要なのは、急にたくさん摂るのではなく、少しずつ食事に取り入れて、腸を慣れさせることです。
また、食物繊維が多い食べ物を摂る時は、水分もしっかり補給しましょう。
水分とともに摂ることで便通がスムーズになり、腸内環境を整える効果を最大限に引き出せます。
短鎖脂肪酸(SCFA)とは?腸内発酵で生まれる健康成分の秘密
便秘改善や腸内環境の維持に欠かせないのが、短鎖脂肪酸(SCFA)です。
短鎖脂肪酸は、腸内で食物繊維が善玉菌(ビフィズス菌や酪酸菌など)によって発酵される過程で生成されます。
代表的なものは酢酸・プロピオン酸・酪酸で、生成比率は一般的に約60:20:20です。ただし、個人の腸内細菌叢によって変動します。
▶短鎖脂肪酸の働きと腸への効果
- 腸の蠕動を促進
短鎖脂肪酸の中でも、特に大腸を健康に保つために重要な働きを担っているのが、酪酸です。
酪酸は大腸粘膜の主要なエネルギー源であり、腸の動きを活発にして便の通過をスムーズにします。
これにより、便の滞留が減り、自然な排便リズムが整いやすくなります。 - 腸内環境を弱酸性に維持
短鎖脂肪酸は腸内pHを弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑制し、善玉菌が優位なバランスを維持しやすくします。
その結果、便やガスのニオイの原因となる腐敗産物が減少します。 - 腸のバリア機能を強化
酪酸は腸の上皮細胞を保護・強化し、炎症や有害物質の侵入を防ぎます。
この働きによって腸粘膜の機能が高まり、水分吸収や便の形成もスムーズに行われます。
つまり、食物繊維の積極的な摂取は、便秘改善だけでなく腸内環境を整え、全身の健康維持や代謝の安定にも役立つということなのです。
腸から全身へ広がる短鎖脂肪酸の健康効果
腸内で生成された短鎖脂肪酸は血流を介して全身に運ばれ、エネルギー代謝の調整や脂肪蓄積の抑制など、代謝バランスの安定にも関与します。
近年の研究では、短鎖脂肪酸が炎症を抑え、インスリン感受性を高めることで、2型糖尿病や肥満のリスク低下に寄与することも報告されています。
また、腸と脳をつなぐ「腸–脳相関」を通じて、ストレス応答や睡眠リズムの安定に関わる可能性が、さまざまな研究で示唆されています。
腸内環境が良くなると自律神経が安定し、交感神経と副交感神経が正しく働き、心身を健康な状態へ導くと考えられます。

2025年版食物繊維摂取基準の見直しと1日目安量の最新情報
近年の研究では、食物繊維の十分な摂取が腸内環境の改善や代謝機能の安定に寄与することが明らかにされています。
2025年版の「日本人の食事摂取基準」では、健康維持や生活習慣病予防の観点から、食物繊維の摂取目標量が引き上げられました。
具体的な目安量は以下の通りです。
▶年代別の食物繊維摂取目標量
(日本人の食事摂取基準2025年版)
- 12~14歳:1日17g以上
- 15~17歳:1日19g以上
- 18~29歳:1日20g以上
- 30~64歳:1日22g以上
- 65~74歳:1日21g以上
- 75歳以上:1日20g以上
- 12~14歳:1日16g以上
- 15~74歳:1日18g以上
- 75歳以上:1日17g以上
【男性】
【女性】
しかし、実際には以下のグラフのように、ほとんどの世代で食物繊維の摂取量が足りていません。

科学的な研究によれば、少なくとも1日25g程度の食物繊維を摂取することで、生活習慣病のリスク低下や便秘改善に有効であると考えられています。
腸活の基本として、摂取基準の値を意識して毎日の食事内容を工夫すると良いでしょう。
食物繊維が体重管理・肥満予防に役立つメカニズム
食物繊維は便秘改善だけでなく、体重管理にも重要な役割を果たすと考えられています。
大規模な前向き研究では、非肥満者を対象に長期的な体重増加と食物繊維摂取量の関係が調査され、食物繊維の摂取量が多い人ほど、体重の増加が抑えられることが確認されました。
このことから、食物繊維は日々の体重コントロールに貢献する栄養素であるといえるでしょう。
▶食物繊維が体重増加を抑えるメカニズム
- 食事量の調整
食物繊維は噛みごたえや満腹感を高めるため、食事量のコントロールに役立ちます。 - 脂肪蓄積の抑制
水溶性食物繊維が生成する短鎖脂肪酸が腸内細菌のバランスを整え、脂肪の蓄積を抑える働きがあると考えられています。 - 代謝機能の促進
腸内環境が改善し便通が安定すると、老廃物や有害物質の滞留が減り、代謝機能がよりスムーズに働きやすくなります。
このように、食物繊維の摂取は直接的・間接的に体重管理を支える要素として注目されています。
食物繊維が豊富な食生活を送ることが、長期的な体重維持や肥満予防に効果的と考えられるでしょう。
まとめ|食物繊維で腸内環境を整え、体の内側から健康をサポート
食物繊維の働きは、腸内環境を整えて便秘を改善するだけではありません。
水溶性・不溶性の両方を意識的に摂ることで、善玉菌が活性化し、短鎖脂肪酸(SCFA)の生成が促されます。
短鎖脂肪酸は単に腸を動かすだけではなく、腸内環境を健全に保ちながら、便通・代謝・免疫・メンタルまで支える中心的な存在です。
短鎖脂肪酸が増えることで腸のバリア機能が強化され、老廃物や有害物質の排出がスムーズになり、腸内フローラのバランスが健全に保たれます。

腸内環境が整うと、便秘改善・予防だけでなく、肌の調子が良くなったり、効率良くダイエットが出来たりといったメリットが期待できます。
つまり、腸を整えることは、見た目やメンタル面にも影響を与える“全身ケア”の第一歩といえるでしょう。
現代の日本人は、食物繊維が不足しやすい傾向にあります。
しかし、日々の食事に野菜・果物・豆類・海藻・穀物を取り入れるだけでも、腸は変化していきます。
今日の一食から、食物繊維の摂取を意識する習慣を実践してみませんか。
【参考資料・出典】

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。