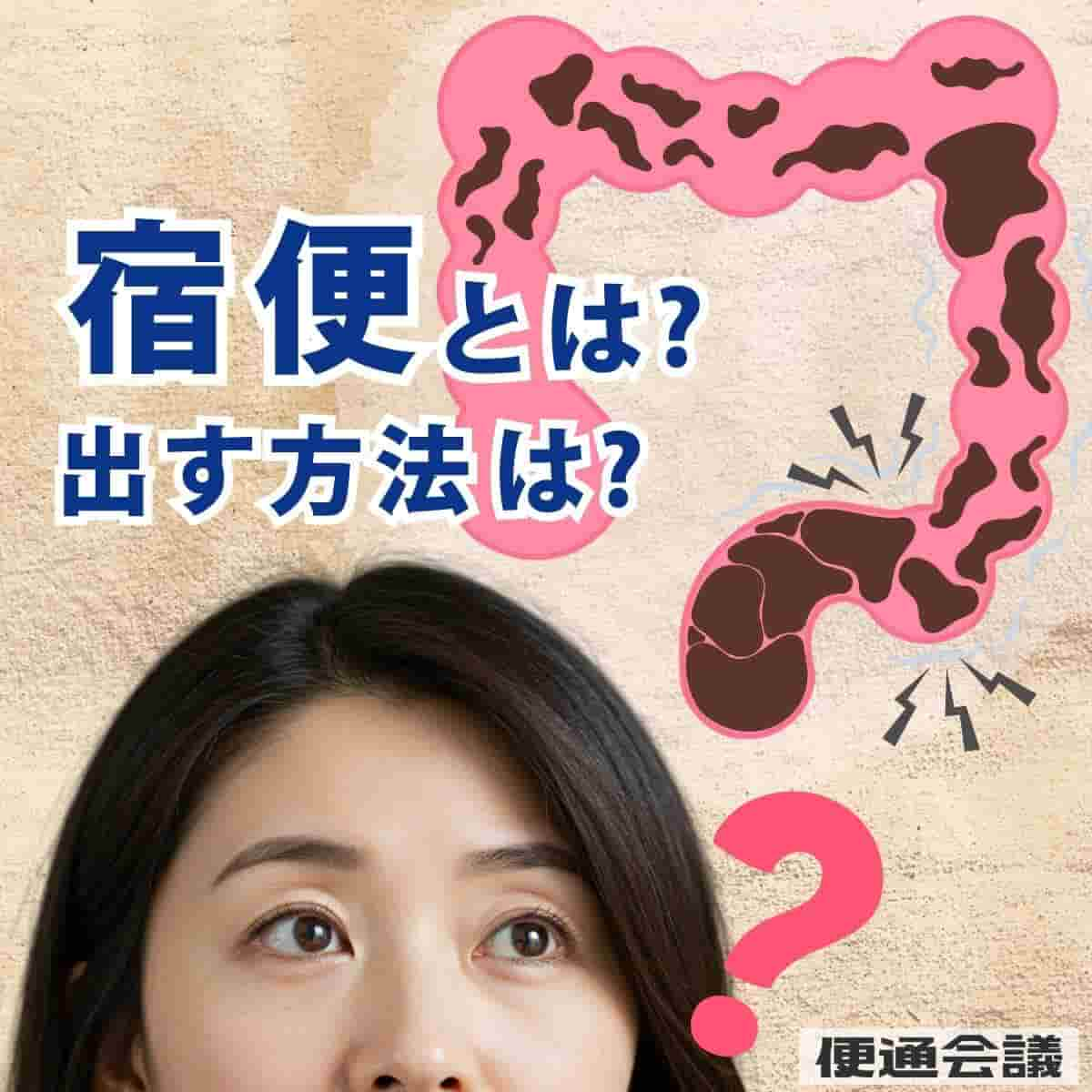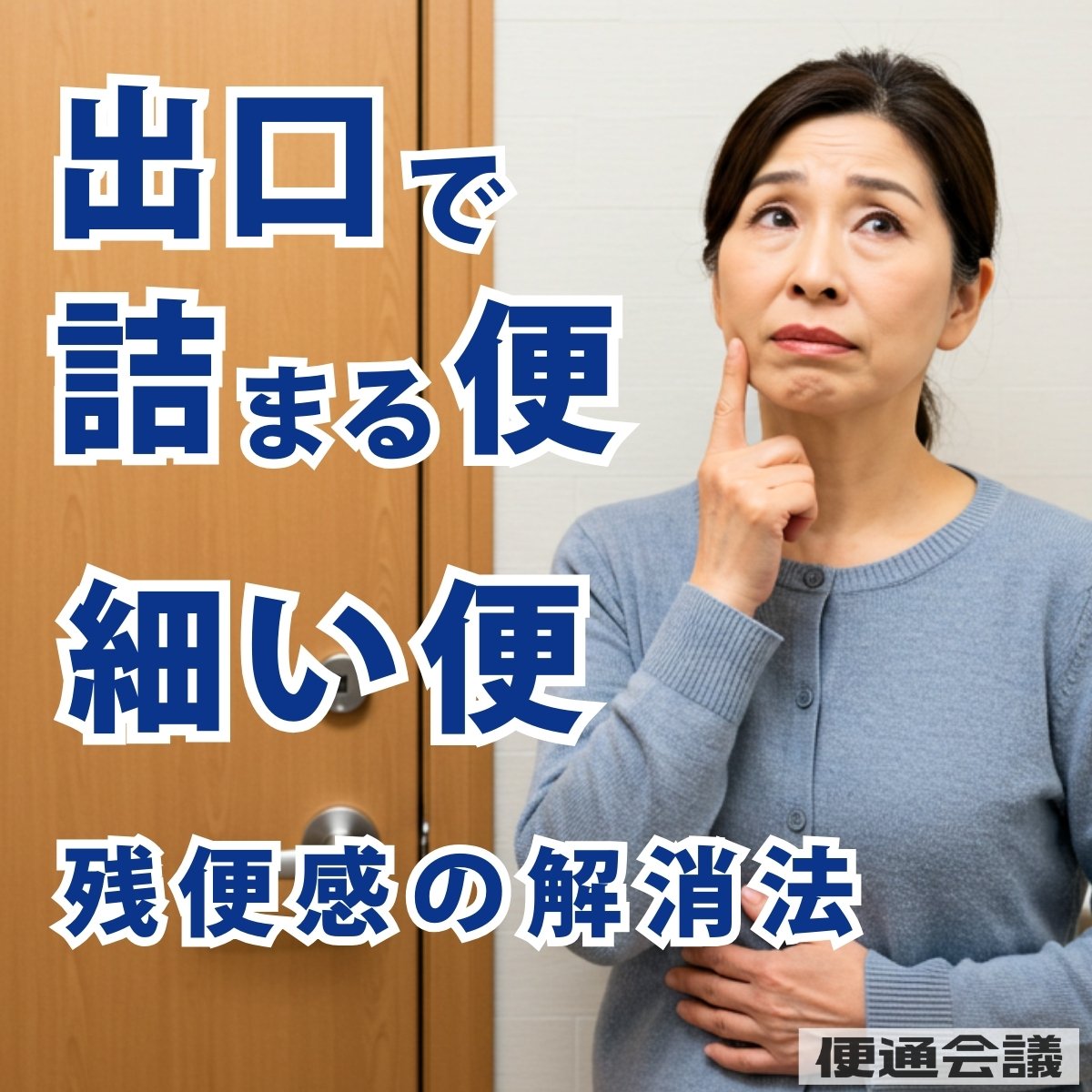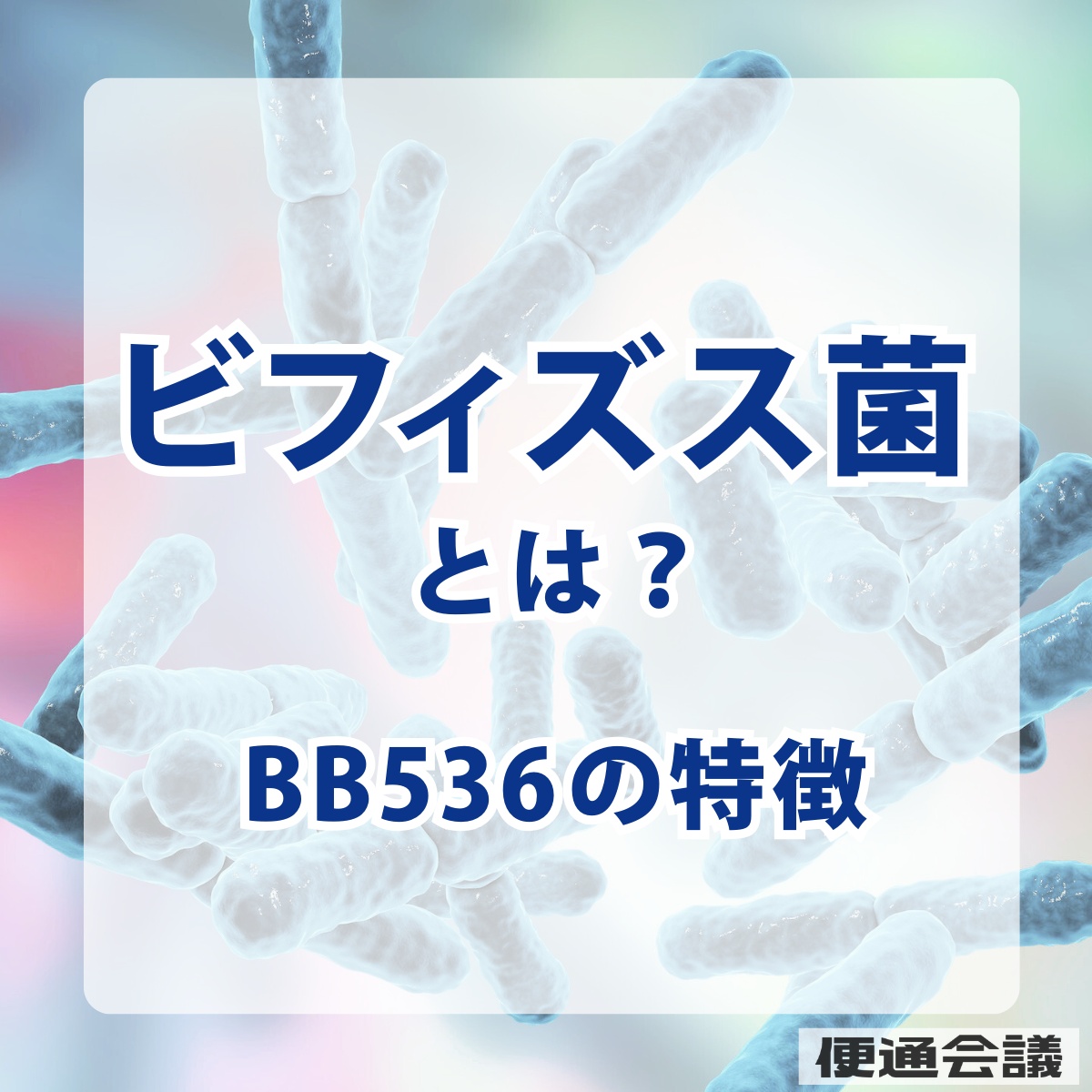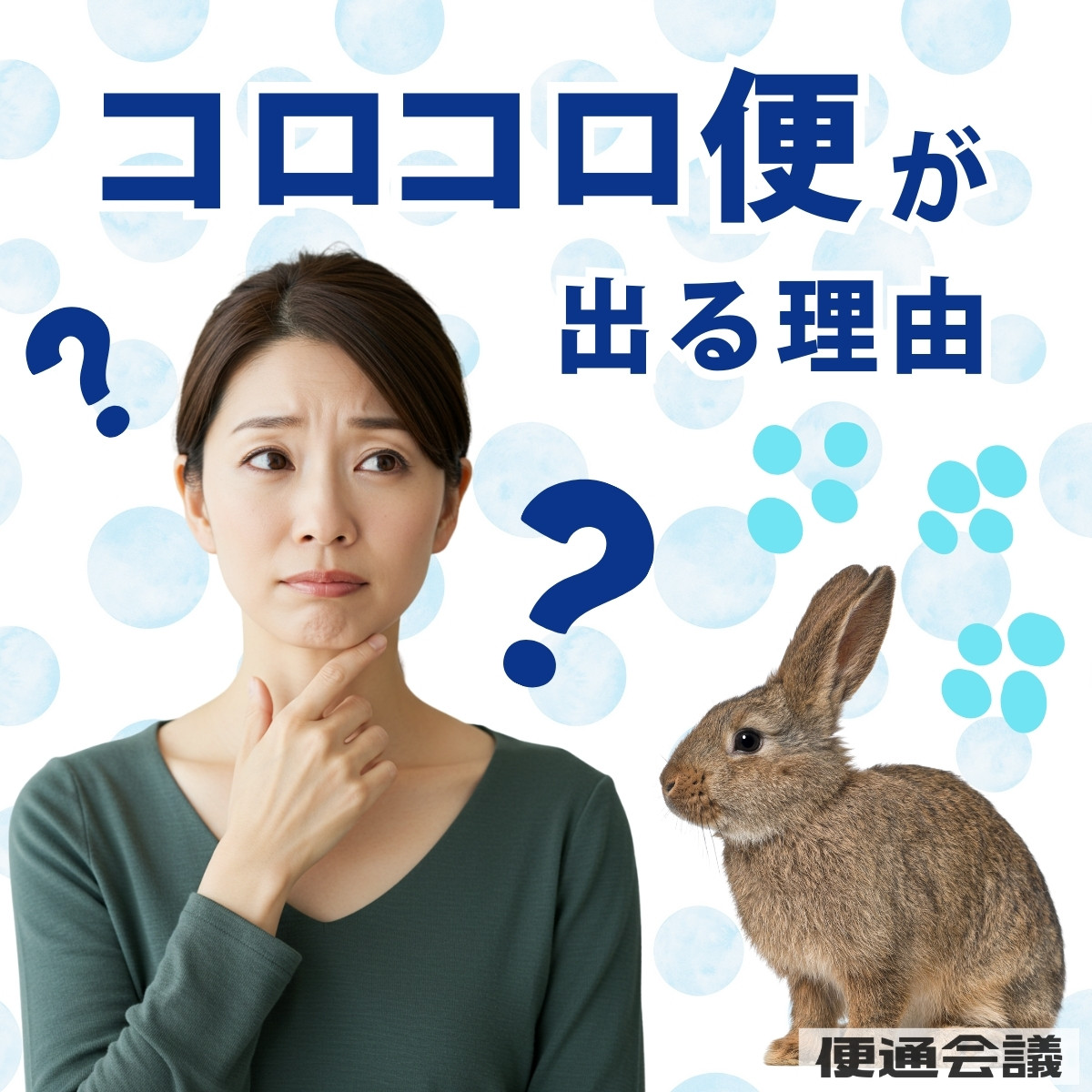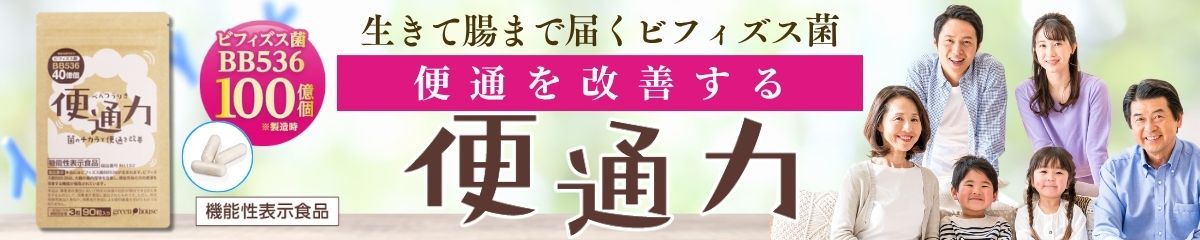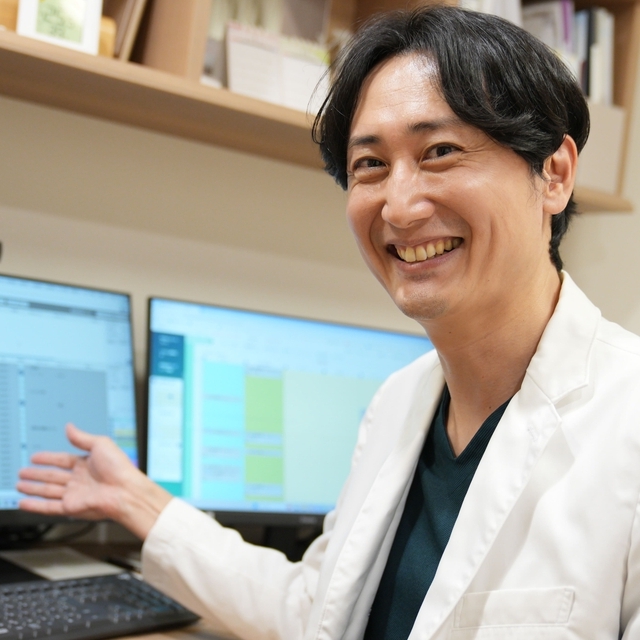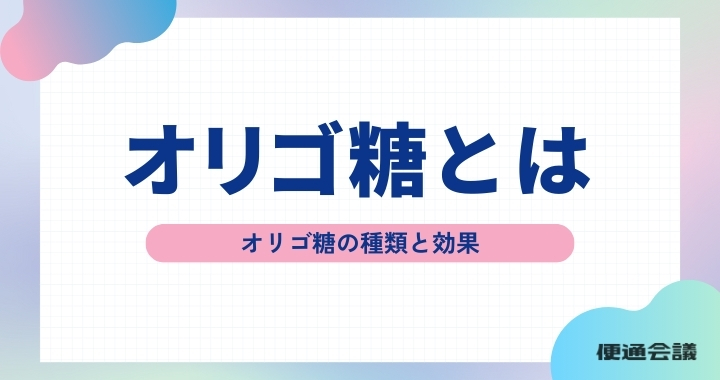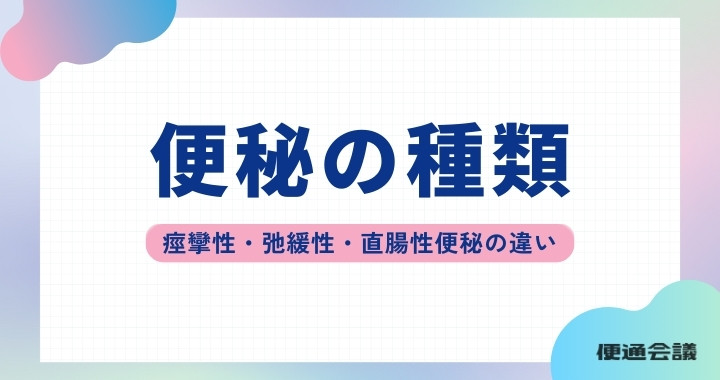最終更新日:2025.12.05
【脂肪便とは?】白い便・浮く便が続く原因と対策

「白い便」「油っぽい」「下痢と白い油が続く」…その便は脂肪便かもしれません。
これは膵臓や胆のうのサインであると同時に、腸内環境の緊急事態を招き、便秘を急速に悪化させる悪循環の始まりです。
本記事では、脂肪便の原因と「腸内環境の悪化を食い止める根本改善法」を徹底解説します。
深刻な腸のトラブルが起きる前に、脂肪便や油っぽい下痢に対して適切な対策を始めましょう。
目次
脂肪便(白い便・白いうんち)とは?便秘との関係
脂肪便とは、便の中に通常より多くの脂肪が混ざった状態のことです。
健康な便は茶色くて形が整っていますが、脂肪便は白っぽい見た目で油分が多く、水に浮くことも珍しくありません。
何らかの理由で、食事から摂取した脂肪分を腸でうまく処理できない時に、便の中に脂肪が多く含まれた状態で排出されます。
脂肪便の特徴
- 白っぽく透明感があり、油分が多いためテカリや光沢が見られる
- 形が崩れやすく、水に浮くことも多い
- 粘り気やまとまりが少なくベタつくことがある
このような形状の変化は、脂肪の消化・吸収不良が原因であり、放置すると腸内環境の悪化や便秘を招く恐れがあります。

自分の便は大丈夫?脂肪便セルフチェックリスト
「便秘が続く」「なんとなくお腹の調子が悪い」。そんな時は、まず毎日の便の状態に注目してみましょう。
脂肪便の特徴
◆これって脂肪便のサイン?簡易チェックリスト
脂肪便には、特有のサインがあります。
以下のチェックリストにあてはまる項目がないか、まずは確認してみましょう。
- 便が白っぽく、油膜が張ったようにテカテカしている
- トイレの水面に便が浮くことが多い
- 排便後、お尻に油っぽさが残る感覚がある
- 便の量が少ないのにべたつきや不快感が強い
特に、「白いうんち」「テカテカした便」「便が浮く」。これらの症状は、脂肪便の典型的なサインです。
脂肪便が続く原因は何?見逃せないサイン
脂肪は小腸で消化・吸収されますが、次のような原因でこの機能が低下すると、脂肪便が生じます。
原因1. 膵臓酵素の不足で脂肪が分解されない
「白い便」や「油っぽい便」が続く背景には、膵臓内での酵素不足が関係している可能性があります。
◆膵臓の役割とリパーゼとは?
膵臓は、食べ物の消化を助ける重要な臓器です。特に脂肪を分解するリパーゼという酵素を分泌し、脂肪を小さな分子にして小腸で吸収できるようにします。
ところが、このリパーゼが不足すると脂肪がうまく消化されず、そのまま便と一緒に排出されてしまいます。これが「脂肪便」の主な正体です。

働き盛りの世代は「膵臓の働き」が落ちていることに気づかず、脂肪便や便秘を長期間放置してしまう方も少なくありません。
日頃から便の状態を観察し、白っぽい便や油っぽい下痢が続くなどの異変がある場合は、早めにケアを始めましょう。
原因2. 腸の吸収障害で脂肪が吸収されにくくなる
脂肪を消化しても、小腸粘膜の炎症や腸内フローラの乱れによって吸収力が低下すると脂肪便が起こります。
特に、悪玉菌の増加は腸の粘膜を刺激し、吸収効率の低下を招き、脂肪便を促進する要因の一つです。
白い便や油っぽい脂肪便が出たら!腸内環境を整えて脂肪便の悩みを解決に導く方法とは…>>詳しい解説を見る
原因3. 脂質の多い食生活と肝臓・胆のうの不調
高脂質の食事や、脂肪の乳化を助ける胆汁の分泌不足(肝臓・胆のうの不調)も脂肪便が出る原因の一つです。
このような食事習慣は、腸内環境のバランスを乱すリスクを高めます。
◆飽和脂肪酸・トランス脂肪酸に要注意!
現代の食生活で増えている「脂質中心型の食事」は、腸にさまざまな負担を与えます。特に以下の脂肪は注意が必要です。

また、欧米型の食生活も腸内環境を悪化させ、脂肪便や油っぽい下痢を誘発します。
以下に挙げる食習慣は「腸の脂肪処理能力」を超えやすく、脂肪がそのまま便に出てしまう状態を引き起こします。
- 外食・ファストフードが多い
- 揚げ物・加工肉が好き
- 野菜や発酵食品が少ない
- 糖質制限をしていて、代わりに脂肪を多く摂っている
脂肪便が便秘を悪化させる理由とは?
脂肪便はただの「白い便」ではありません。
実は、腸内環境を乱し、便秘をどんどん悪化させてしまう原因にもなるのです。
その理由について、解説します。
原因①:未消化のままになった脂肪が「悪玉菌のエサ」になる
脂肪便には、消化されずに残った脂肪分が多く含まれています。この未消化の脂肪が腸にとどまることで、悪玉菌が繁殖しやすくなります。
▶ 悪玉菌が増えると…
- 腸内で有害物質を発生させる
- 善玉菌とのバランスが崩れ、腸内環境が悪化
- 便の水分が奪われ、硬く・出にくい便になる
結果、便秘が慢性化しやすい土壌ができてしまいます。
原因②:腸の動き(蠕動運動)を鈍らせる
脂肪分が腸の粘膜に与える刺激によって、腸の「蠕動運動」が低下することがあります。
▶ 蠕動運動が弱まると…
- 便の移動が遅くなる
- 便が腸内に長くとどまり、水分が吸収されすぎてカチカチに
- 排便のリズムが乱れ、さらに便秘が深刻に
放置はNG!脂肪便→腸内トラブル→便秘の悪循環に
脂肪便は、「腸内環境の乱れ」と「便秘悪化」の両方を引き起こす大きな要因です。
一度、腸内環境が乱れると自然に回復しづらく、便秘を繰り返す悪循環に陥ります。
だからこそ、脂肪便のサインを見逃さず、早めに対策することが大切なのです。

脂肪便の改善は腸内環境を整えることから!ビフィズス菌BB536+オリゴ糖のシンバイオティクスで便通をサポート>>詳しく見る
脂肪便・便秘を自然に改善するための具体的な方法
脂肪便や便秘の悩みは、生活習慣や食事のちょっとした見直しで改善が期待できます。
ここでは、無理なく続けられる食生活のポイントや生活習慣の改善方法、さらに効果的なサプリメント活用法まで、便秘薬に頼らず自然にスッキリするための具体的なステップをわかりやすく紹介します。
毎日の習慣で腸内を整えて、快適な便通環境を取り戻しましょう。
1. 食生活の見直し
脂肪便の改善には、脂肪の摂取量を調整しつつ、腸内環境を整えることが大切です。
- 脂質の質と量を見直す
- 食物繊維を増やす
- 発酵食品やオリゴ糖で善玉菌を増やす
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を減らし、良質な脂肪(オメガ3脂肪酸など)を適量摂るように心がけましょう。
水溶性・不溶性繊維をバランスよく摂取することで、便のかさを増やし腸の動きを促進します。
ヨーグルト、納豆、キムチなどの発酵食品と、オリゴ糖を含む食品は腸内環境改善に効果的です。
2. 生活習慣の改善
食事だけでなく、毎日の生活習慣も腸や便通に大きく影響します。
特に運動・睡眠・ストレスケアは、腸の働きを整えるうえで欠かせないポイントです。
- 適度な運動で腸の蠕動運動を活性化する
- 規則正しい睡眠をとり、体内リズムを整える
- ストレスケアを心がけ、腸の神経機能を安定させる
3. サプリメント・専門的サポートの活用
食事・生活改善と並行し、腸内環境をダイレクトにサポートする成分配合のサプリメント活用は、便秘の根本改善の近道です。
特に、ビフィズス菌BB536とオリゴ糖を同時に摂取することで、未消化の脂肪によって増えすぎた悪玉菌を抑え、腸の蠕動運動をサポートする効果が期待できます。

まとめ|脂肪便を改善して毎日スッキリ快調に!
脂肪便(白い便・白いうんち)は、便秘を悪化させる重要なサインです。
放置せず、便の状態を観察しながら生活習慣や食事を見直すことが、健康な腸への第一歩になります。
特に、脂質の質や量の調整、食物繊維や発酵食品の摂取は便通改善に効果的です。

さらに、脂肪の消化吸収をサポートし、腸内環境を整えるサプリメントをうまく取り入れることで、薬に頼らず、自然なスッキリ感を実感できる人も少なくありません。
まずはご自身の便の状態をチェックして、この記事で紹介した対策をぜひ試してみてください。
“腸からの声”に耳を傾けて、今日から一歩ずつ、快適な毎日を。
よくある質問【Q&A】
- 脂肪便とはどんな便ですか?
- 脂肪便が続く原因は何ですか?
- 脂肪便を改善するにはどうすればいいですか?
- 脂肪便は便秘だけでなく、下痢を伴うことはありますか?
脂肪便は、脂質を多く含むために便が油っぽく、ベタベタしたり、便器に浮いたりする特徴があります。色は淡黄色〜灰白色になることが多く、臭いも強い傾向があります。
主な原因は「脂肪の消化・吸収不良」です。膵臓や胆のうの機能低下、腸内環境の乱れ、脂質の多い食事などが関係します。慢性的な場合は病気のサインの可能性もあります。
食事の見直しに加え、腸内環境を整えることが大切です。善玉菌や水溶性食物繊維、消化を助ける成分を意識的に摂ることが有効です。
はい、脂肪便は下痢を伴うことがよくあります。未消化の脂肪は、大腸内で水分を吸収しにくくする作用や、腸内細菌によって刺激性の物質に変化することで、白い油状の下痢を引き起こすことがあります。慢性的な場合は、膵臓や胆のうの機能低下、または腸の吸収不良が疑われます。
脂肪便のお悩みにビフィズス菌でアプローチ!
食生活の見直しが難しい方にも
ビフィズス菌BB536とオリゴ糖で内側からサポート。
ダイレクトにアプローチできるビフィズス菌習慣、始めませんか?
【出典・参考資料】
※柳町幸, 丹藤雄介, and 中村光男. "間接熱量計を用いた慢性膵炎患者の栄養管理." 静脈経腸栄養 27.6 (2012):337-1342.
※日本消化器病学会 慢性膵炎診療ガイドライン 2021(改訂第3版)
※Nakamura, Y., Suzuki, S., Murakami, S., Nishimoto, Y., Higashi, K., Watarai, N., Umetsu, J., Ishii, C., Ito, Y., Mori, Y., Kohno, M., Yamada, T., & Fukuda, S. (2022). Integrated gut microbiome and metabolome analyses identified fecal biomarkers for bowel movement regulation by Bifidobacterium longum BB536 supplementation: A RCT. Computational and Structural Biotechnology Journal, 20, 5847–5858.

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。