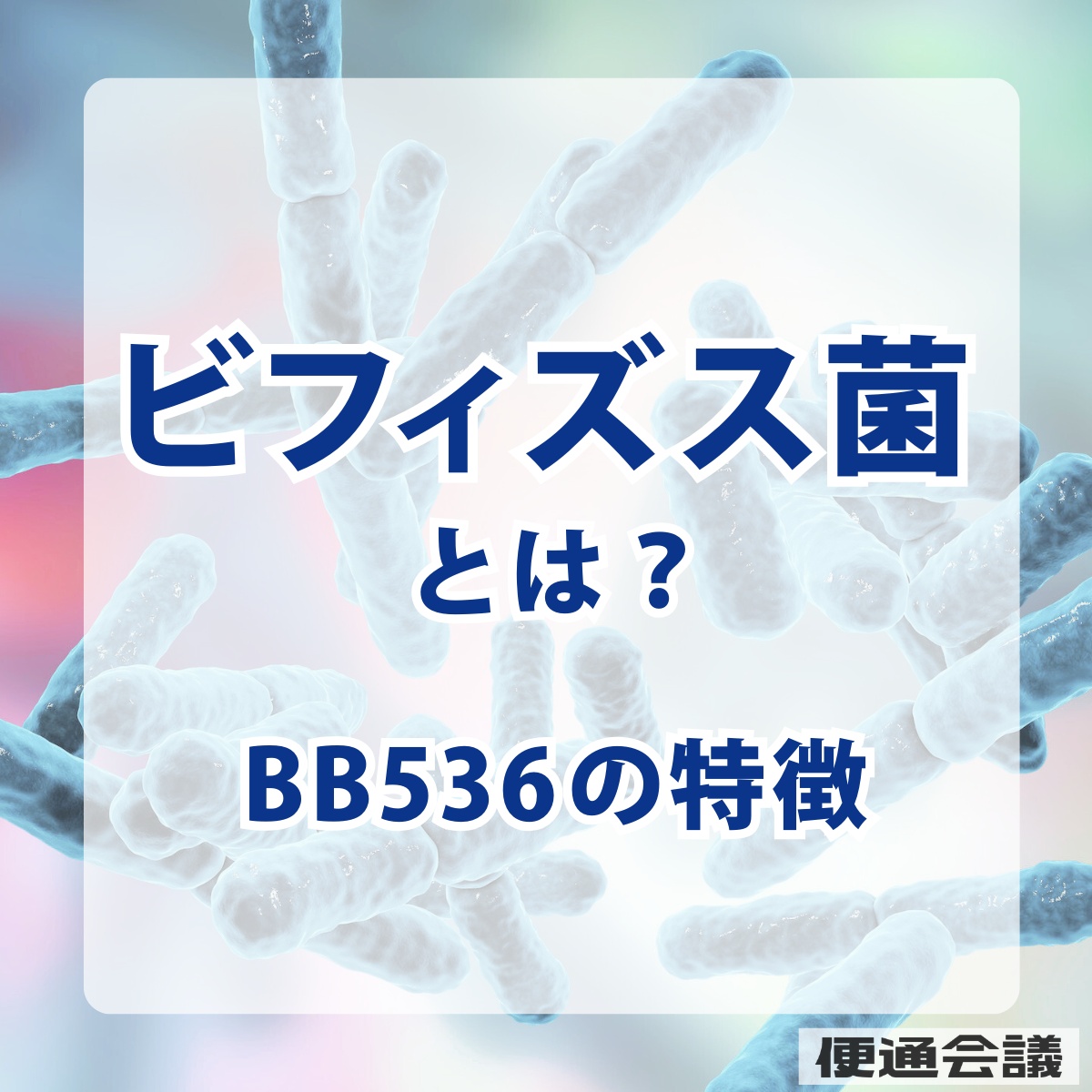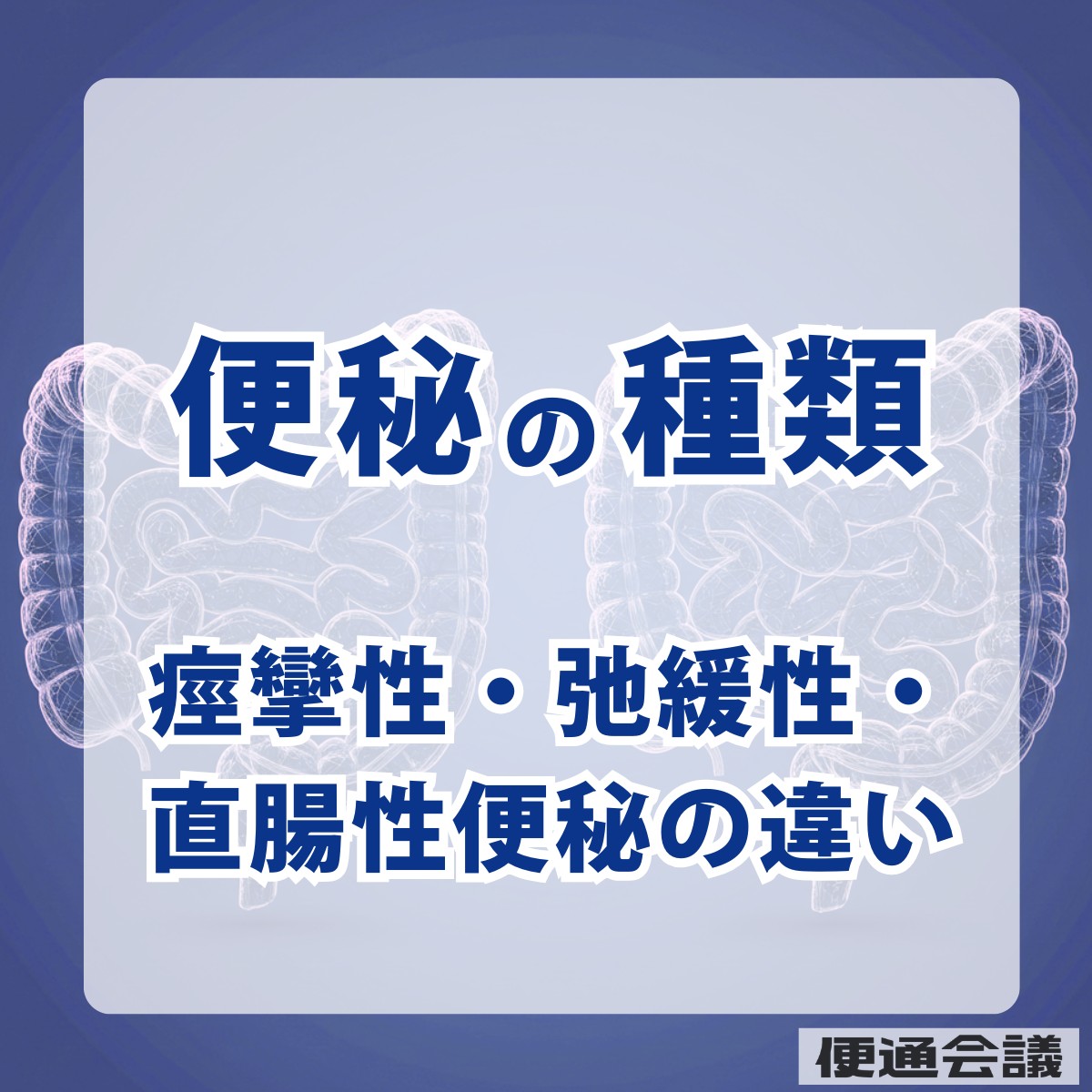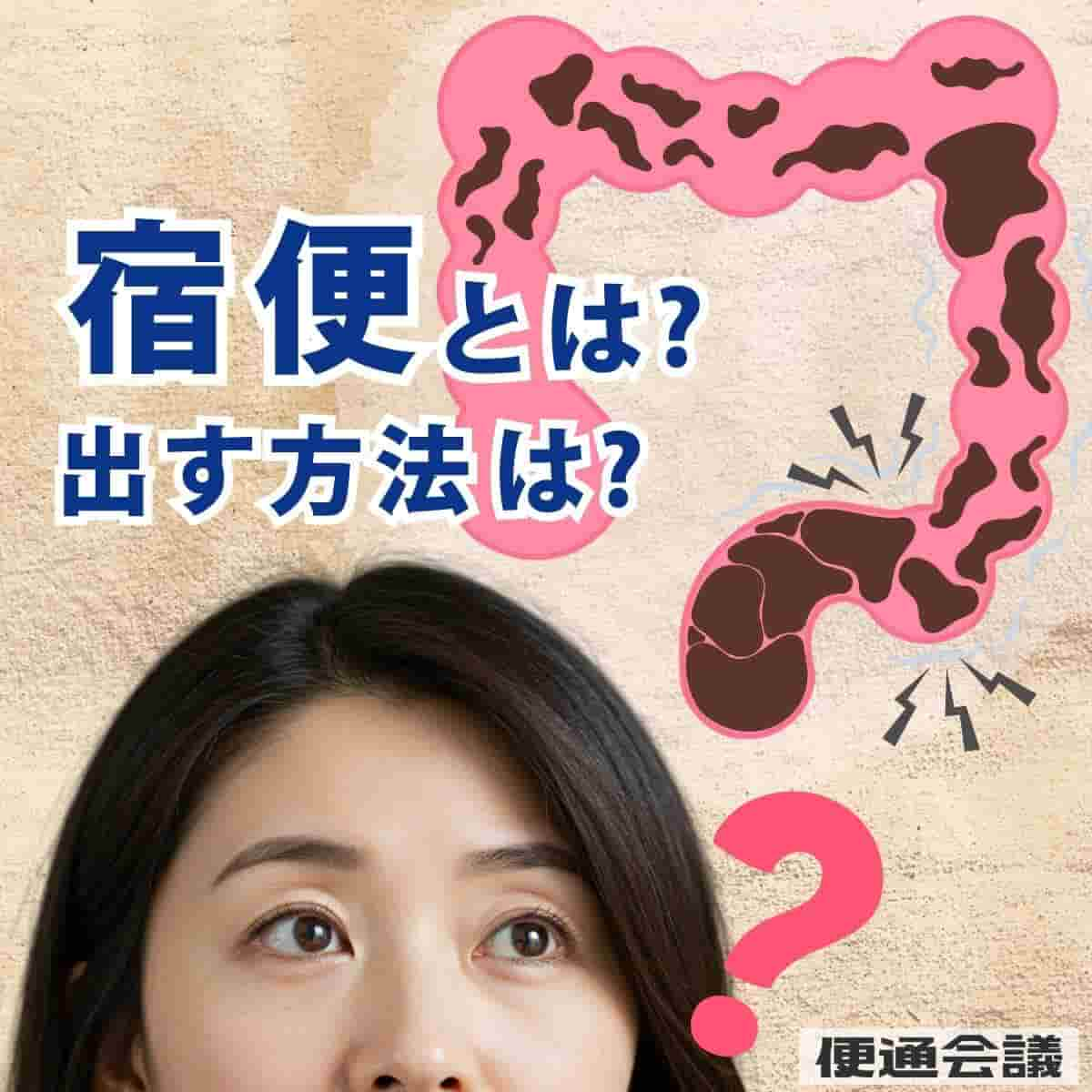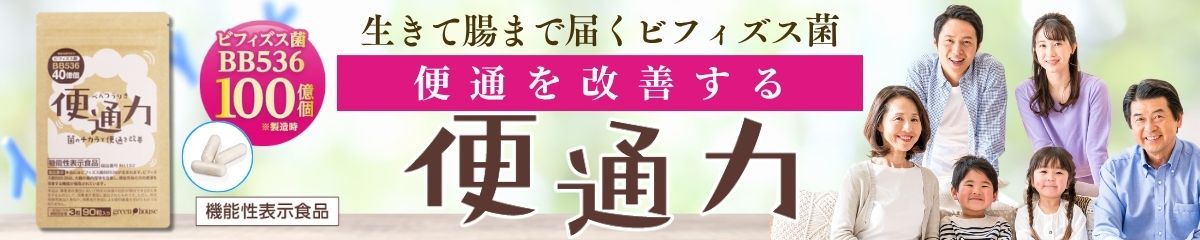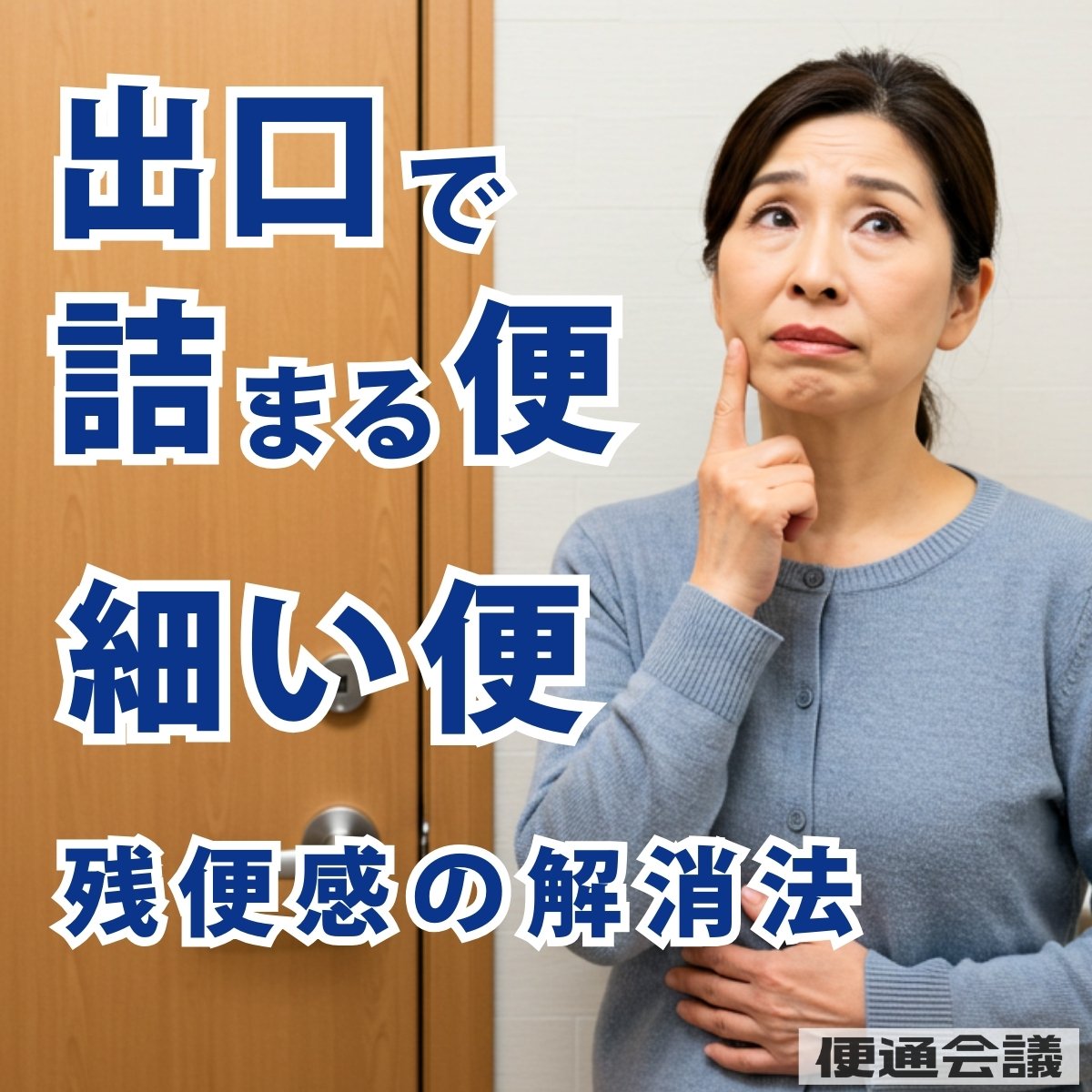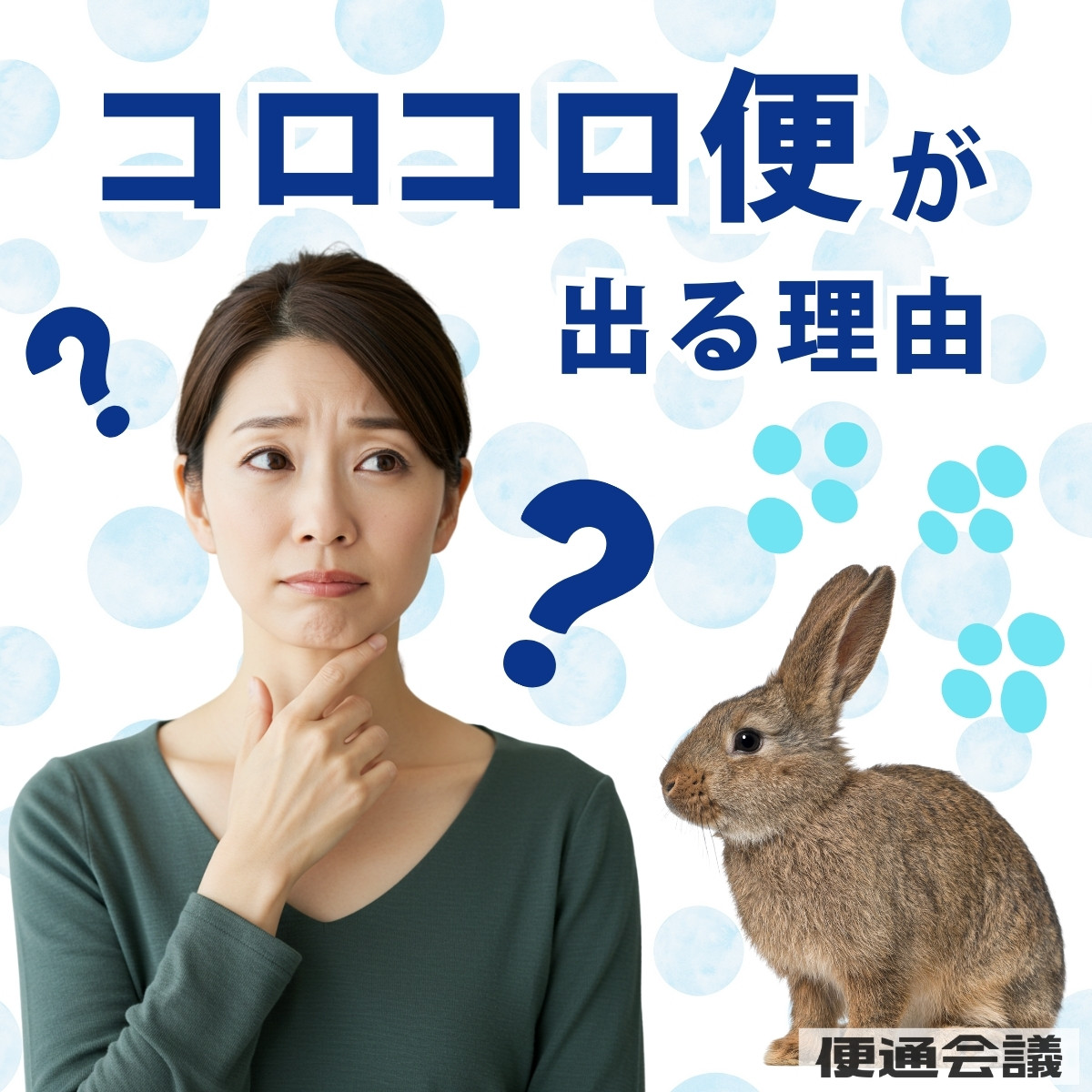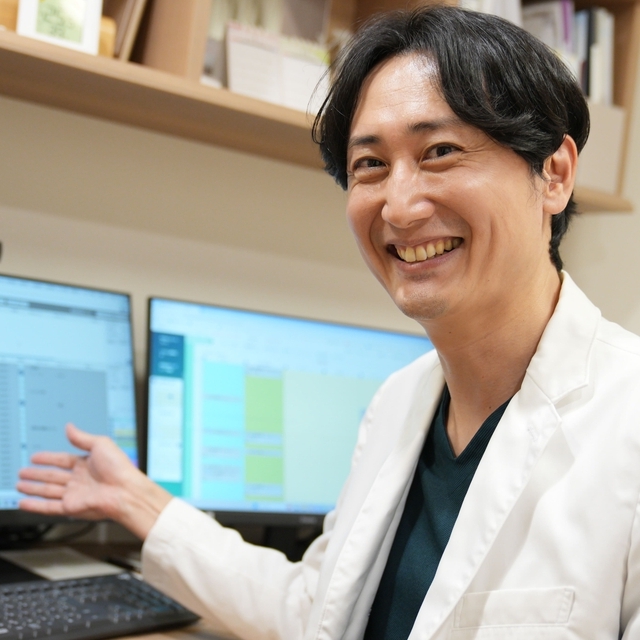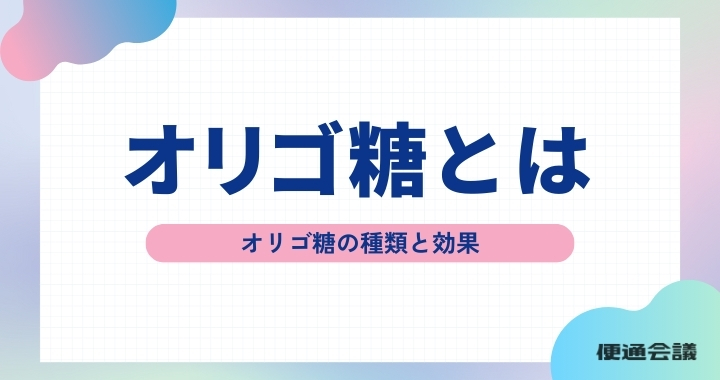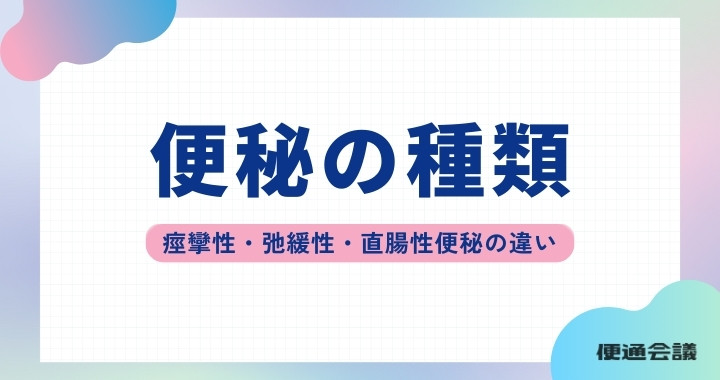最終更新日:2025.12.5
腸脳相関とは?腸内環境とメンタルの深い関係

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど多くの神経細胞を持ち、脳からの指令を待たずに独立して動くことができるほど複雑な神経ネットワークを備えています。
この脳と腸の密接なつながりは「腸脳相関」と呼ばれ、腸内環境の乱れがメンタルの不調や便秘などの体調トラブルを引き起こすことが、近年の研究によって明らかになってきました。
本記事では、腸脳相関の基本メカニズムから、ストレスが腸に与える影響、そして「幸せホルモン」セロトニンとの関係まで、分かりやすく解説します。
目次
腸内環境の悪化でメンタルに悪影響?腸内細菌と心の関係
「腸脳相関」とは、「脳と腸が神経系・ホルモン・免疫系を介して双方向に影響し合う仕組み」を指します。
腸には1億個以上の神経細胞(腸内神経系)が存在し、一部の消化運動は脳からの指令を待たずに独立して働くことが可能です。
これは、腸が単なる消化器官ではなく、ストレス反応や感情調整などに関わる可能性を示しています。
近年の研究では、不安やうつ症状を持つ人の腸内環境に特徴的な菌バランスの違いが観察されることが報告されています。

うつ病と腸内細菌バランスについての調査
例えば、うつ病患者を対象にした研究では、健常者に比べてビフィズス菌が有意に少なく、乳酸菌も少ない傾向があると報告されています。
ただし、研究間で結果が一貫しているわけではないため、因果関係を直接示すものではありません。
腸内細菌とオキシトシン産生量の関係
さらに、ある動物実験では、腸内細菌と「オキシトシン」(ポジティブなスキンシップなどで分泌されるホルモン)との相互作用が示唆されました。
腸内細菌がオキシトシン産生に影響を与え、社会的行動やストレス応答を調整する可能性があると考えられています。
これらの知見から、腸内細菌叢(腸内フローラ)とメンタルの状態には一定の関連があると推測されます。
ただし、研究はまだ発展途上であり、「どの菌がどのように作用するか」「誰に効果があるのか」といった点は明確ではありません。
最近の研究では、プロバイオティクスなど腸内細菌を調整する介入がうつ症状を軽減する可能性が示されていますが、その効果は小さく、個人差も大きいため、今後さらなる研究が必要とされています。
ストレスと腸脳相関の深い関係 | 心と腸をつなぐメカニズム
ストレスも、腸脳相関を乱す大きな要因の一つです。
心理的ストレスが強くかかると、HPA(視床下部-下垂体-副腎)軸が活性化し、副腎皮質ホルモンの一種である「コルチゾール」が分泌されます。
コルチゾールの特徴
肝臓での糖の新生や筋肉でのタンパク質代謝など、重要な役割を果たすホルモン。
ストレスを感じると分泌量が増えることから「ストレスホルモン」とも呼ばれ、体を緊張状態に保ち、危険にすぐ対応できるように備えます。
ストレス負荷がかかった状態が続いて分泌量が多い状態が続くと、免疫力低下や血圧上昇、不眠、脂肪がつきやすくなるなど様々な悪影響が表れます。

コルチゾールが腸に及ぼす影響
消化管に関しては、慢性的ストレスによって腸の蠕動運動が抑制され、便秘や下痢、腹痛、ガスの増加など、多様な消化器症状が現れる可能性があります。
特に、腸の一部が過剰に収縮して便の通過が妨げられ、硬くコロコロした便が出やすくなるタイプの便秘は、従来「痙攣性便秘」と呼ばれてきました。
現在の医学分類では過敏性腸症候群(便秘型:IBS-C)や機能性便秘に含まれる症状と考えられています。
研究では、ストレスが副交感神経(消化を促進する迷走神経)の働きを低下させ、腸のリズムを乱す可能性が示唆されています。
このことから、便秘や下痢などの症状は単なる「腸のトラブル」にとどまらず、精神状態と腸の健康が密接に関わっていることが分かります。
また、近年の研究では、オキシトシンによってコルチゾール分泌が抑制される可能性が示されています。
腸内環境が乱れて悪玉菌が増加!メンタルへの影響も?
腸内には数百種類以上の細菌が存在し、主に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」という3種類に分類されます。これらの菌は、菌種ごとに小さなコロニー(集団)を作って共生しています。
一般的に、理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」とされ、これが崩れると腸内環境は不安定になります。

腸内環境が不安定になるとpHが変化し、悪玉菌が増殖。アンモニアや硫化水素などの有害物質が発生して腸の粘膜を刺激し、炎症を起こします。
結果として、免疫力低下や全身の倦怠感、肌荒れなど多様な不調につながる可能性が示唆されています。
ストレスが蓄積すると腸内環境が悪くなる理由
ストレスがたまると交感神経が優位になり、副交感神経の働きである消化吸収機能が低下します。
すると、腸内に悪玉菌が増加。腸内の神経伝達物質のバランスにも影響を与え、抑うつ状態やイライラ感など、メンタル面での不安定さを助長すると考えられています。
幸せホルモン「セロトニン」と腸の関係
セロトニンは感情を安定させ、幸福感や安心感をもたらす神経伝達物質で、一般に「幸せホルモン」と呼ばれます。体内のセロトニンの約90%以上は腸でつくられており、腸はセロトニン産生において非常に重要な役割を担っています。
腸内環境が乱れるとセロトニン分泌に影響がある?
腸内細菌は、セロトニンの材料となる必須アミノ酸トリプトファンの代謝に関わり、その利用経路を調整することが分かっています。
腸内環境が乱れると、この代謝バランスに影響が生じ、セロトニン系の働きに変化をもたらす可能性があります。
その結果、不安感や気分の落ち込み、睡眠の乱れなどをもたらすことが研究で示唆されました。

さらに近年の研究では、プロバイオティクスや特定の乳酸菌を摂取することで腸内環境を改善し、セロトニン代謝や気分の安定に良い影響を与える可能性が報告されています。
こうした効果はまだ研究段階であり、すべての人に当てはまるとは限りません。
しかし、腸内環境を整えることで心の健康やストレス耐性に良い影響を与える可能性が期待されています。
腸脳相関を整える生活習慣!セロトニン分泌量を増やす方法
腸脳相関を健全に保つためには、日常生活の習慣を少しずつ見直すことが重要です。
腸内環境を整えることで、便通の改善だけでなく、セロトニンの分泌をサポートし、気分の安定やストレス耐性の向上にもつながります。
ここでは、腸脳相関を整える具体的な生活習慣を紹介します。
1. 食生活の改善
腸内環境のバランスは、日々の食事によって大きく左右されます。善玉菌を増やし、腸内細菌の多様性を保つことが、腸脳相関を整える第一歩です。
■ 発酵食品で善玉菌を補給
ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌が含まれています。これらの善玉菌は腸内で短鎖脂肪酸を生成し、腸の蠕動運動を促すほか、腸内の免疫バランスを整える役割も果たします。自分に合う菌を見つけるのは難しい場合、サプリメントの活用も選択肢の一つです。
■ 食物繊維で腸内細菌のエサを供給
野菜、海藻、きのこ類などに含まれる水溶性・不溶性食物繊維は腸内細菌の重要な栄養源です。食物繊維を十分に摂ることで、善玉菌の活動が活発になり、便の量や質が改善されます。
■ オメガ3脂肪酸で腸粘膜を保護
青魚(サバ、イワシ、サンマなど)や亜麻仁油に含まれるオメガ3脂肪酸は、腸の炎症を抑える効果があります。腸粘膜の健康が保たれることで、腸内環境が安定し、腸脳相関の働きもサポートされます。

2. 適度な運動
運動は腸の蠕動運動を促進するだけでなく、自律神経のバランスを整える効果があります。腸脳相関を健全に保つためには、日常的に軽い運動を取り入れることが大切です。
■ ウォーキングやストレッチ
歩行や軽いストレッチは腸の蠕動運動を活発にし、便通をスムーズにします。特に朝のウォーキングは体内リズムを整え、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
■ 深呼吸を取り入れた軽運動
ヨガや呼吸法を取り入れると、副交感神経が優位になり、腸の働きが安定します。ストレスで交感神経が過剰になりがちな方におすすめです。

3. 睡眠とストレス管理
睡眠不足や慢性的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、腸脳相関に悪影響を与えます。質の高い睡眠とリラックス習慣を意識することが、腸内環境の安定につながります。
■ 質の高い睡眠を確保する
睡眠中に副交感神経が優位になることで腸の蠕動運動が促進されます。寝る前のスマホやカフェインを控えるなど、生活リズムを整える工夫が重要です。
■ マインドフルネスやヨガでリラックス
呼吸を意識したマインドフルネスやヨガは、ストレスホルモンの分泌を抑え、自律神経を安定させます。これにより、腸内細菌のバランスが整い、腸脳相関の働きがスムーズになります。

まとめ | 腸脳相関を意識した毎日で健康寿命を延ばそう
腸脳相関は、腸と脳が双方向に影響し合う重要なメカニズムです。腸内環境を整えることで、便通の改善だけでなく、メンタルの安定にも好影響が期待できます。
日々の食事や運動、睡眠の質を整え、小さな一歩から腸脳相関を意識した腸活を始めてみましょう。
特に、腸内細菌をサポートするサプリメントは、忙しい人にも続けやすい方法です。
「腸を整えることが心の健康につながる」という新常識を、今日から取り入れてみませんか?
【参考資料・出典】
※山川香織. "急性ストレスが認知・感情に及ぼす影響―コルチゾールを中心として―." Psychoneuroendocrinology 38: 1467-1475.

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。