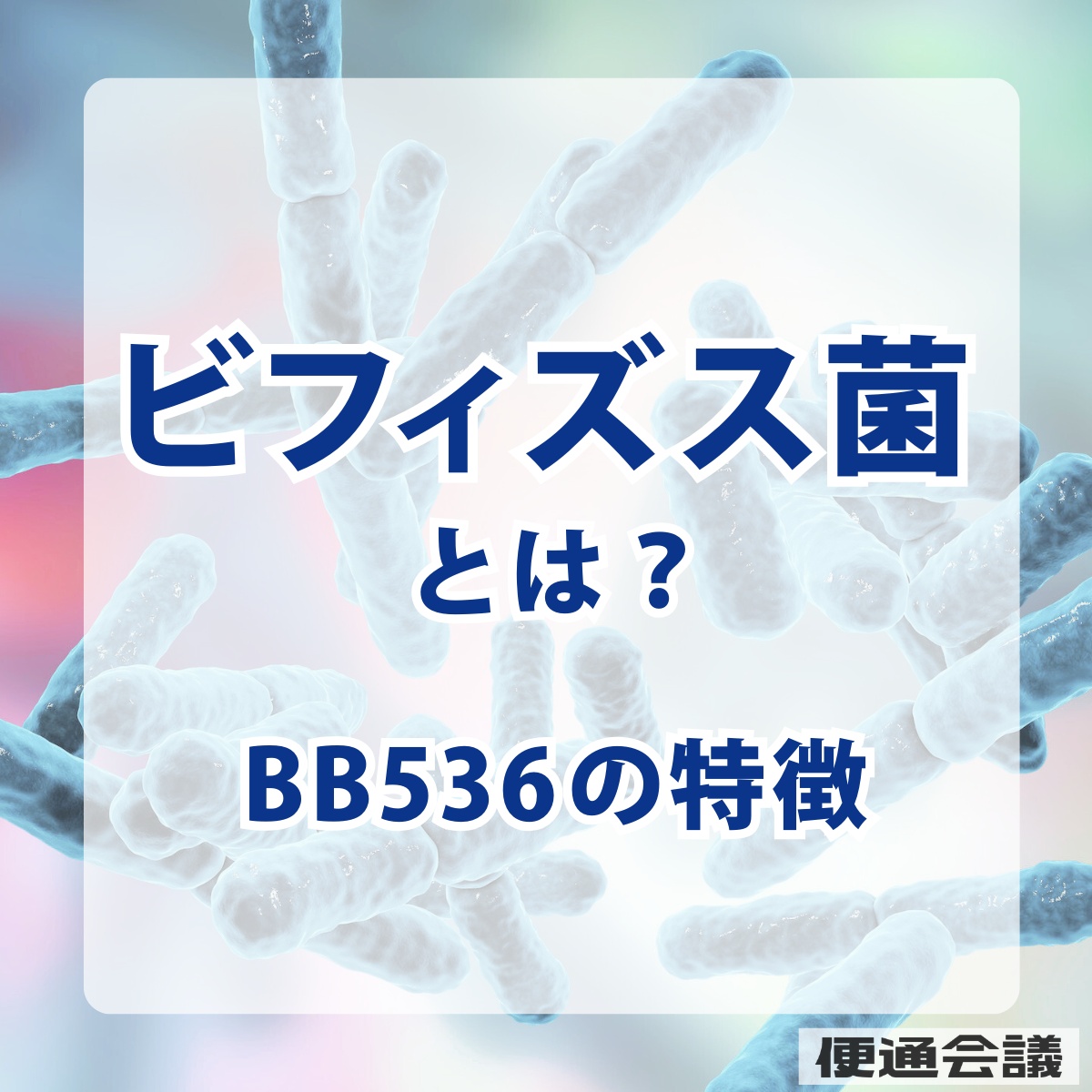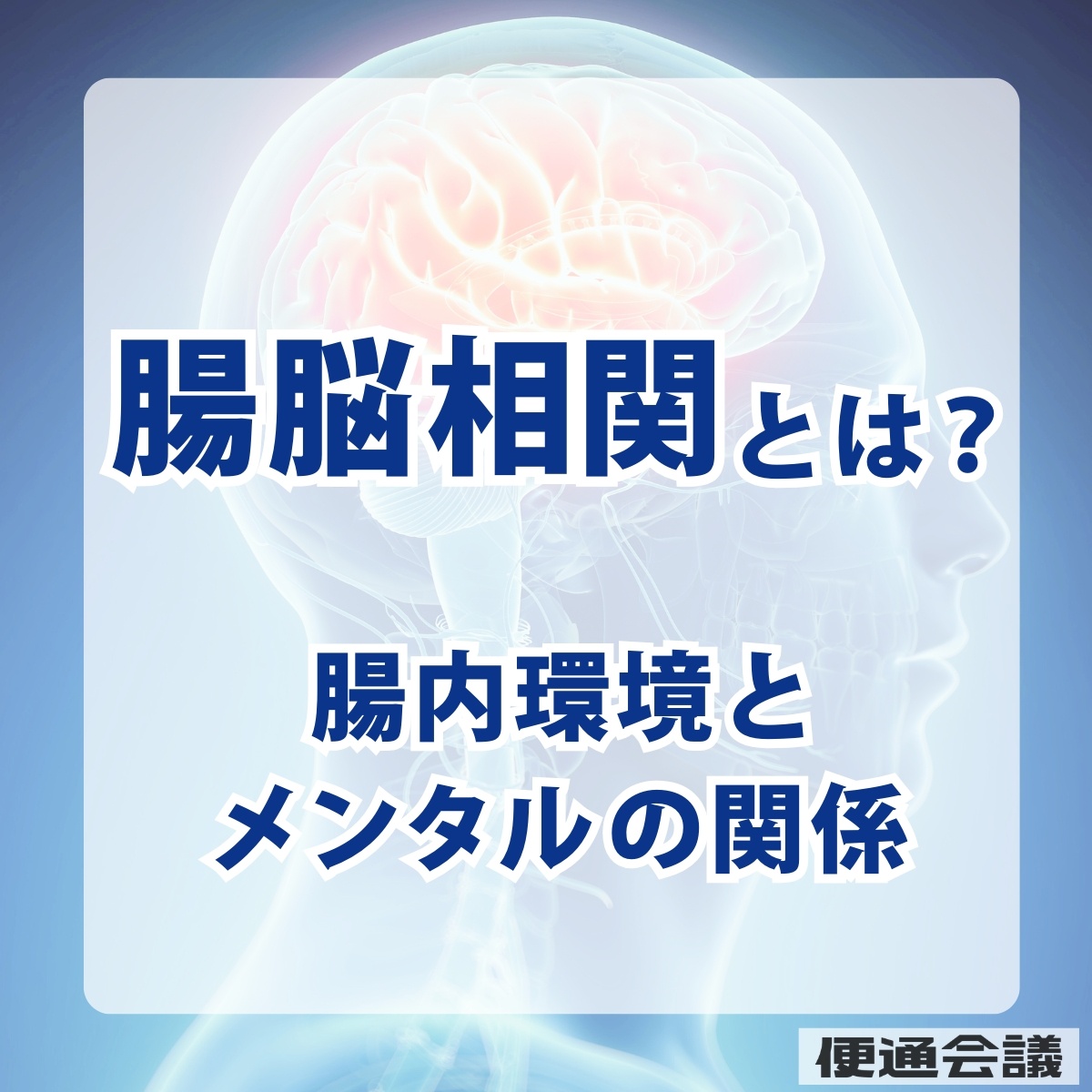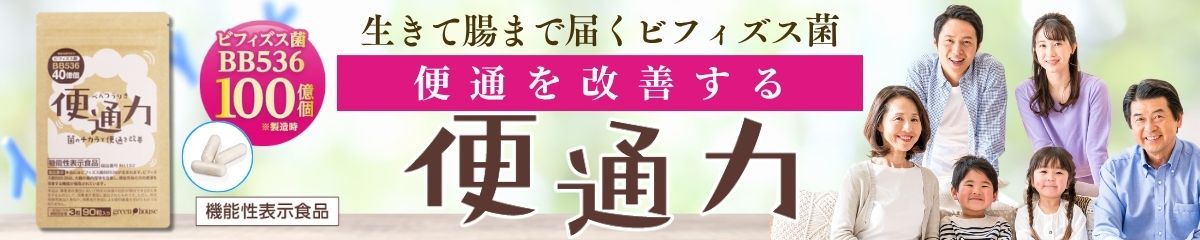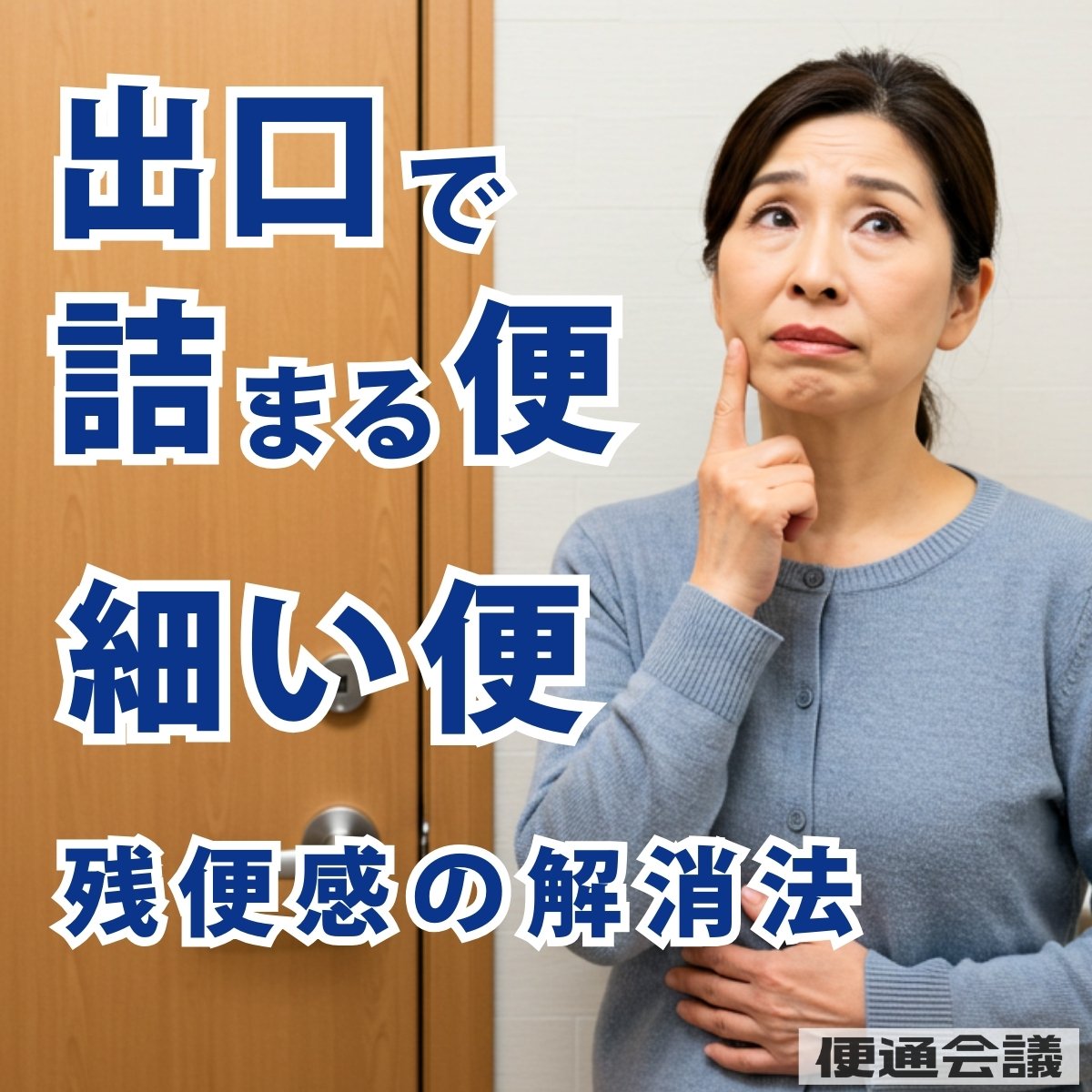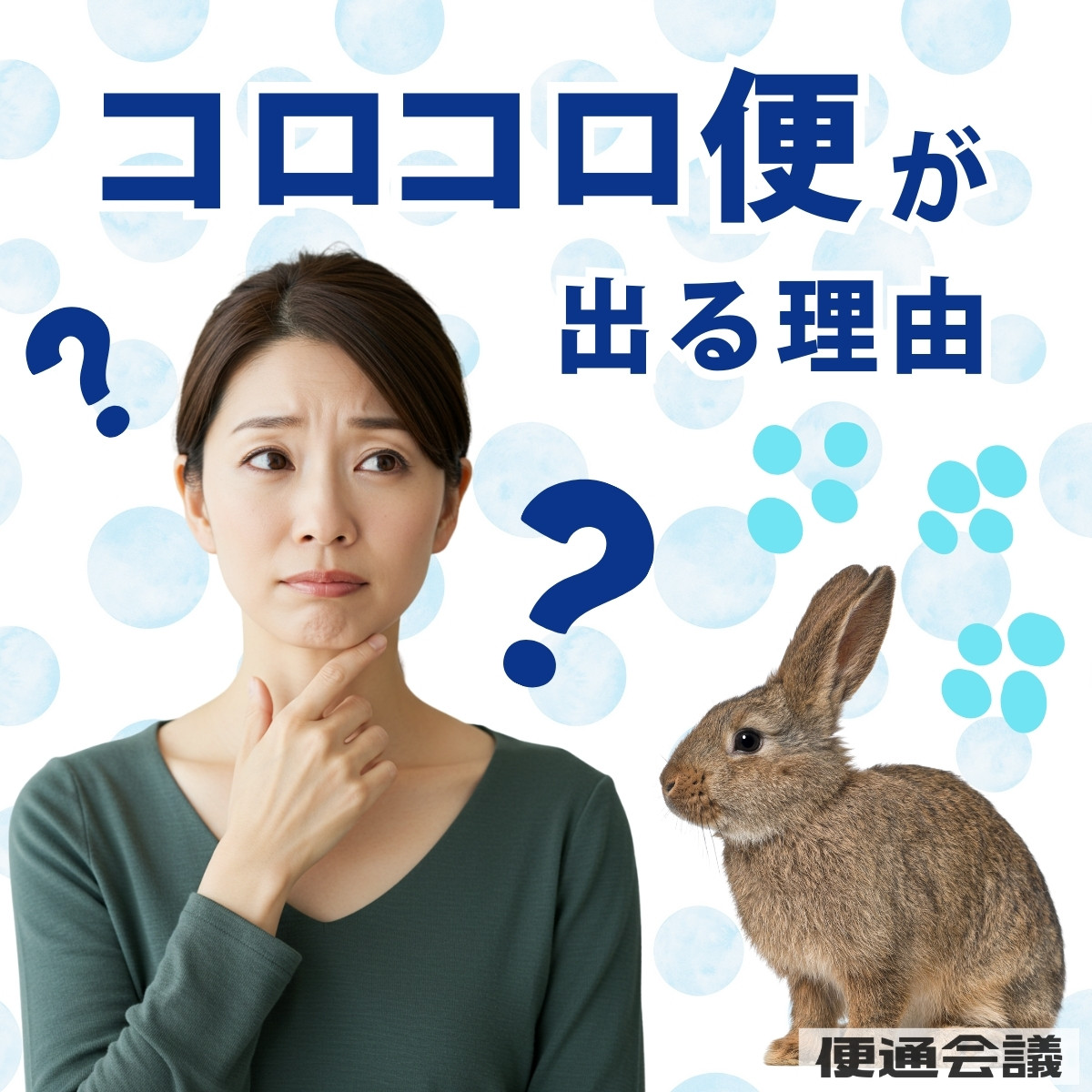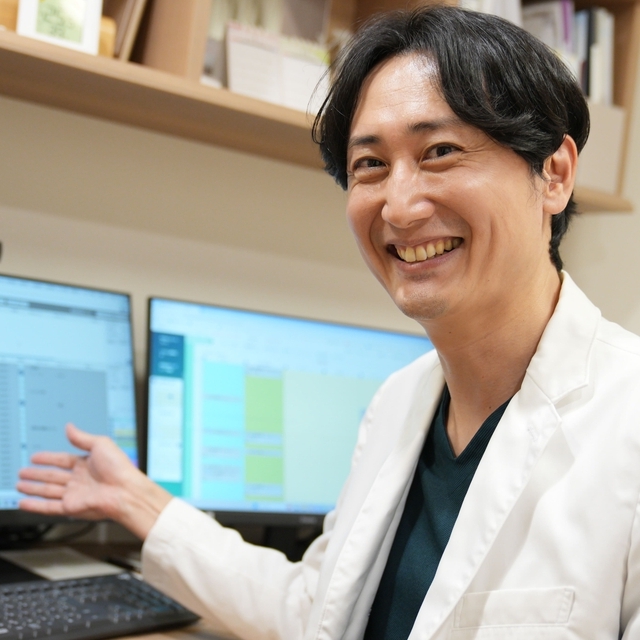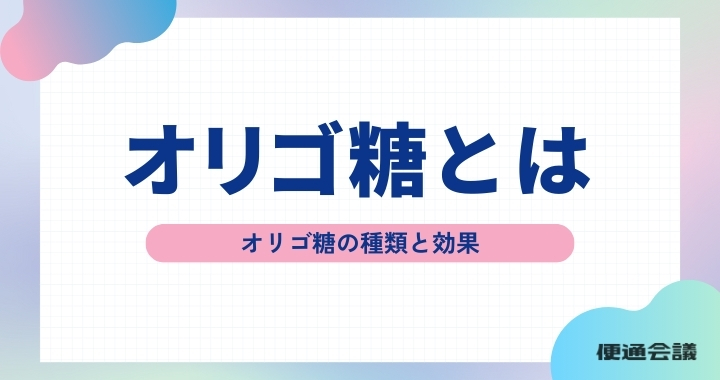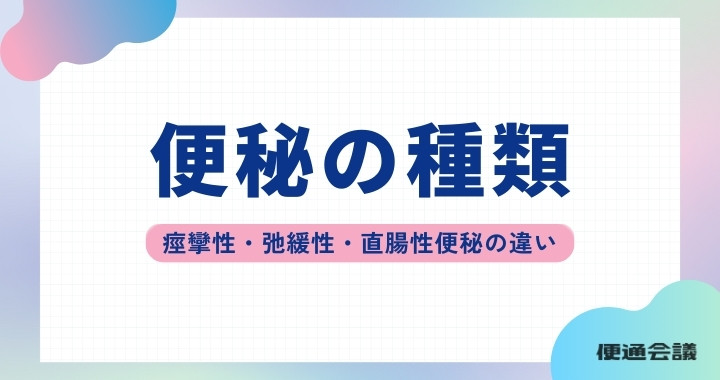最終更新日:2025.12.5
オリゴ糖の種類と効果を徹底解説|ビフィズス菌を増やすプレバイオティクスの力

腸内環境を整えるためには、ビフィズス菌などの善玉菌をしっかり増やすことが大切です。そこで注目されているのが「オリゴ糖」。
オリゴ糖は腸まで届いてビフィズス菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを整える“プレバイオティクス”として知られています。
本記事では、数あるオリゴ糖の中でも、特に腸活効果が期待されるガラクトオリゴ糖・フラクトオリゴ糖・ビートオリゴ糖(ラフィノース)の3種類にフォーカス。
それぞれの特徴や、ビフィズス菌との相乗作用、便通改善につながるメカニズムを専門的に解説します。
「オリゴ糖の種類ごとの違いを知りたい」「効率よくビフィズス菌を増やす方法を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
便秘の原因は「腸内環境の乱れ」にあった
便秘は単に「食物繊維が足りないから起こる」という単純なものではありません。
実際には、100兆個以上の腸内細菌から成る腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが崩れることが便秘の一要因になることが、多くの研究で明らかになっています。
腸内細菌の種類
腸内細菌は大きく分けると、善玉菌(ビフィズス菌など)、悪玉菌(ウェルシュ菌、大腸菌の一部など)、そして日和見菌(善玉菌・悪玉菌の優勢に応じて働きが変わる菌)の3種類に分類されます。
ただし、これは便宜的な分類であり、実際には腸内細菌の働きは腸内環境によって柔軟に変化します。

この中でも、健康的な腸内環境を保つのに重要な役割を果たすのが、善玉菌の代表格・ビフィズス菌です。
ところが、ビフィズス菌はストレスや食生活の乱れ、不規則な生活、加齢など様々な要因によって減少してしまいます。
腸内環境を良好に保つためには、ビフィズス菌を腸にしっかり補充し、そのエサとなる栄養素を与えることがカギとなります。
そこで注目されているのが、オリゴ糖です。
オリゴ糖とは?ビフィズス菌を育てるプレバイオティクス
オリゴ糖は、およそ3〜10個の単糖(グルコース、ガラクトース、フルクトースなど)が特定の結合でつながった低分子の炭水化物で、一般的な糖質に比べて消化されにくい特徴があります。
これは、オリゴ糖の結合がヒトの小腸に存在する消化酵素によってほとんど分解されないためです。
そのため、オリゴ糖は小腸で吸収されずに大腸まで届きます。
プレバイオティクスとは?
腸活への注目が集まる中で、「プレバイオティクス」という言葉を目や耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
プレバイオティクスとは、「宿主微生物によって選択的に利用され、健康効果をもたらす基質」のことを指します。
オリゴ糖の「消化されずに腸内の善玉菌のエサとなる」という特徴こそが、まさに「プレバイオティクス」としての働きなのです。

腸内でオリゴ糖はどう働く?
大腸に到達したオリゴ糖は、主にビフィズス菌などの善玉菌に利用され、その分解過程で短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸など)が産生されます。
これらの短鎖脂肪酸は腸内を適度に酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑制するだけでなく、大腸の蠕動運動を活発にし、便の水分保持を助ける役割も果たします。
その結果、腸内環境のバランスが整い、自然でスムーズな排便が促されるのです。
実際に、フラクトオリゴ糖(FOS)を4週間にわたり摂取したヒト臨床試験では、腸内のビフィズス菌が増加すると同時に、排便回数の増加や腸内通過時間の改善が確認されています。
つまり、オリゴ糖は「腸内環境を整える」だけでなく、「便秘の改善」にも直接役立つ可能性があるのです。
上記の理由から、たとえビフィズス菌を摂っても、エサとなるオリゴ糖が不足していると、腸内環境は悪玉菌優位な状態に偏ります。
そのため、ビフィズス菌を摂取する際には、パートナーであるプレバイオティクスの代表成分であるオリゴ糖が欠かせません。
便通改善に効果的な3種類のオリゴ糖
オリゴ糖には多くの種類がありますが、便通改善とビフィズス菌の増殖促進において特に注目されているのが、ガラクトオリゴ糖(GOS)、フラクトオリゴ糖(FOS)、そしてビートオリゴ糖(ラフィノース)の3種類です。
次は、それぞれの特徴や作用機序を詳しく解説していきます。
ガラクトオリゴ糖(GOS)
ガラクトオリゴ糖は、母乳に含まれるヒト乳糖オリゴ糖と構成の一部に共通性があり、特にビフィズス菌(Bifidobacterium longum/BB536)に選択的に利用されやすいプレバイオティクスとして知られています。
臨床試験で証明された効果
2024年に発表されたローマIV基準に該当する便秘傾向の成人63名を対象とした二重盲検プラセボ対照試験では、4週間のガラクトオリゴ糖(GOS)摂取により、排便回数が有意に増加し便の形状も改善されました。
さらに、腸内のビフィズス菌および乳酸菌の比率が有意に高まったことが報告されています。
副作用はなく、安全性も確認された臨床研究です。
他にも、数多くの研究でガラクトオリゴ糖が腸内環境にもたらす好影響について報告されています。
短鎖脂肪酸(酢酸)の豊富な産生
ガラクトオリゴ糖は酢酸産生を強く促し、発酵中にビフィズス菌や乳酸菌などの有意な増加を引き起こすことが、研究によって示されました。
短鎖脂肪酸(SCFA)は、腸内を弱酸性に保って悪玉菌の増殖を抑制し、腸内環境を整えます。
また、食欲制御や概日リズムにも寄与しているほか、短鎖脂肪酸のレベル低下とうつ病発症リスクの関連が示唆されています。
さらに、短鎖脂肪酸には腸の蠕動運動を活発にする作用もあるため、より高い排便促進効果が期待できるのです。
免疫機能への波及効果
ある研究では、アレルギーのリスクが高い赤ちゃんにガラクトオリゴ糖(GOS)とフラクトオリゴ糖(FOS)のミックスを含む粉ミルクを飲ませたところ、アトピー性皮膚炎の発症率が大きく下がったという結果が出ています。
また、65歳以上の高齢者にガラクトオリゴ糖を10週間摂取してもらった研究では、腸内のビフィズス菌が増えたほか、体内の“炎症を抑える物質”が増えたことが分かりました。
ただし、免疫への影響は個人差や研究の条件により異なる可能性があるため、今後の研究が期待されています。
ガラクトオリゴ糖が多く含まれる食品
- 乳製品(特に発酵乳、ヨーグルトの一部)
- 大豆製品

フラクトオリゴ糖(FOS)
フラクトオリゴ糖は、タマネギやアスパラガスをはじめとした野菜や、バナナなどの果物に含まれている、自然食品に多く含まれるオリゴ糖です。
腸内で、善玉菌であるビフィズス菌に良く利用される一方で、悪玉菌のウェルシュ菌には極めて利用されにくいという特徴があります。
臨床試験で証明された効果
2007年に発表された臨床試験の結果では、フラクトオリゴ糖がヒトの腸内でビフィズス菌を増加させることが明確に証明されています。
試験は健康な成人を対象に行われ、一定期間フラクトオリゴ糖を摂取してもらい、便中のビフィズス菌の量を調査しました。
その結果、被験者の便中のビフィズス菌が有意に増加しただけでなく、腸内の有害な細菌の増殖が抑えられ、腸内環境の改善が期待できることが示唆されました。
便の状態を正常化
一度の大量のフラクトオリゴ糖を摂取すると下痢が誘発されますが、適度な量の摂取であれば腸内細菌叢が改善され、便の状態が正常化することが分かっています。
ある研究では、フラクトオリゴ糖8gを含む食品を高齢者に2週間摂取させたところ、便の硬さが改善され、8日後に正常な硬さへ変化しました。
短鎖脂肪酸を産生
フラクトオリゴ糖は難消化性のため、胃酸などで分解されずに大腸まで到達します。大腸でビフィズス菌をはじめとした腸内細菌によって発酵され、酢酸や酪酸を産生します。
ミネラル分の吸収を促進
フラクトオリゴ糖は、カルシウムとマグネシウムの吸収を有意に増加させることが、動物実験によって明らかにされています。
ヒトでも同様の傾向が報告されていますが、まだ限定的です。
フラクトオリゴ糖が多く含まれる食品
- タマネギ
- ニンニク
- アスパラガス
- バナナ
- ごぼう

ビートオリゴ糖(ラフィノース)
ビートオリゴ糖は、砂糖の原料となる甜菜(ビート)由来のオリゴ糖で、「ラフィノース」とも呼ばれます。
サトウキビやキャベツ、ジャガイモ、トウモロコシなど多くの植物に含まれています。
ビフィズス菌の数を大幅に増加させて多様性を高める
ある研究では、健康な成人13人に4週間、1日2回ラフィノース(各2g)を摂取させ、腸内細菌の変化を詳しく調査しました。
その結果、ビフィズス菌の割合が平均12.5%から、4週間後には37.2%まで増加。つまり、ラフィノースの継続摂取により、腸内のビフィズス菌が約3倍にも増えたのです。
この研究では、ラフィノースは単にビフィズス菌を増やすだけでなく、複数のビフィズス菌の種類を同時に増やすことで腸内の多様性をサポートすることまで明らかにされています。
アレルギー症状の緩和効果も期待できる
ビートオリゴ糖(ラフィノース)は、アレルギーの発症に関与する免疫のバランスを整えるという研究結果が報告されています。
ある研究では、アレルギーモデルのマウスにビートオリゴ糖を与えたところ、アレルギー反応のカギを握る「Th2細胞」の働きが抑えられ、アレルギーの原因となるIgE抗体の増加も抑えられたことが確認されました。
これは、ビートオリゴ糖が Th1/Th2バランス(免疫の偏り)を整えることに関与している可能性を示しており、花粉症や食物アレルギーのような症状にも良い影響を与えるかもしれないという期待が高まっています。
便を“良い形状”に整えて排便を促進
ビートオリゴ糖の摂取と便形状や回数などの関係について調査した研究では、ビートオリゴ糖の摂取期間中、便秘傾向にあるグループは“好ましい便”の形状とされる「バナナ状または半練り状」の出現率が増加したことが報告されています。
また、全被験者において「コロコロ」もしくは「カチカチ」の便の出現率が有意に減少しました。
便の悪臭を抑制
上記の研究では、ビートオリゴ糖の摂取によって、便の悪臭の原因となるアンモニアやインドールの濃度も有意に低下したことも報告されました。
また、他の研究でもビートオリゴ糖を投与された人は、便中の腐敗物質濃度が顕著に低下したという結果が明らかになっています。
ビートオリゴ糖が多く含まれる食品
- 甜菜(ビート)
- キャベツ
- アスパラガス

このように、3種類のオリゴ糖はそれぞれ異なる特性を持ちながらも、共通してビフィズス菌を中心とした善玉菌の増殖を促し、短鎖脂肪酸を産生することで腸内環境の改善と便通の促進に寄与します。
つまり、ビフィズス菌と摂る際にはオリゴ糖を一緒に摂取することが、非常に重要なポイントなのです。
まとめ | オリゴ糖+ビフィズス菌のWサポートで自然な便通を
腸まで届くオリゴ糖は、ビフィズス菌の“エサ”として働き、腸内環境を整える力を持っています。
特にガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ビートオリゴ糖の3種類は、研究でも便通の改善や善玉菌の増加が確認されている頼もしい存在です。
ただし、ビフィズス菌だけを摂っても、腸内に十分なエサがなければ効果は限定的です。
逆に、オリゴ糖だけを摂っても、腸内のビフィズス菌が少なければ活躍の場は限られます。
つまり、「菌とエサを一緒に取り入れる」ことが、腸内環境改善の鍵。善玉菌を腸に届けながら、腸でしっかり育てることで、自然でスムーズな便通が期待できます。

毎日の食事で必要な量をバランスよく摂り続けるのはなかなか難しいもの。
そんなときは、ビフィズス菌と3種類のオリゴ糖をまとめて補えるサプリメントを上手に活用するのもひとつの方法です。
手軽に取り入れることで、腸活を続けやすくなり、毎日のお腹の快適さにもつながります。
毎日の腸活をより効率的にサポートするために、ビフィズス菌とオリゴ糖をバランスよく配合した製品をチェックしてみるのもおすすめです。
快適な毎日を目指して、今日から始めてみませんか。
【参考資料・出典】
※鈴木秀和. "機能性消化管障害と腸内環境―腸内細菌, 食事因子, 酸, 胆汁酸から―." 日本消化器病学会雑誌 117.10 (2020): 840-855.
※光岡知足. "プレバイオティクスと腸内フローラ." 腸内細菌学雑誌 16.1 (2002): 1-10.
※上野川修一. "腸管免疫とプレバイオティクス." 腸内細菌学雑誌 16.1 (2002): 65-70.
※名倉泰三, et al. "ラフィノース含有スープのヒト糞便内菌叢および排便習慣に及ぼす影響." 腸内細菌学雑誌 13.1 (1999): 1-7.
※藤崎裕之, et al. "ラフィノースの投与による糞便中の菌叢, 有機酸, 腐敗物質に及ぼす影響." ビフィズス 8.1 (1994): 1-5.

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
・管理栄養士
こちらも見られています
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
本記事の内容に起因するいかなる結果についても、筆者および運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。